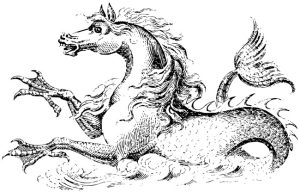コラム「菜園家族 折々の語らい」(7)
コラム
菜園家族 折々の語らい(7)
小さな「地域」から覗く世界の真実
◆ こちらからダウンロードできます。
コラム「菜園家族 折々の語らい」(7)
(PDF:415KB、A4用紙6枚分)
逆行の時代から反転の時代へ
実に不思議なことではあるが、わが国歴代の権力的為政者は、戦後一貫して日本国憲法を嫌い、平然と憲法違反の既成事実を積み重ね、かつての軍国主義日本の道をひたすら突き進んできた。その手口たるや、卑劣としか言いようがない。
1990年代初頭、第二次大戦後の世界を規定してきた米ソ二大陣営の対立による冷戦構造が崩壊し、アメリカ単独覇権体制が成立することになる。しかし、それも束の間、アメリカ超大国の相対的衰退傾向の中、その弛緩に乗ずるかのように、旧来の伝統的大国に加え、新興大国が入り乱れる新たな地球規模での多元的覇権争奪の時代がはじまった。
アベノミクス、それを引き継ぐ高市政権の「責任ある積極財政」、「経済大国」、「軍事大国」への志向は、まさにこの新たな時代に現れた21世紀型「新大国主義」の台頭とも言うべきその本質が、直截的、具体的に現実世界に投影された姿そのものと見るべきであろう。
この時代に注目すべきもう一つの特徴は、ソ連・東欧の「社会主義」体制の崩壊によって、人々がかつて希望の星と仰いだ人類の理想への道に幻滅し、めざすべき新たな未来への道を見失ったまま、自暴自棄に陥っている点にある。地球規模での混迷と混乱の中、剥(む)き出しの欲望が渦巻き、モラルの崩壊、欺瞞と策略の蔓延、暴力と紛争と戦争の常態化を招き、恐るべき暗黒の世界を現出している。
特に「東アジア世界」においては、この間、ソ連・東欧での激変を受け、朔北のモンゴルでも70年間続いた「社会主義」体制が崩壊し、瞬く間にグローバル市場経済の荒波に呑み込まれていった。
中国は、改革開放の時代を経て、今や日本を追い越し、アメリカに次ぐ世界第二位の経済大国となり、習近平国家主席が世界に向かって唱える巨大経済圏構想「一帯一路」のもと、経済的・政治的影響力を拡大し、周辺諸国との軋轢を生み出している。中国「社会主義」はすっかり変質したかのようである。
一方、朝鮮半島に目を向けると、1953年以来休戦状態が続く朝鮮戦争は、超大国のエゴのもと今もって終結せず、冷戦構造の最後の歪みが未解決のまま残存している。北朝鮮は、超大国アメリカの圧倒的な核の脅威のもと、自己の存亡をかけて核開発を急ぎ、核実験とミサイル発射の実験を繰り返してきた。
民衆に壊滅的な犠牲を強いる、勝者も敗者もない一触即発の核戦争の危機迫る中、2018年6月シンガポールでのトランプ・金正恩米朝首脳初会談によって、危機は一時的に凌ぐことができたかのように見えたが、この東アジア地域世界は、依然として爆薬を抱えたまま不穏な情勢が続いている。
こうした中、わが国の為政者は、中国、北朝鮮、韓国という東アジアのもっとも身近な隣国への敵意と憎悪を煽り、この地域世界の民衆に分断を持ち込み、深刻な対立をつくり出している。歴史の歪曲、自己正当化と保身がますます露わになっている。
東アジアの民衆にとって、この地域はどこまで続く泥濘(ぬかるみ)なのであろうか。
米ソ冷戦構造が崩壊し、アメリカと中国の新たな二大超強国が主導するグローバル市場経済が世界を席捲する今、21世紀の今日における「東アジア世界」の逆行的とも言えるこの驚くべき変化をどう見るのか、あらためてこの「東アジア世界」を根本から見直し、新たな視点から現代世界が抱える問題を、そしてわが国をはじめこの地域における諸民族の社会そのもののありようを根源的に捉え直さなければならない。
こうした事態を迎えた中で、あらためて歴史を見つめ直す必要に迫られている。何よりも私たち自身の問題として、身近なところから、新たな視点で「東アジア世界」の中に日本の近代と現代を位置づけて、自覚的に捉え直さなければならない時に来ている。
私たちは今、どんな時代に生きているのか。そこで突きつけられている大切な課題とは、本当は何なのか。そしてそれをどのように解決していくのか。こうした未来への洞察を意識的、持続的におこなっていかなければならない。
「菜園家族」社会構想は、海図なきこの時代にあって、かつての19世紀以来の未来社会論に対して、21世紀私たち自身の新たな未来社会のあり方を探究するものであるが、今述べたような問題意識から、その前提として、民衆の視点から日本の近現代を東アジアの歴史構造の中で捉え直し、自らを、自らの問題として検証することからはじめなければならない。
富国強兵の軍国主義の道を突き進んだ近代日本が東アジアにおいて過去に犯した行為が、この地域の民衆に計り知れなく大きな犠牲を強いてきたことは言うまでもなく、敗戦を経て平和な文化国日本の建設を誓い、歩んできたはずの今日においても、主観的にはどうあれ、客観的に見て、現に東アジア民衆の未来への自立的で豊かな可能性を閉ざし、圧殺さえしているのではないか。
このことは結局、18世紀イギリス産業革命以来、自明の善とされてきた経済成長、「拡大経済」そのものを問い直すことであり、とどの詰まり、21世紀の新たな「東アジア世界」において、社会変革の真の主体となるべきはずの民衆が、今後も近代の落とし子とも言うべき根なし草同然の人間の社会的生存形態、すなわち「賃金労働者」のままであっていいのか、という根源的問題に帰結してくるのではないか。
いずれこのことは、「東アジア世界」の未来を展望する上で、避けては通れない極めて大切な論点になるものと確信している。
新生「菜園家族」日本の未来像と東アジア世界 ―小さな「地域」の視点から考える
こうしたことをふまえるならば、この「東アジア世界」の中にあって、何よりもわが国自身がどんな未来への道を選ぶべきなのか、そのことは自ずから明確になってくるのではないだろうか。
私たちが思想としての「軍国主義」の旧套を敢然として脱ぎ捨て、新たな社会構想のもとに、世界に誇る日本国憲法の究極の具現化の道である新生「菜園家族」日本の道を選択し、着実に歩んでいくならば、それは東アジア民衆との真の連帯に先鞭をつけることになるはずだ。その意義は「東アジア世界」の未来にとって、計り知れないほど大きいと言わなければならない。
日本が変われば、「東アジア世界」は変わる。そして、その逆もまた真である。すなわち、「東アジア世界」が変わるという新たな国際的環境のもとで、日本のこの未来構想の実現の可能性も、いっそう確実なものになっていくであろう。
拙著『新生「菜園家族」日本 ―東アジア民衆連帯の要(かなめ)―』(小貫雅男・伊藤恵子、本の泉社、2019年)には、“菜園家族レボリューション”に固有の相互連関、相互補完の揺るぎない法則とも言うべき普遍的真理と、この地域世界の民衆が長きにわたる苦難の歴史の中で虐げられ、心に秘めてきた悲痛な叫びとさえ思える願いが込められている。
ところで、人間が生きる場としての社会をその基層から構造的に捉え、全一体的(ホリスティック)に考察する上で、私たちが大切にしてきた“地域生態史観”とも言うべき21世紀の新たな歴史観に基づく「地域生態学」的方法論として、以下のことをここであらためて再確認しておきたい。これは、日本のみならず、東アジアをはじめ世界各地のあらゆる社会を考察し、未来を構想する際にも通ずる、普遍的な方法論であると確信している。
私たちが今生きている21世紀現代社会は、分かり易く単純化して言うならば、「家族」、「地域」、「国」、「グローバルな世界」といった具合に、多重・重層的な階層構造を成している。
最上位の階層に君臨する強欲な巨大金融資本が、あらゆるモノやカネや情報の流れを統御支配する。そしてそれは、それ自身の論理によって、賃金労働者という根なし草同然の人間の社会的生存形態を再生産するとともに、同時に社会のその存立基盤そのものをも根底から切り崩しつつ、この巨大システムの最下位の基礎階層に位置する「家族」や「地域」の固有の機能をことごとく撹乱し、衰退させていく。
このことが今や逆に、この多重・重層的な階層システムの巨大な構造そのものを土台から朽ち果てさせ、揺るがしている。まさにこれこそが、近代経済学が機能不全に陥った要因の根源であり、同時に治療の術を失った末期重症の現代資本主義の姿ではないのか。これが今日のわが国社会の、そして各国社会の例外なく直面している現実である。
人間社会の基礎代謝をミクロのレベルで直接的に担う、まさに「家族」と「地域」の再生産を破壊する限り、どんなに見かけは繁栄していても、現代社会のこの巨大な構造は、決して安泰ではいられないであろう。
そうだとすれば、社会の大転換にさしかかった今日の時代においてはなおのこと、経済成長率偏重のこれまでの典型的な「近代経済学」の狭隘な経済主義的分析・視角からは、こうした現代社会の本質をより深層からトータルに把握し、その上で未来社会を展望することはますます困難になってくるのではないか。
私たちは今、このことに気づかなければならない。
21世紀の未来社会を構想するためには、こうした時代の変革期に差しかかっているからこそなおのこと、現代社会のこの巨大な構造の最下位の基礎階層に位置する「家族」や「地域」から出発して、それを基軸に社会を全一体的(ホリスティック)に考察する、“地域生態史観”とも言うべき21世紀の新たな歴史観に基づく「革新的地域研究」が、いよいよ重要不可欠になってきている。
では、ここで問題にしたい括弧付きの「地域」とは、そして21世紀の今日の時代が求めている「革新的地域研究」とは一体何なのであろうか。今あらためて考え直さなければならない時に来ている。
これまで再三述べてきたことなのであるが、「地域」とは、自然と人間の基礎的物質代謝の場、暮らしの場、いのちの再生産の場としての、人間の絆によるひとつのまとまりある最小の社会的、地理的、自然的基礎単位である。
この基礎的「地域」は、いくつかの「家族」によって構成され、日本の場合であれば、多くは伝統的な少なくとも近世江戸以来のムラ集落の系譜を引き継ぐものである。人間社会は、「家族」、基礎的「地域」(=ムラ集落)、さらにはその上位の町、郡、県などいくつかの階梯を経て、より広域へと次第に拡張しつつ、多重・重層的な地域階層構造を築きあげている。
したがって、この基礎的「地域」は、人間社会全体を総合的かつ深く理解するために必要なすべての要素が完全なまでにぎっしり詰まっているがゆえに、社会考察の不可欠にして重要な基本的対象となる。
人間とその社会への洞察は、とりとめもなく広大な現実世界の中から、任意に典型的なこの基礎的「地域」を抽出し、これを多重・重層的な地域階層構造全体の中に絶えず位置づけながら、長期にわたり複眼的、かつ総合的に調査・研究することによってはじめて深まっていく。
特に21世紀現代においては、世界のいかなる辺境にある「地域」も、いわゆる先進工業国の「地域」も、今やグローバル市場世界の構造の中に組み込まれている。こうした時代にあって、自然と人間という二大要素からなる有機的な運動体であり、かつ歴史的存在でもあるこの基礎的「地域」を、ひとつのまとまりある総体として深く認識するためには、(1)「地域」共時態(シンクロニック)、(2) 歴史通時態(ダイアクロニック)、(3)「世界(グローバルな)」場という、異なる三つの次元の相を有機的に連関させながら、具体的かつ総合的に考察することがもとめられる。
こうすることによってはじめて、社会の構造全体を、そして世界をも、全一体的(ホリスティック)にその本質において具体的に捉えることが可能になってくる。やがてそれは、社会経済の普遍的にして強靱な理論に、さらには21世紀世界を見究める哲学にまで昇華されていく。地域未来学とも言うべきこの「革新的地域研究」としての「地域生態学」は、こうして、21世紀の未来社会をも展望しうる方法論の確立にむかうものでなければならない。
それは時代が変わり、社会上部の権力的規制の姿、形が異なっても、基本的にはその本質において何ら変わるものではない。
拙著『新生「菜園家族」日本 ―東アジア民衆連帯の要―』では、こうした問題意識から、現代日本とは時代も地理的にも異なるが、「東アジア世界」全域に散在するあまたの小「地域社会」の中から、特に19世紀、清朝支配下の東部モンゴルの封建領主ト・ワン所領、および20世紀末、「社会主義」体制から市場経済移行期におけるモンゴル西南部の山岳・砂漠の村ツェルゲルを、今ここで述べてきた重要な方法的概念である「地域」として選定し、「家族」とか、「地域」とか、「自然」とか、「人間理解」といった次元の異なる多角的要素を全一体的(ホリスティック)に考察する、この「革新的地域研究」としての「地域生態学」的方法論をたえず念頭に置きながら考察してきた。
こうすることによって、かつてこの「東アジア世界」の片隅の小さな遊牧の「地域」で人知れず支配権力と闘った、民衆の自立への人間的営為の深い意味と、時代的制約から来るその限界が、東アジア近現代の文脈の中で浮き彫りになってきたように思える。
と同時に、それらが決して私たちの置かれた現実とはかけ離れた、遠い異国の見知らぬ人々の物語などではなく、21世紀の今日、冷酷無惨なグローバル市場経済に喘ぎながらも、それでもなお立ちあがって、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている」(日本国憲法前文)日本の、東アジアの、そして世界のすべての民衆の悲願にも連なる、人間の飽くなき試みの一つであることに気づかされるのである。
これら具体的「地域」における民衆の自己の存在をかけた苦闘の姿を丹念に見つめることが、やがて「東アジア世界」の歴史構造の特質と今日この地域世界が直面する課題の把握、さらには21世紀私たちがめざすべき新たな未来への展望へと、次第につながっていくのである。
世界は変わる
人が大地に生きる限り
「菜園家族」の未来社会構想の根底には
人々の心に脈々と受け継がれてきた
大地への回帰と止揚(レボリューション)という
民衆の揺るぎない歴史思想の水脈が
深く静かに息づいている。
まさにこの民衆思想が
冷酷無惨なグローバル市場に対峙し
大地に根ざした
素朴で精神性豊かな生活世界への
新たな局面を切り拓く。
世界に誇る日本国憲法 究極の具現化
新生「菜園家族」日本が
「東アジア世界」の分断と対立の
長きにわたる歴史に訣別を告げ
やがて東アジア民衆の連帯に
先鞭をつけるにちがいない。
◆コラム「菜園家族 折々の語らい」(7)の引用・参考文献◆
奥村皓一『米中「新冷戦」と経済覇権』新日本出版社、2020年
西嶋定生「総説」および「皇帝支配の成立」『岩波講座・世界歴史』第4巻、岩波書店、1970年
江口朴郎『帝国主義と民族』東京大学出版会、1971年
遠山茂樹「東アジア歴史像の検討」『歴史像再構成の課題』御茶の水書房、1969年
山室信一『近現代アジアをめぐる思想連鎖 アジアの思想史脈 ―空間思想学の試み―』人文書院、2017年
小貫雅男『モンゴル現代史』山川出版社、1993年
映像作品『四季・遊牧 ―ツェルゲルの人々―』小貫雅男・伊藤恵子共同制作(三部作全六巻・7時間40分)、大日、1998年
そのダイジェスト版(前編・後編 各1時間40分)をYou Tubeに公開中。
前編 https://youtu.be/8ckpvZv3blc ,後編 https://youtu.be/8WR0TCZd7O0
小貫雅男・伊藤恵子『新生「菜園家族」日本 ―東アジア民衆連帯の要―』本の泉社、2019年
――― ◇ ◇ ―――
★このコラム「菜園家族 折々の語らい」は、これからも随時、掲載していく予定です。
読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2025年12月9日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/