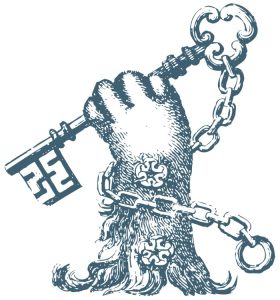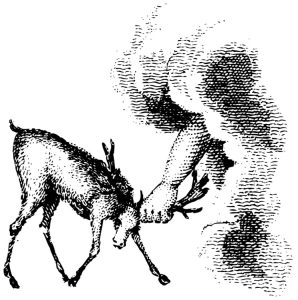コラム「菜園家族 折々の語らい」(12)
コラム
菜園家族 折々の語らい(12)
グローバル市場経済の新たな重圧と東アジア民衆、究極の課題 ④
―朔北のモンゴル遊牧民の苦闘が問いかけるもの―
◆ こちらからダウンロードできます。
コラム「菜園家族 折々の語らい」(12)
(PDF:588KB、A4用紙7枚分)
8.再び踏みにじられた遊牧民の思い ―グローバル市場経済の荒波に呑まれて―
新しい時代への希望を胸にスタートしたはずのモンゴル・ツェルゲル村“ウーリン・トヤー”遊牧民協同組合ホルショーではあったが、アメリカや日本など西側経済顧問言いなりの拙速な市場経済化、長期展望のないその場凌ぎのモンゴル政府の無策、西側追従の金権腐敗政治によって、新生ホルショーの活動は阻まれ、停滞を余儀なくされた。
突如導入された舶来の「市場経済」は瞬く間にモンゴル全土を覆い、社会主義体制下の遊牧の集団化経営ネグデル時代の旧来の流通システムが完全に崩壊し、新興商人が台頭する中、国営農場の解体による小麦生産の壊滅、旧ソ連からの輸入に依存していた石油や日用品の欠乏も相俟って、特に遊牧地域は、物不足、物価高騰、畜産物販売価格の不安定化で疲弊のどん底に陥っていた。
こうした中、ホルショー総会で約束した畜産物の共同出荷と日用必需品の共同購入の活動も、当初から困難を極めることになった。
家畜の私有化によって遊牧民の労働意欲が高まり、この間、気候にも恵まれたこともあって、全国の家畜総頭数は、旧ネグデル体制下では実現できなかった3000万頭を超す勢いで順調な伸びを見せたが、総合的な農牧業政策もないまま、未知なる市場原理の荒波に放り出された地方の遊牧民の暮らしの内実は、むしろ苦しくなっていった。
こうした中で、さらに追い打ちをかけたのが、ツェルゲル村の人々の熱い期待を集めてスタートした分校の国からの予算打ち切りであった。
1998年夏、ツェンゲルさんと分校長の老先生は、ボグド郡中心地の本校長、郡役場および県庁に赴き、窮状を訴えた。1996年の中央での政権交代により、地方の主要な役職もいわゆる民主派の人に総入れ替えになっていた。ツェンゲルさんたちは、思わぬ冷たい反応に驚き、戸惑った。
一行は諦めることができず、はるばる首都ウランバートルまで出向くことになった。文部省および農牧省の大臣に会い、僻地においてこの分校が子供たちの教育にとどまらず、地域づくりの拠点として如何に大切な役割を果たしてきたか、そして遊牧地域の将来にとって、どれだけ大きな可能性を秘めているか、縷々説明し、今後も引き続き、せめても従来通りの予算を確保するよう求めた。
しかしここでも、地方の下々の遊牧民の暮らしより、明日からのアメリカ視察旅行の方が気になるのか、大臣たちは上の空で、やはり聞く耳を持たなかった。
必死の陳情にもかかわらず、ついに翌1999年6月、非情にも予算は打ち切られ、分校は閉校を余儀なくされた。1993年秋の開校以来、先生方や村人たちの並々ならぬ努力によって、学校生活は充実し、教室や校庭には子供たちの笑顔が溢れ、5年制までの拡充を望む声が出されていた矢先の突然の閉校に、村の皆が落胆した。
特にツェンゲルさんは、首都での民主化運動が高揚するかなり以前から、山中のゲルの中でウランバートル発のラジオ放送を聞きながら、民主化運動に期待を寄せていただけに、地方から中央政府に至る民主派の政治家や官僚たちの豹変ぶりには、少なからず精神的ショックを受けたようである。「選挙」で言っていることと、実際にやっていることがそんなに短期間のうちに変わるものなのかと、人間不信にすら陥ったのである。
近頃は、こんなことはもはや慣れっこになってしまったのか、騙される方が悪いと人は言うけれど、権力や権限を持った政治家や役人が自らの保身に汲々として嘘を並べ立て、善良な庶民を騙す方が、よっぽど罪深いのではないか。
この分校廃校の背景にあったのは、国家規模で断行された「教育の構造改革」であった。
1991年、IMF(国際通貨基金)に加盟したモンゴルは、巨額の融資と引きかえに、賃金・価格の自由化、輸入規制の緩和(関税撤廃)、国有・公有財産(家畜を含む)の私有化、国営企業の民営化、商業銀行制度の確立、資本規制の緩和、変動相場制の導入など、一連の新自由主義的政策を国内で実施するよう迫られた。
特に1997~1998年には、国家歳出削減のため、社会保障(教育・保健・年金など)の効率化が迫られ、教育分野においては、都市・地方問わず、生徒20人につき先生1人という一律の基準が押しつけられた。
ツェルゲル村の分校では、1~3年生までの各学年の担任教師3名、分校長先生と教師である妻の合計5人で運営していたのであるが、僻地の村のこと、1学年の生徒は10人前後であり、「教育の構造改革」の求める一律の基準に満たないことになる。ツェンゲルさんや分校長先生たちがどんなに懇願しても、分校の予算が打ち切りとなったのは、背後にこのような国の政策があったからなのだった。
同時に、財政効率化のために県・郡レベルの行政区画の広域合併の必要性が喧伝される中、地方は置き去りにされ、これまで教育・医療・流通・文化など公共サービスの拠点として重要な役割を担ってきた地方中核都市としての郡や県の中心地も、設備が老朽化したまま荒廃の一途を辿った。
ここでまざまざと思い起こされるのが、2000年代初めのわが国の状況である。ソ連崩壊後、アメリカ発の冷酷無惨な新自由主義が全世界を風靡し、日本にも及んできた。小泉純一郎首相(2001~2006在任)は、「構造改革なくして、景気回復なし」を絶叫しつつ、次々と新自由主義政策を強行した。都市における労働者の不安定雇用は急速に増大し、地方においては農山漁村の過疎・高齢化にさらなる拍車がかけられ、限界集落・消滅集落はますます増加の一途を辿り、国土の荒廃が進んでいった。
このような社会の荒廃をもたらしている根っこにあるものは、日本もモンゴルも共通しているのではないかと思えてならない。
こうした地方の疲弊にとどめを刺すかのように襲ったのが、数十年ぶりとも言われる大雪害(ゾド)であった。1999年冬から3年連続で見舞われ、2002年春頃までの間に、モンゴル全土で累計1100万頭の家畜が斃死する壊滅的被害を被った。
社会主義集団化経営ネグデル時代には、各地に冬期用飼料を備蓄する拠点が整備されていたが、ネグデル解散後、それに代わる全国組織が生まれないまま、自然災害への公的な備えや対策も的確にできない状態だったのである。この大雪害は単なる自然災害と言うよりも、人災の側面が大きかったという指摘がモンゴルでも囁かれていた。
大雪害で家畜を失った遊牧民たちは、わずかな現金収入を求めて、夏の間、家族を離れ、金鉱の傍を流れる川のほとりに簡易テントを張って、寝泊まりしながら砂金すくいをしたり、松の実拾いをして市場(ザハ)で売ったりと、「出稼ぎ」を余儀なくされた。
仕事を求めて首都ウランバートルへと移住する者も、年々増加していった。その中には、市場経済移行後、仕事を失い生計が立たなくなった旧国営農場の作業員や、郡・県の中心地の住民たちも多かった。
しかし、首都でも市場経済移行後、新たな産業が生み出されたわけでもなく、これといった当てもなく田舎から出てきた者が、もちろん安定的な職に就けるはずもなく、新聞配達、路端での牛乳売り、守衛など、不安定で微細な仕事を転々としながら何とか食いつなぐほかない。
中心市街地のアパートにも入居できず、地方から持ってきたゲルを郊外に建てて住みつく。水道や下水処理などの生活インフラも未整備なまま、こうした貧困層居住エリア「ゲル地区」が、首都周縁の丘陵一帯に無秩序に拡大していった。
市場経済移行直後の1992年に57万人(総人口に占める割合26%)であった首都人口は、 2001年には81万人(同33%)、さらに2012年には131万人(同46%)に達した。広大な草原の国モンゴルにあって、総人口の実に約半数が首都ウランバートルに加速的に一極集中するという異常事態に至っている。
そして、そのうち約6割が「ゲル地区」に居住することとなった。貧困の中で、栄養不足の子供たちにくる病が目立つようになり、社会の急激な変化についていけない失意の人々の間に、アルコール依存や家庭内暴力、児童虐待、家庭崩壊が増加した。
一方で、本コラム(11)で触れたバウチャー方式による国有・公有財産の所有分割をきっかけに、一部の新旧エリート層に財産や利権が集中することとなり、これらの人々は、外国資本と結びつき、国内外の人脈を利用しながら利権を拡大していった。
こうして、新興財閥とそれに癒着した政治家など一握りの富裕層が形成され、金権政治、汚職が蔓延る一方で、圧倒的多数の民衆は、格差の拡大と貧困に喘ぐことになった。
このような事態を招いた根本には、市場経済移行後、どのような理念のもと、何を基盤に、自らの「地域」を、そしてモンゴルという国を築いていくのかという国づくりの展望において、その根幹となるべき主体的思想の欠如、ないしは未成熟があったことを指摘せざるを得ない。「羮(あつもの)に懲(こ)りて膾(なます)を吹く」という言葉があるが、「社会主義」崩壊後、それに代わる未来社会とは何かを長期展望のもとに考える意欲も視野も失われ、目先の私事に競うように埋没していったのである。
新しく台頭した「民主化運動」の若い指導者たちは、旧体制の幹部の比較的恵まれた家庭の出身者が多く、モスクワなど社会主義圏に留学した経験もある都市型のエリート層・知識層であった。彼らは、党組織や官僚の最上層部には入れない中堅幹部の子弟として、旧体制に漠然とした批判や不満を持ってはいたが、自国の基盤であるはずの遊牧とその地域の暮らしの実体験がなく、実情も知らなかった。今後、モンゴルが西側先進工業国のように経済成長を遂げ、発展していくためには、遊牧など非効率的で時代遅れのものである、と考えていたのである。
古来モンゴルの自然に適合的な遊牧という伝統的な生産と暮らしのあり方や、「地域」の特性を熟知した上で、モンゴル独自の未来構想をじっくり主体的に練ることなど、まさに舶来の「自由選挙」なるものによって突如選ばれた、こうした新時代の政府や政党の若いひ弱な幹部たちには望むべくもなかった。
その結果、外国からの「援助」・投資に安易に依存した地下鉱物資源(石炭・金・銅・モリブデン・ウラン・その他レアメタル・レアアース)の開発とその輸送網(鉄道・舗装道路)の建設に偏重した国土開発計画が、無批判に立案されていった。
先に見たツェルゲル村の分校廃校についても、1996年に人民革命党から政権交代した民主同盟政権(~2007年7月)のもとで進められた「教育の構造改革」の一環での出来事であったのだ。
ツェンゲルさんは、硬直した旧体制に早くから批判を持ち、遊牧民たちとともに分校開校と独自の地域づくりに奮闘し、民主同盟にも期待を寄せていただけに、分校廃校の仕打ちは、裏切られたという思いが強く、その精神的ショックは相当に深かったようだ。
ツェンゲルさんは、その後どうなったのであろうか。
その後も現地調査を続けていた今岡良子氏(大阪大学外国語学部准教授)や山本裕子さん(当時、大阪外国語大学院生)たちの報告によると、1999年夏に分校が廃校となった後、ツェンゲルさん家族は村を離れ、ボグド郡中心地へ出て行った。ヤギをはじめ数百頭の家畜は、村に残る弟家族に世話を託した。そして、ほどなく県の中心地へと移住し、その一角に板塀でぐるりを囲んだ敷地内にゲルを建て、住まいとした。
ツェンゲルさんは、村の旧知の遊牧民から家畜を仕入れ、この町の市場(ザハ)で食肉を売るが、一家の生活に十分な安定した収入にはならない。家で子守りをしたり、金鉱帰りで顔を真っ黒にし、泥だらけになって時折訪ねて来る同郷の人々の相談に乗ったり、優しさは変わらないが、かつての気力はなく、めっきり痩せて白髪が増えた。酒に任せて荒れることもあったという。子供たちの大学進学だけが唯一の望みとなっていた。
奥さんのバドローシさんが市場(ザハ)に小屋を借り、食堂(ゴアンズ)を切り盛りして生計を支えた。高校生に成長した長女スレン、次女ハンドも、水汲み、肉の仕込み、手打ち麺の支度などをして母を手伝うとともに、学校帰りに小さな日用雑貨売店(キオスク)の店番をして、家計を助けた。それでも足りない分は、村に残してきた家畜から少しずつ売って現金にし、生活費に充てた。
そこへきて、先述の数年続きの大雪害が襲った。
2002年夏、ツェンゲルさんから人づてに私たちのもとに届いた手紙には、「もう(オドー)家畜(マル)は尽きてしまいました(ドーススン)」と綴られていた。遊牧民にとって命にも劣らぬほど大切な家畜という生産手段を、すべて失ったのである。この簡潔な一文は衝撃的であった。遊牧民にとってこれほど決定的なことがあるだろうか。「暮らし向きは、ますます辛く厳しくなっていくようです・・・」と手紙は続いていた。
希望に満ちたあの遊牧民協同組合ホルショーの結成から、10年目のことであった。
9.岐路に立つモンゴル ―揺らぐ暮らしと平和の礎―
中央政府の政策は、あいかわらず地下鉱物資源の開発・輸出による経済成長の実現をめざすものであった。二大政党間で何度か政権交代が繰り返されたが、政策面で大きな対立軸はなく、IMF路線追随、鉱物資源開発で見込まれる利益の国民への「ばらまき型」で、いずれにしてもその大枠において大差はなかった。
「資源立国」を掲げ、2009年には、南ゴビのオユトルゴイ銅・金鉱床開発に関わる投資契約をカナダの鉱山大手企業との間で締結した。2010年には、60億トンを超える埋蔵量が眠る、世界最大級の南ゴビのタワントルゴイ炭田の採掘権を国際入札する方針を決定。隣国である中国、ロシアの二大国に加え、アメリカ、日本、韓国、イギリス、オーストラリアなど、世界の資源メジャーが入札に名乗りを上げ、利権獲得競争が過熱していった。
しかし、資源開発に極端に依存したモンゴル国内の経済基盤は脆弱で、資源ブームの2011年に17.3%だった経済成長率は、中国の景気後退などで鉱物資源の需要が落ち込み、価格が下落すると、2016年末には1.3%に急落する見通しとなった。外貨準備は急減、通貨トゥグルクは暴落した。
財政も急速に悪化し、対外債務不履行の危機に直面していたモンゴルは、2017年2月、IMF(国際通貨基金)・ADB(アジア開発銀行)・日本・中国・韓国などから、3年間で総額55億ドル(約6200億円)の緊急支援を受けることで合意した。その条件として、IMF管理下で財政緊縮策の推進を受け入れることとなった。それは、社会保障費のカットなど弱者切り捨て、民衆生活の圧迫、社会の不安定化につながるものと言わざるを得ない。
市場経済への移行から25年余、ついにモンゴルは、累積した借金をさらなる借金で返済するという悪循環の泥沼に陥った。大国追従の市場経済第一主義政策は、明らかに破綻した。
モンゴル経済は中国経済に過度に依存しており、中国資本の進出が顕著で、最大の貿易相手国も中国である(2017年、輸出の85パーセント、輸入の33パーセントが対中国でともに第1位)。特に近年では、中国が押し進める習近平国家主席主導の巨大経済圏構想「一帯一路」の中で、モンゴルは「中蒙露経済回廊」の一環に位置づけられている。
しかし、地下鉱物資源開発・輸送による草原・砂漠の荒廃、河川・泉・地下水の汚染など環境破壊、市場経済に翻弄される遊牧の生産と生活のあり方、首都での貧困問題・大気汚染の深刻化等々、モンゴルの人々の暮らしがその基盤から脅かされ、風土に根ざした地域づくり・国づくりの主体性が損なわれれば、いずれ遠からず圧倒的多数のモンゴル民衆からの大きな不満と反発を招くことにならざるを得ないであろう。
一方、ソ連崩壊後、アメリカもモンゴルへの影響力を強め、台頭する中国・ロシアの二大国の勢力圏に食い込むかのように、この東アジア地域の力学に不安定要因を加えている。モンゴル政府も、中・ロの影響力抑制のため、日米を主体とした「第三の隣国」との関係強化を指向し、巨額の経済支援と引きかえに軍事協力が進行している。
2001年9・11アメリカ同時多発テロ、続く2003年対イラク戦争に際して、モンゴル政府は、日本の小泉首相(当時)に続き、いち早くアメリカ・ブッシュ政権の方針に支持を表明。2003年からアフガニスタン・イラクへの派兵に応じた。
また2004年には、アメリカは、ウランバートル郊外の草原で「反テロ」を名目に国連平和維持活動(PKO)の合同軍事演習「カーン・クエスト」を実施。アメリカ軍・モンゴル軍を主体に7ヵ国が参加し、日本の自衛隊もオブザーバーとして参加した。以後、この多国間共同訓練は毎年続けられ、2017年には27ヵ国、約1000人が参加する規模に至っている。アメリカは、この演習基地タワントルゴイ(旧ソ連軍訓練基地)の整備とモンゴル軍将校の強化育成のため、2005年、巨額の資金(それぞれ1100万ドル、1800万ドル)を供与している。
「カーン・クエスト」には、2015年からは中国人民解放軍も参加、日本の自衛隊も「戦争法案」を先取りする形で、それまでの教官要員に加えて訓練部隊を送り、「巡回」「検問」などの訓練に参加させている。2017年には「駆け付け警護」、2018年には暴徒と化した群衆の鎮圧、食糧配給所に見立てた施設の武装警備など、武器使用を伴う実動訓練をおこなっている。安倍政権(当時)は、ここでも憲法違反の既成事実を着々と積み上げようとしてきた。
さらに、2024年12月、日本とモンゴル両政府は、二国間で防衛装備品の輸出入を可能にする「日・モンゴル防衛装備品・技術移転協定」に署名、2025年1月に発効した。2024年9月に岸田首相(当時)とフレルスフ大統領が、早期署名を目指す方針で一致していたものである。
日本は、同様の協定をアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オーストラリアのほか、インド、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイなどアジア諸国との間でも締結を広げており、モンゴルは16ヵ国目となる。
日米軍事同盟 対 超大国中国・ロシアの危険な鍔(つば)迫り合いの最前線と化した「東アジア世界」。
21世紀、「東アジア世界」の新たな歴史段階に突入した今日、多元的覇権争奪がもたらす深刻な矛盾と混迷は、まさにこの地域世界の「辺境」に位置する小国モンゴルに、凝縮された形で如実に表現されているのである。
◆コラム「菜園家族 折々の語らい」(12)の引用・参考文献(一部映像作品を含む)◆
小貫雅男・伊藤恵子『新生「菜園家族」日本 ―東アジア民衆連帯の要―』本の泉社、2019年
小貫雅男『モンゴル現代史』山川出版社、1993年
映像作品『四季・遊牧 ―ツェルゲルの人々―』小貫雅男・伊藤恵子共同制作(三部作全六巻・7時間40分)、大日、1998年
そのダイジェスト版(前編・後編 各1時間40分)をYou Tubeに公開中。
前編 https://youtu.be/8ckpvZv3blc ,後編 https://youtu.be/8WR0TCZd7O0
伊藤恵子「遊牧民家族と地域社会 ―砂漠・山岳の村ツェルゲルの場合―」滋賀県立大学人間文化学部研究報告『人間文化』第3号、1997年
村井宗行「1990年代モンゴルの政治と経済 ―1990年代モンゴルをどのように評価するか―」『モンゴル研究』第18号、モンゴル研究会(大阪)、2000年
村井宗行「エンフバヤル政権の性格 ―2000~2004年―」『モンゴル研究』第24号、モンゴル研究会、2007年
今岡良子「2002年夏のツェルゲル ―ゾドの後はゴールドラッシュ、首都ラッシュ―」『モンゴル研究』第20号、モンゴル研究会、2002年
山本裕子「バヤンホンゴル県 バットツェンゲル家滞在記 2002年」『モンゴル研究』第20号、モンゴル研究会、2002年
長沢孝司・今岡良子・島崎美代子・モンゴル国立教育大学ソーシャルワーク学科 編著『モンゴルのストリートチルドレン ―市場経済化の嵐を生きる家族と子どもたち―』朱鷺書房、2007年
――― ◇ ◇ ―――
★このコラム「菜園家族 折々の語らい」は、これからも随時、掲載していく予定です。
読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2026年1月30日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/