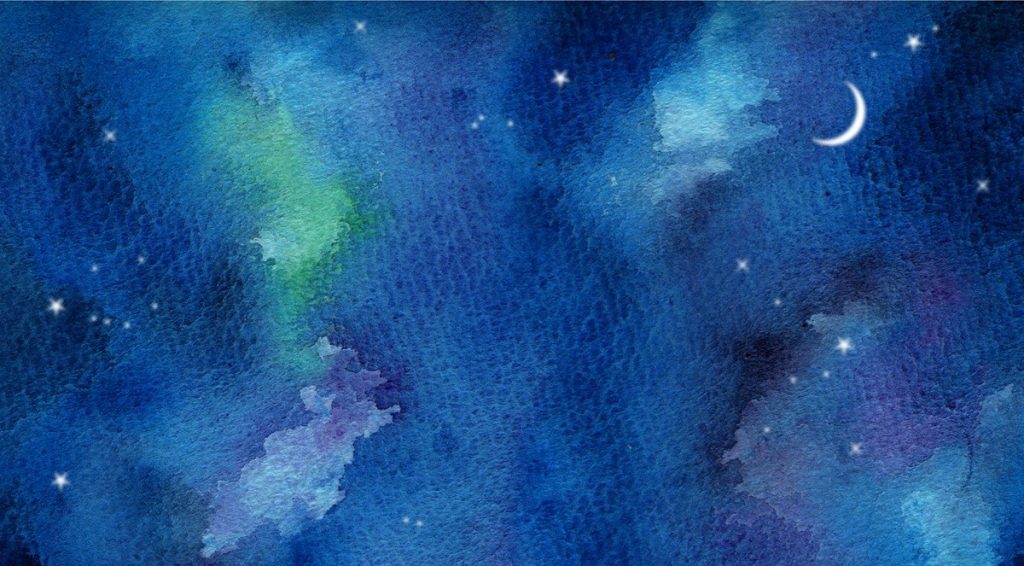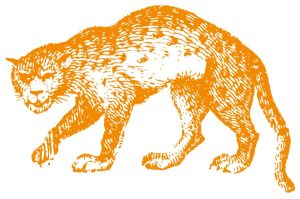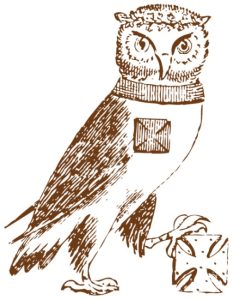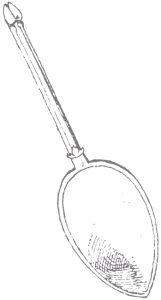コラム「菜園家族 折々の語らい」(10)
コラム
菜園家族 折々の語らい(10)
グローバル市場経済の新たな重圧と東アジア民衆、究極の課題 ②
―朔北のモンゴル遊牧民の苦闘が問いかけるもの―
◆ こちらからダウンロードできます。
コラム「菜園家族 折々の語らい」(10)
(PDF:561KB、A4用紙9枚分)
ここからは、20世紀末のソ連崩壊と冷戦構造の終結から21世紀の今日にかけて、市場経済至上主義グローバリズムの激動の時代に、「東アジア世界」の民衆がどんな現実に直面し、どのような歴史的課題を新たに背負うに至ったのか、朔北のモンゴル、山岳・砂漠の村ツェルゲルという具体的な一「地域」を取り上げ、遊牧民たちの苦闘とその歴史的背景を辿ることによって、浮き彫りにしていきたいと思う。
今回は、ツェルゲル村での新たな“模索の動き”に入る前に、まずは、20世紀のモンゴルにおいて、遊牧の集団化という特異な社会主義への実験がどのように進められ、またそれがいかなる問題を孕んでいたのかについて、概観しておくことにしよう。
4.モンゴルにおける遊牧の社会主義集団化、その生成と衰退の小史
今からおよそ100年前、1921年7月11日に樹立されたモンゴルの人民政府は、当初から想像を絶する困難を抱えていた。
首都クーロン(現在のウランバートル)を制覇したものの、この都市を一歩出れば広大な遊牧地域が広がっていた。地方の行政組織は、清朝支配下の封建時代におけるザサック・ホショー制がそのままであり、封建領主や寺院勢力が旧態依然として地方を支配していた。国家の財源一つ見ても、ゼロからの出発であった。
旧聖俗封建領主は、その政治支配権を失ったにもかかわらず、巨大な経済力を残していた。1924年の時点で、旧封建領主はジャス(寺院領)を合わせて、全国家畜頭数の約35パーセントを所有していたと言われている。
1929年のアメリカ・ニューヨークの株式暴落を画期に、資本主義世界は大恐慌となった。この経済恐慌は、帝国主義諸国の矛盾を先鋭化させ、ドイツ、イタリア、日本では政治のファシズム化が進み、東と西に戦争の新たな火種が生まれた。
東アジアでは、日本が1931年9月、中国東北を侵略、やがて「満州国」を宣言して市場の獲得とソビエトに対する防壁の構築を狙い、中国を足場にシベリア進出を考えるようになった。「満州」を占領した日本は、モンゴル東部国境のハルハ河に向けて、飛行場・舗装道路・鉄道を敷設して、戦闘準備をはじめ、ついに1939年、ハルハ河戦争(ノモンハン事件)を仕掛けたのである。
このハルハ河流域は、清朝皇帝を頂点とする冊封体制下の19世紀前半、モンゴル在地の封建領主による二重の不条理な支配に抗して、遊牧民トゥデッブらが自らの生存と「地域」を守るために果敢に闘った、あのト・ワン所領の地である。
それからほぼ100年の後に、今度は日本帝国主義の軍隊がこの地を踏みにじったことになる。
モンゴル国内では、1920年代後半から封建勢力の反革命活動が活発化し、階級闘争が先鋭化した。こうした緊迫化した内外情勢を背景に、人民政府は、封建領主の家畜財産没収計画を1929年から1930年にかけての冬に集中的に強行した。さらに一定の家畜所有以上の富裕牧民を敵と看做し、多数の遊牧民家族を集団化経営コルホーズに加入させる計画を並行して強行したのである。
ソ連では、1929年11月、農業の集団化に対して穏健な態度をとっていたブハーリンを党政治局から除名し、スターリンは12月になると全面的集団化に向けて「大転換」をおこなった。まさにスターリンがおこなったことと符合するかのように、モンゴルでも遊牧の集団化が強行されていったのである。
1930年~1931年のこの時期のこうした運動の中で、一般の民衆に対しても上からの強制や命令が貫徹され、民主主義は損なわれ、専制的強権体制が地方へも浸透していった。遊牧民の小規模な個人所有家畜に対しても攻撃が加えられた結果、遊牧民は萎縮して経営拡大への積極性が失われ、家畜総頭数は激減していった。このような中で、遊牧の集団化の試みも頓挫した。
1945年8月15日、日本帝国主義の崩壊によって、極東での日本の脅威が一気に後景へと退き、モンゴルは、戦時体制下で疲弊しきった経済を建て直す絶好の機会を得ることになった。
1947年12月、モンゴル人民革命党の大会が開かれた。この大会の最大の任務は、国民経済・文化を計画的に運営し発展させる社会主義への基礎を準備するために、第一次五ヵ年計画(1948~1952)を策定することであった。この5ヵ年計画は、家畜総頭数を5年後に50パーセント増の3200万頭にまで増やす目標を設定し、耕地の拡大と工業・運輸・通信を発展させることであった。
しかし、結果的には、家畜頭数の増加は、目標をはるかに下回る8.6パーセント増にとどまった。この不振の原因を、私的所有は悪で、家族小経営は遅れたものであるという固定的な観念に基づき、小規模な遊牧民家族経営には将来性がないことに帰した。
引き続き1952年11月には、第二次五ヵ年計画(1953~1957)が採択された。しかし、依然として主要産業である牧畜部門の不振は根強く、この期間中に家畜総頭数の目標2750万頭に達することができなかった。この時もやはりその原因を、3分の2の家畜が個人の遊牧民家族経営の手中にあったからだと総括したが、そこに原因を求めるのは明らかに誤りであろう。牧畜部門に対するこうした考え方が、その後の数十年間の歩みを決定づけてしまったのである。
1958年3月、党大会が開かれ、1958年から1960年の三ヵ年計画が検討され、採択された。大会は、今後3年間で遊牧民家族経営を自発性の原則に基づいて全面的に協同組合化することを確認し、家畜総頭数増加の決定的条件は、飼料供給基地、井戸など水の問題、獣医のサービスの問題に留意することであった。
工業部門では、石炭・電力・建築資材の生産を拡大し、石油工業の生産高を上げ、鉱業資源、非鉄金属を大いに増産することであった。この期間に工業生産の平均成長率は、17.9パーセントであった。この3年間の投下資本額は、第二次五ヵ年計画の期間を49パーセントも上回った。
1950年代の後半を過ぎると、東ヨーロッパ・中国でも農業の集団化が進展していく。こうした国際的時代状況を背景に、モンゴルにおいても二次にわたる五ヵ年計画と三ヵ年計画の中で明らかになった牧畜業の不振と相俟って、遊牧の集団化が必然的なものであるとする意識がますます助長されていった。この意識の特徴を要約すると、おおよそ次のようになる。
人口の増加、工業と都市の定住化の飛躍的発展により、食糧や工業原料の十分で安定的な供給基盤が必要になってきた。このような経済的要求を、規模の小さな分散的な個人遊牧民経営ではもはや満たすことはできない。社会主義的な都市への定住と工業原料は、高い生産性をもつ遊牧の社会主義的集団化による大経営によってのみ満たされる。また、社会主義的思想を発展させることが、社会主義建設においては重要課題であり、そのためにはプチブル思想の温床となる個人家族小経営を遊牧の社会主義的大経営へ変革することが必要である、といった主張なのである。
1959年12月、モンゴル人民革命党中央委員会総会は、協同組合化の実践が成功裏に完了したことを確認し、それを受け、農牧業協同組合全国大会では、農牧業協同組合(ネグデル)模範定款が採択された。
1959年末には、全国の遊牧民家族経営はネグデルに全面的に加入し、集団化は完了した。1960年からネグデルの時代がはじまったのである。1989年末に民主化運動が高まり、市場経済に移行し、1991年の末にネグデルが解体するまでの30年間、ネグデルの時代は続くことになる。
第三次五ヵ年計画(1961~1965)の時点で見ると、ネグデルは全国で284に達し、1ネグデル平均で構成員は900名、家族数480戸、家畜頭数7万2700頭、保有地47万ヘクタール、トラック6台、トラクター3~4台であった。ネグデルの共有家畜は全家畜頭数の77パーセントを占めた。1965年には、播種面積15万3200ヘクタールで14万トンの穀物を収穫するまでになった。伝統的な遊牧社会では耕作の習慣がなかったことを考えると、これはネグデル時代の大きな特色とも言える。
こうしたネグデルの急成長を支えたのは、人材であった。ネグデルの内部で時間をかけて自然に養成されたというよりも、中央政府の主導のもとで急拵えに準備され、派遣されたものであった。この期間中に、政府はネグデルのために幹部や会計士、トラクターやコンバインの運転手、建築専門家など数百人もの専門要員を講習会で養成し、農牧業の高等専門家1000人、中等専門家2000人を養成してネグデルに送り出した。
基本的には1つの郡に1つのネグデルが組織されるようになっていき、その中心地には、ネグデル管理部をはじめ、郡役所、病院、公共浴場、小中髙校、寄宿舎、幼稚園、小さな図書館、映画館、娯楽センター、電話局・郵便局、ラジオ中継局、発電所、売店、食堂、公務員・教師・専門技術者などのための住宅が建ち並び、定住地として整備されていった。
広大な草原の中に、このような新しい地方小都市の萌芽が全国で250~300ヵ所形成され、農牧業の発展にとどまらず、国土の発展にとって計り知れない大きな意義をもつことになった。
しかし、その後、、五ヵ年計画のたびに労働の生産性の向上を目標に掲げ、一方では農牧業の大規模化・工業化をめざし、機械・設備の大量投入を繰り返したが、家畜頭数はいっこうに増えず、低迷を続けていった。
1987年12月、ついに党中央委員会総会は、はじめて公式に農牧業生産の停滞を認めて、方針を大きく転換し、牧畜の生産請負制を導入し、実質上、個人所有家畜の制限を撤廃するに至った。
さらに「民主化」後の私有化法に基づき、1991年8月頃から家畜の私有化が急速に進み、1992年1月からネグデルの解体がはじまった。ネグデルの時代は、1960年にはじまり30年間でその幕をおろしたのである。
封建制が1921年の人民革命によって打破された時、その廃墟には民主的制度はまったく見られなかった。すべてがゼロからはじめなければならなかった。国家大ホラル(後の人民大ホラル、国会に相当する)にしても、地方行政制度にしても、選挙制度にしても、遊牧民の自発性に基づいて結成されたはずのネグデルにしても、民衆が自らの手で時間と年月をかけてつくりあげたものではなかった。すべてが上からのお仕着せであった。
こうした中で上層の独裁権力の強化が進行していく時、お仕着せられた民主的諸制度や、組織の規約・定款上の民主的文言だけが残されることがあったとしても、その民主的内実の空洞化は避けられないことであった。モンゴル社会の上から下まですべてのレベルにおいて、またすべての分野の隅々に至るまで、建て前と本音のまったく違う実態が蔓延していった。
よその国のことだ、時代が違うなどと言って、笑っていられる場合なのだろうか。今日の私たちの国ではそんなことはないと、本当に言い切れるのであろうか。もっと巧妙かつ狡猾に、しかも大がかりに、民意を反映しない偽りの「議会」装置で国民の不満や怒りをガス抜きし、反国民的な政治をぬけぬけと、しかも「合法的」にごり押ししつつ、支配権力の思うがままに進めているのではないか。
それはさておき、こうした民主主義の根幹に関わる問題を、1960年からはじまったネグデルを具体的に例に挙げて見ることにしよう。
ネグデルの定款では、ネグデルは自発的に加入した遊牧民によって構成されると書かれている。ネグデル総会が最高の議決機関であり、ネグデル長をはじめ管理部門の役員は、ネグデル構成員による選挙で選ばれるとなっている。
しかし実際は、自発的な加入でありながら、そうはなっておらず、遊牧民はネグデルの末端の単位組織ソーリに縛りつけられていた。ネグデル長は、地元のネグデルとはまったく関係のないところで決められ、ほとんどが首都ウランバートルの党大学出身者の中から人選され、任命され、派遣されていたのも同然であった。遊牧民たちの意思によってネグデルが管理運営されることはなく、ただ上からの命令によって働かされていた。
国家や地方行政も、その他のすべての組織や機関もまた然りであった。こうした社会が国家権力の監視の下に維持されるとするならば、その結果、国家はますます強権化し硬直していくのは当然であろう。
ネグデル30年間の歴史の中で、莫大な資金と機械設備と労働力が投入されながら、結局、農牧業が低迷し続けていったことの原因も、こうした視点から見直すことによって解明されるのではないか。つまり、直接生産者である遊牧民たちの自発性・創意性を最大限に発揮できる生産と生活の組織として、ネグデルは存在していなかったのである。定款上、形式の上では民主主義は整えられていても、大多数の直接生産者である遊牧民にとって、民主主義はまったく欠落していたのである。
ネグデル30年間の歴史の最末期に当たる1984年8月23日、党中央委員会臨時総会は、1963年に独裁体制を固め、長年にわたって党と政府の権力を掌握してきたツェデンバルについて、その健康状態を考慮して、書記長兼政治局員の職務から解任し、新書記長にバトムンフを選出した。1984年12月、バトムンフは人民大会幹部会議長に選出され、ソドノムが首相に選ばれた。
ツェデンバルは解任される4年前の1980年頃から、アルコール依存症に加え記憶喪失症にも悩まされ、党政治局会議において議長をつとめながら、同じことを何度も繰り返し聞き返す始末で、両側に2人の政治局員が着席し補佐して会議をおこなっていたという。このような状態にもかかわらず、解任までの4年間、党の最高指導者・議会の最高責任者をつとめていたこと自体が、ツェデンバル体制末期の国家の性格を如実に物語っている。
この国家の性格とは、40年間繰り返し繰り返しおこなわれてきた五ヵ年計画を無難に繕う「官僚主義的保守性」、「臆病」、「忖度」、「凡庸さ」、「追従」、「腐敗」、「停滞」、「老人支配」、「傲慢さ」、「保安と統制」などであった。これは、「社会主義」国に限らず、どこの国にも通ずる問題なのだ。
1984年にツェデンバルに代わって登場した党政治局員バトムンフ、ソドノムらの新政権が民主化運動の高揚の中で1990年3月に退陣するまで、ツェデンバル体制は本質的には同質のものとして継承され維持されたのであった。
5.モンゴルの「社会主義」はなぜ崩壊したのか
―遊牧の社会主義集団化経営ネグデルの根底から考える―
遊牧の基盤は「家族」であり、それは、ものの再生産の場であるとともに、人間のいのちの再生産の場でもある。そして、この「家族」には、人間発達を促す諸機能の萌芽が未分化のままぎっしり詰まっている。炊事や育児・教育・医療・介護・こまごまとした家事労働など、暮らしのあらゆる知恵、牧畜生産の総合的な技術体系、手工芸・手工業や文化・芸術の萌芽的形態、それに娯楽・スポーツ・福利厚生の芽、相互扶助の形態、共同労働の知恵などなど。「家族」は他に類例を見ない、優れた人間の社会構造上の最小の基礎的共同体なのである。
こうして大地に根ざして生きてきた「家族」には、大地と人間をめぐる物質代謝の循環に適合したゆったりとした時間の流れの中で、自然との共生を基調とする価値観、これに基づく人生観や世界観が育まれ、人々は気の遠くなるような長い年月をかけて、これにふさわしい生き方を築きあげてきた。
この「家族」を補完するのが、伝統的な隣保共同体ホタ・アイルであり、さらにその上位の次元の共同体サーハルトである。隣近所に住む数戸の遊牧民家族が、個々の家族の中だけではこなすのが難しい生産労働(放牧、毛刈り、フェルトづくり、家畜小屋の修繕、食肉の準備、四季の幕営地の移動など)、日常の暮らしの中での仕事(水くみ、薪拾い、炊事など)、世代を結んでの協力(遊牧技術・暮らしの知恵の伝授、出産・子育ての協力、老齢者への扶助など)、自然災害(旱魃・洪水・雪害ゾド)への対策などで互いに助け合うのである。
つまり、これら伝統的な隣保共同体は、苛酷なモンゴルの自然の中で生きぬくために、なくてはならない共同の力なのである。モンゴルには、「ホタ・アイルのいのちは一つ、サーハルトの心は一つ」という諺があるほどである。
本コラム(7)の中で、「地域」とは何かについて述べたが、モンゴルの遊牧社会においては、まさにこのホタ・アイル、サーハルトといった家族機能を補完する多次元の共同体から成る重層的な団粒構造のコミュニティこそが、一つのまとまりある遊牧「地域」であり、それは、総合的で豊かな人間発達の場、独自の文化醸成の場、そして村落自治、草の根民主主義熟成のかけがえのない場としての可能性を秘めた基礎的「地域」というべきものなのである。
17世紀の後半に清の皇帝を頂点とする国家的封建制(冊封体制)がモンゴルにも及び、確立され、直接生産者である遊牧民は、その体制下に編入されていくのであるが、このような支配上層の権力編成の変化によっても、遊牧民家族経営を補完するもっとも身近な隣保共同体としての伝統的ホタ・アイルは、基本的には変わらず維持されていった。
東部モンゴルのト・ワン・ホショーで闘われた遊牧民トゥデッブらの訴訟闘争をはじめとする、19世紀前半から全国的に展開された反封建・反清の牧民運動、さらに20世紀初頭の遊牧民アヨーシの長期にわたる訴訟闘争に代表される牧民運動の高揚の基礎に、この伝統的ホタ・アイル共同体の本質とも言うべき、直接生産者の自治組織としての民主的な性格があることに注目しなければならない。
モンゴルにおける遊牧の集団化は、1980年代最終期には、255の農牧業協同組合(ネグデル)と14の飼料国営農場、51の国営農場に編成され、ネグデルの下位組織であるブリガード787、このブリガードのもとに2~3家族からなる労働組織の基礎単位であり家族の生活の場でもあるソーリが3万3629あって、これらが広大なモンゴルの国土に網の目のようにはりめぐらされていた。
このソーリこそ、伝統的なホタ・アイル共同体の延長線上にあらわれてきてしかるべきはずのものであった。遊牧の伝統的ホタ・アイル共同体がソーリに編入されることによって、社会主義的農牧業協同組合ネグデルは、共有経済の社会的関心と組合員の個人的関心を正しく結合しながら生産と分配を計画的に運営し、それが国民経済の統一的で有機的な一翼として機能していることを前提に、科学・技術の成果を十分に活用する条件をもつはずであった。
こうした中で、モンゴルに特殊な自然条件の中から歴史的に育まれてきた伝統的なホタ・アイル共同体特有の共同労働とか、消費とか、相互扶助の形態や経験の伝統、土着の民主的な性格も、社会主義的改造を遂行する人々の力量によって、ソーリを直接の媒体にして、より高次の段階へと止揚される可能性があったはずなのである。
ホタ・アイル共同体は長い歴史を経て、それ自身の体内にモンゴルに特殊な自然の苛酷さに対する優れた独特の「抗体」をつくり出してきた。しかし、集団化に対する当時の教条主義的な精神からは、伝統的に培われてきたこの「抗体」を評価するなどと言うことは、到底考えも及ばぬことであった。こうした伝統との断絶の上に集団化が可能であるとする浅薄な近代主義的発想に、ネグデル失敗の根源的な原因があったのではないか。
ソ連は、1921年のモンゴル人民革命以後、モンゴルに大きな影響を及ぼし、特に1960年代初頭からは、中ソ対立が表面化するにつれて、モンゴルはソ連の対中戦略の中で重要な位置を占めるに至った。
こうした状況の中で、首都ウランバートルにおける工場・住宅建設のみならず、地方における牧畜の生産基盤、さらには日用雑貨に至るまで、ソ連の援助は地方の遊牧民の生活の中にも浸透していった。
その特徴は、日用品の針1本からアルミのスプーン・食器、衣服や鉄製のベッドに至るまで、すべてできあいのものが提供されたことである。この安価で軽便な商品が大量に遊牧地域に浸透することによって、遊牧民の伝統的な手工業・手工芸は衰退の一途を辿った。その結果、身近な素材を用いて自分でものをつくり出す能力を失い、自分たちが生きる地域の自然を多面的に細やかに活用する能力を失っていったのである。
ネグデルが発足した1960年代の初めに当たる1963年に、全人口の53.3パーセントを占めていた遊牧民人口は、ネグデル末期に当たる1989年には27.8パーセントとなり、全人口の3分の1を切る状態になった。このネグデル30年間の歴史の過程で、モンゴルの全人口が2倍以上になり、その上、全人口の3分の1以下の遊牧民人口が3分の2以上の人口を支えなければならない産業構造に変化してしまったのである。
加えて、1970年代以降、特に工業基盤や農牧業の技術的基盤の形成に力が注がれるようになり、それに伴う機械・建築資材・輸送手段などの輸入増加は、輸出とのアンバランスや借款の埋め合わせを必要とし、結果として牧畜業への負担はいっそう重くなっていった。
こうした中で、広大な遊牧地域からすべての畜産原料が国家調達の名のもとに首都に集められ、この一極集中の経済体制が確立すればするほど、遊牧民の手元に残る余剰の畜産原料は、限りなくゼロに近づいていった。その結果、遊牧地域は、都市のための原料供給基地の地位におとしめられ、伝統的手工業・手工芸は、この原料の面からも衰退へと追い込まれていったのである。
遊牧の社会主義集団化経営ネグデル30年の歴史の中で犯したもう一つの重大な誤りは、自然と深く結びついている農牧業の特殊性を考慮せず、工業の論理をそのまま適用したことである。
ネグデルは、経営を大規模化し、分業と協業を機械的に農牧業に当てはめていった。主要な生産手段である家畜や家畜小屋をはじめ、農牧業機械や運搬手段に至るまでネグデルの共同所有にし、生産性向上のために、家畜群を種類・年齢・性別によって細分化・専門化した。
それぞれの遊牧民家族は、この大規模集団化経営の末端の労働組織であるソーリの一員として、細分化・専門化された共同家畜の一群を担当し、放牧料として月々の賃金を受け取るという、いわば大工場の賃金労働者と酷似した身分に組み込まれてしまった。
本来、遊牧とは、自然と家畜が直接結びついた、変化に富んだ要素を含む複雑かつ総合的な労働である。これに対して大規模集団化経営ネグデルでは、個々の遊牧民は、上部からの極めて単純な指標によって労働の成果が評価され、これに基づいて上から指揮される。遊牧民の労働の自主性・創意性は次第に窒息させられていった。
こうして、労働の側面からも、ネグデルの内部組織の民主主義の芽は摘み取られていったのである。
その上、先に見た産業構造の変化によって、遊牧民1家族が担当する家畜頭数は次第に増大し、放牧地の牧養力は極端に衰えて、放牧地の荒廃が進行していった。
また、先にも見たように、中央集権的経済体制のもとでの国家調達による遊牧民からの畜産原料の吸い上げ、ソ連製の安価で軽便な日用雑貨の流入、伝統的なホタ・アイル共同体の崩壊という三重の要因が重なり、1960年からの集団化の30年間は、遊牧地域から伝統的な手工業・手工芸を根絶させていく歴史でもあった。つまり、都市のみならず遊牧地域の隅々に至るまで、外国のできあいの製品をそっくりそのまま受容して、自らの力でつくり出すことのない「援助の経済」の社会体質に染めあげられていったのである。
1990年代に入ると、ソ連との経済交流が激減し、コメコン(経済相互援助会議)体制が崩れた結果、この「援助」の肩代わりを西側先進諸国に期待し、その方向に急速に転回していった。
1921年のモンゴル人民革命以降70年間、特に最後の30年間に作り上げられた「援助の経済」の社会体質そのものにメスを入れずに、東側の「援助」を西側の「援助」に置き換えさえすれば済むという安易な傾向が顕著になっていった。「自立の精神」、「自立の経済」の体質を社会の底辺からどう作り、築きあげていくかという根源的な洞察を抜きにしては、本当の解決にならないことは明らかであった。
◆コラム「菜園家族 折々の語らい」(10)の引用・参考文献◆
西嶋定生「総説」および「皇帝支配の成立」『岩波講座・世界歴史』第4巻、岩波書店、1970年
江口朴郎『帝国主義と民族』東京大学出版会、1971年
遠山茂樹「東アジア歴史像の検討」『歴史像再構成の課題』御茶の水書房、1969年
小貫雅男「モンゴル革命把握の前提 ―モンゴル近代史の位置づけと東アジア―」『歴史学研究』410号、(特集「ロシア周辺の革命(Ⅱ)」)、青木書店、1974年
小貫雅男『遊牧社会の現代 ―モンゴル・ブルドの四季から―』青木書店、1985年
小貫雅男『モンゴル現代史』山川出版社、1993年
小貫雅男・伊藤恵子『新生「菜園家族」日本 ―東アジア民衆連帯の要―』本の泉社、2019年
――― ◇ ◇ ―――
★このコラム「菜園家族 折々の語らい」は、これからも随時、掲載していく予定です。
読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2026年1月16日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/