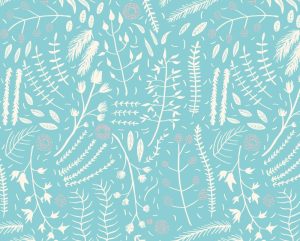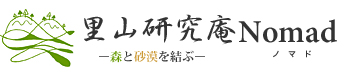
“シリーズ21世紀の未来社会(全13章)”の要諦再読―その21―
“シリーズ21世紀の未来社会(全13章)”の
◆要諦再読◆ ―その21
―
生命系の未来社会論具現化の道 <5>
―自然界の生命進化の奥深い秩序に連動し、展開―
世界的複合危機の時代を生きる ①
―避けては通れない社会システムの根源的大転換―
――CO2排出量削減の営為が即、
古い社会(資本主義)自体の胎内で
次代の新しい芽(「菜園家族」)の創出・育成へと
自動的に連動する
CSSK社会メカニズムの提起――
◆ こちらからダウンロードできます。
要諦再読 ―その21―
“世界的複合危機の時代を生きる ①”
(PDF:668KB、A4用紙14枚分)
環境活動家17歳の少女
グレタ・トゥーンベリさんの
涙ながらの訴え。
あの清新の気は
私たち大人からは
もうとうに消え失せてしまったのであろうか。
1 気候変動とパンデミック、そしてウクライナ戦争は、果たして人間社会の進化にとってまことの試練となり得るのか
今、世界の人々は、新型コロナウイルス・パンデミックの脅威と地球温暖化による気候変動、さらにはウクライナ戦争がもたらす人類破局の事態に直面し、この複合危機回避の重い課題を背負わされている。
大量生産・大量浪費・大量廃棄に基づく市場原理至上主義「拡大経済」は、今や行き着くところまで行き着いた。消費拡大による「景気の好循環」の創出は、結局、資源の有限性・地球環境保全とのジレンマに陥らざるをえない矛盾を孕んでいる。今こそ、大地に根ざした素朴で精神性豊かな自然循環型共生社会(じねん社会としてのFP複合社会)への転換が切実に求められる所以である。
そうはいっても、そのような社会は、結局、縮小再生産へと向かい、じり貧の状態へと陥っていくのではないかといった不安。あるいは、それは理想であり願望であって、実現など到底不可能であるといった諦念にも似た漠然とした思い。あるいはまた、先のない僅かばかりの温もりに訣別できず、ただただその日その日の歓楽を追い求める根深い意識などなどが、人々の心のどこかに根強くあるようだ。
続きを読む