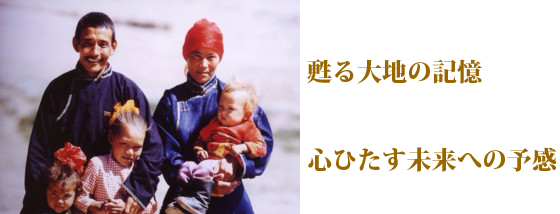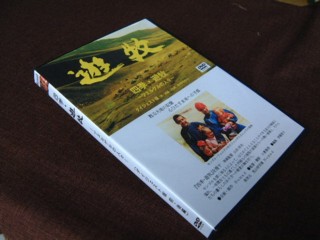『グローバル市場原理に抗する 静かなるレボリューション』への書評
評者:澤 佳成(さわ・よしなり=東京農工大学講師、環境哲学)
生命本位史観を基軸にした菜園家族
東日本大震災の発生した2011年3月11日。この日は、福島第一原発事故の要因である、地方を疲弊させてきた中央集権化政策、海外の貧困層の生存にまで影響する資源浪費型の経済、それに追従する科学技術のあり方といった、この国の矛盾を再考するための、転換点となるはずだった。しかし、3年後の今、この社会では、まるで何もなかったかのように、市場至上主義的経済体制下での、マンモニズムにもとづく政策が跋扈している。本書は、こうした現実に警鐘を鳴らしつつ、オルタナティブな社会を構想する労作である。
筆者の新しい社会構想は、人間を大地と生産手段から切り離す資本主義によって出来した、環境、人間、家族の危機という現代社会の矛盾の克服が前提となる。それゆえ、資本主義の現実的矛盾が深まり、それを克服する実践や研究が進んだ19世紀の理論、とりわけマルクスの理論が、意義と限界の両側面から、序編において吟味される。
本編では、序編における考察を踏まえつつ、筆者の提唱する「生命本位史観」のもとでの未来社会論が、展開されてゆく。人類は、有史以来、剰余生産物を巡る階級闘争において「指揮・統制・支配」を基本原理とする社会のあり方によって、本来なら人間もその一部分であるはずの自然を脅かしてきた。人間を大地から引き離した市場の原理は、その決定打となった。しかし、そもそも生命体は、37億年にわたり、「外的環境の変化に対して、自己を適応させようとして自己を調整し、自己をも変革しようとする」「適応・調整」(322頁)という普遍的原理のもと進化してきたはずである。そうであるなら、人間の社会もまた、この原理に照応する形で編み直さなければならない。その基本単位が、筆者の十数年にわたる実践に裏打ちされた、生きる糧を生産する自律的「菜園家族」となる。
以下、筆者の現代的問題の把握と、菜園家族を基盤とした未来社会の構想をみていこう。
人間の危機と環境の危機の相即性
資本主義は、産業革命後、大量生産が可能な生産手段を、剰余生産物の主たる持主である資本家が独占することで成立する。競争に敗れ、あるいは土地を追われる形で生産手段を奪われ、賃金労働者となった人びとは、自ら生産した物がすべて資本家のものとなるために、本来労働を通じて得られる自己確証、生きる喜びや豊かさといったものを享受できない。それだけではない。賃金労働者は、失業や、生産物があり余っているからこそ生じる恐慌という人災(93頁)によって生死の境を彷徨いかねない境遇に、常に晒されている。それでも、生産手段を失った賃金労働者は、賃労働による生存の維持を余儀なくされる。
こうした形での人間の危機の昂進は、地球環境危機をも深めていく。持たざる者が、自立のための生産手段を含めてわずかな富まで収奪され、根なし草同然になる一方で、富める者がますます富んでゆく市場原理のグローバル化プロセスは、持たざる者の土地・文化・社会を収奪する仕方での環境破壊の拡大と、表裏一体の関係にあるからである。 大地と切り離された人間が増えてゆくほど、自然環境の破壊は昂進する。筆者は、資本主義経済体制下での人間の危機と環境の危機との相即性を、このように鋭く告発する。
家族の変質と子どもの成長の危機
時を経るとともに、空間を超えて拡大するグローバル市場原理体制のもと、「現代賃金労働者(サラリーマン)」として、賃金を得なければ生存を維持できない私たちの多くもまた、帰る故郷をもたない根なし草となっている。この状況が、家族の危機をも招来していると筆者はいう。
かつて、自然との循環のなかで生活を営む家族は、「いのちの再生産の輪」と「ものの再生産の輪」(138頁)が重なる“場”であった。だが、市場原理の貫徹によって、まずは工業生産が、次いで農業生産が、家族の外へと追いやられ、それらの生産物が、自分たちで文化を伝承しつつ生産すべき対象から、賃金を得なければ手に入らないものとなった。
こうして大地から引離され、世代間の継承を通して行われる労働(生産活動)での喜びや自己形成の機会、人間的交流が失われた家族からは、子どもを育む力が失われてゆく。それだけではない。子どもの成長を育む営み事態が、幼児保育、学校や塾といった形で家族の外部に追いやられてゆく。生産物の獲得から教育にわたり、家族の維持には賃金が必須となるため、「家族がまるごと市場に組み込まれ、熾烈な競争にもろに晒される」(138頁)。結果、現経済体制下でいかに生き残るかに賭ける、教育家族が出来する。
こうして、市場原理の支配する経済体制への適応志向が家族を席捲し、マンモニズムが跋扈することで、社会における倫理の頽廃も深まってゆくと筆者は警鐘を鳴らす。
市場原理の昂進により、人間が、家族が、大地から切り離され、環境の破壊も深まってゆけばゆくほど、人類は、自らの破滅に、一歩、また一歩と近づいてゆくのだ。
人類史の新たな段階:菜園家族
では、どうすればよいのか。二百年程度の歴史しかない資本主義体制は、数百万年続いてきた人類の歴史からみれば微々たるものだが、結果として大地から切り離され、賃労働に縛り付けられ生きている私たちの手許には、もはや、自然循環型の生活を営むための土地や生産手段が残されていない。だからこそ、現代賃金労働者と「自立の基盤としての「菜園」との再結合を果たすことによって創出される新たな家族形態」である「菜園家族」(311頁)を、未来社会の根本的な担い手としなければならないと筆者は強調する。
三世代を基礎とする菜園家族は、賃労働を週二日に減らし、週休五日のなかで、生きるために必要な物の栽培、手作りによる加工品の制作、自営業(匠商家族)を営む。その共同作業のなかで、農地や里山などの美しい景観を育み、技を伝承してゆく家族は、他の生命種にはみられぬほどの未熟さをもって誕生する人間の子どもの感性を育み、自己を形成する場として機能する。
こうしたあり方の菜園家族は、資本主義の席捲によって失われていた人間の生き方、つまり、数百万年継続してきた、家族を基礎とする人間の生存のための営みを、現代の社会様式のよき部分も組み込みつつ継承することで、人間疎外、環境破壊をもたらす社会の仕組みをかえる担い手となる。
それは、「大地から遊離し根なし草同然となった不安定な現代賃金労働者(サラリーマン)が、大地に根ざして生きる自給自足度の高い前近代における「農民的性格」との融合を果たすことによって、21世紀の新たな客観的条件のもとで「賃金労働者」としての自己を止揚し、より高次の人間の社会的生存形態に到達することを意味している」(311頁)のだ。
抗市場免疫の自律世界の構築へ
こうした筆者の提言は、けっして前近代への回帰の称揚ではない。資本主義セクターC(Capitalism)、家族小経営セクターF(Family)、公共的セクターP(Public)の相互連関により形成される「CFP複合社会」で、セクターPによる規制によってセクターFを主役に据え、セクターCの積極面を受容しつつ賃金労働者と菜園(大地)との再結合を図り、歴史の進展とともに、昨今の矛盾を招いたセクターCの範囲を徐々に狭めてゆくという構想である。
だからといって、この社会は、中央集権的共同所有によって資本主義に対抗しようとした旧ソ連型の発展形態(A型発展)を目指すものでもない。そうではなくて、「大地に根ざした個性的で創造的な人間一人ひとりの活動と人間的鍛錬を通じて、非民主的で中央集権的な独裁体制の生成と増幅を抑制する豊かな土壌と力量を社会の内部に涵養していく」(168頁)発展(B型発展)を重視する。それゆえ菜園家族は、むしろ、中央集権化、非民主化という市場原理のもたらす問題への、抵抗の拠点となる。
市場原理の貫徹する現代社会は、家族、地域、国、グローバルな世界といった階層構造をなす社会の「最上位の階層に位置する巨大資本が、あらゆるモノやカネや情報の流れを統御支配」している(132頁)。この上からの支配が、人間や家族を危機に陥れ、地域の衰退を招いているのなら、自律した菜園家族を基盤として地域や同業の協同組合(なりわいとも)を結成し、村、郡、県レベルへと繋がりを広げてゆく「ローカルからグローバルへ」という形での、下からの民主主義を徹底すればよいと筆者は提起するのである。「経済の源泉は、まぎれもなく草の根の「人間」であり、「家族」であり、「地域」である。そして民主主義の問題は、究極において人格の変革の問題であり、人格を育むものは、人間の生産と暮らしの場である「家族」と「地域」である。したがって、この「家族」と「地域」を時間がかかってもどう立て直し、どう熟成させていくかにすべてがかかっている」(240頁)。
混迷するグローバル社会の海図
3・11福島原発事故は、原子力ムラに代表される中央集権的かつ非民主的な政治・経済体制を見直すための、エネルギー自治、生産活動の民主化といった構想の必要性を浮き彫りにした。しかし、現実には、新規の<放射性物質安全神話>によって市民が分断され、経済成長神話に依拠した従来型の路線が、資本を崇拝する者達によって維持継承されている。また、グローバルな経済体制を保安するための軍備増強がはかられ、同時に、行政権力にとって都合の悪い情報を隠すための秘密保護法制が議論されてもいる。人間の「いのち」の視点を重視した文明への転換が強く求められている今、本書は、これらの課題に、理論的かつ具体的な形で有益な視座を与えてくれる好著であり、一読をお勧めしたい。
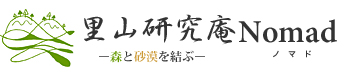
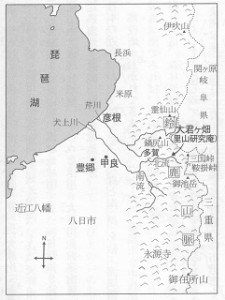
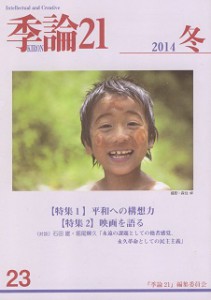
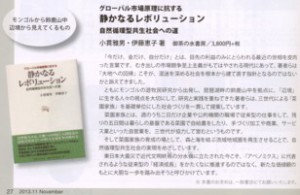
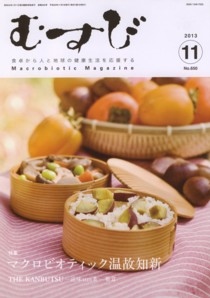
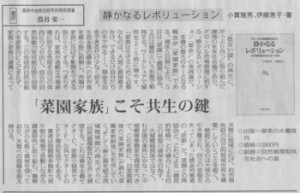
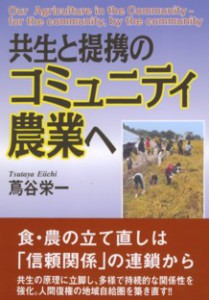
-300x201.jpg)