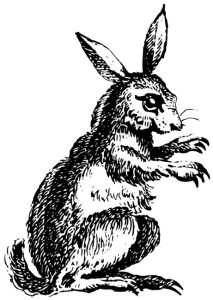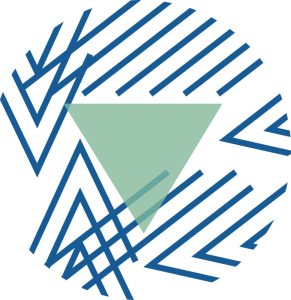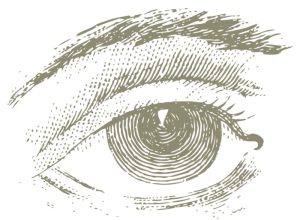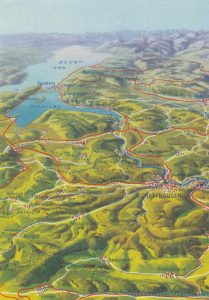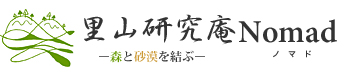
長編連載「いのち輝く共生の大地―私たちがめざす未来社会―」第13章(その1)
長編連載
いのち輝く共生の大地
―私たちがめざす未来社会―
第四部 民衆主体の具体的政策
―「いのち輝く共生の大地」をめざして―
第13章
「菜園家族的平和主義」の構築(その1)
―いのちの思想を現実の世界へ―
◆ こちらからダウンロードできます。
長編連載「いのち輝く共生の大地」
第13章(その1)
(PDF:734KB、A4用紙12枚分)
”原爆を許すまじ”
― 孤立や差別に苦しむ被害者に、そして
日本と世界のひしがれしすべての人々に
考え、行動する勇気を与えつづけた歌 ―
核兵器の非人道性を語り継ぎ、核廃絶の必要性を唱えてきた原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が、昨年12月10日、ノーベル平和賞を受賞した。
ノルウェーのオスロ市庁舎での授賞式で代表委員の田中煕巳(てるみ)さん(92歳)は、講演に立った。渡航の2週間ほど前から体調を崩し、強い圧迫感を感じながら原稿を書き上げた。
「核兵器の保有で戦争を抑止できると信じる人々がいる今の世界に、限りないくやしさと憤りを覚えます」と投げかけた。
そして、ご自身の人生について語りはじめた。
「私は長崎原爆の被害者の一人です」
中学一年生だった1945年8月9日、長崎の自宅で原爆に遭った。母と兄、妹の4人と暮らしていた。
みな無事だった一方、爆心近くに住む親族は違った。
「一発の原子爆弾は、私の身内5人を無残な姿に変え、一挙に命を奪った」
祖父は骨が見えるほど全身に大やけどを負い、伯母やいとこは炭のように真っ黒になって転がっていた。
「たとえ戦争といえどもこんな殺し方、傷つけ方をしてはいけない」
生き残った被害者たちの苦悩は続いた。身体に残る大やけどの痕、放射線の影響による健康不良、愛する人を失った悲しみ・・・。田中さんの通う学校には、髪の抜けた頭を布で隠して通学する女子学生や、突然亡くなる同級生がいた。
「占領軍に沈黙を強いられ、さらに日本政府からも見放され、被爆後の十年余を孤独と病苦と生活苦、偏見と差別に耐え続けました」
ビキニ環礁での米国の水爆実験に日本のマグロ漁船「第五福竜丸」の船員が被曝し、揺れ動いた70年前、浅田石二作詞“原爆を許すまじ”が反核運動を奮い立たせる。広島・長崎の被爆者は悲しみと怒りを胸に歌い、人々も口ずさんで全国へ広がっていった。
ふるさとの街やかれ
身よりの骨うめし焼土(やけつち)に
今は白い花咲く
ああ許すまじ原爆を
三度(みたび)許すまじ原爆を
われらの街に――
その2年後、1956年に日本被団協が結成された。
孤立や差別に苦しむ被爆者が団結し、核廃絶を訴える声を一つにするのを支える。ノーベル平和賞の授賞式に臨んだ田中煕巳さんも「団歌といってもいい」と感謝する。
待望の受賞が薄れゆく戦時の記憶を呼び覚まし、日本そして世界中で考え、行動する契機になればと願う。戦後80年へと伝えたい。
「いつの時代も、戦争による死者のことが忘れられた時に新しい戦争が始まる」と。
――― ◇ ◇ ―――
人は誰しも
決して避けることのできない
死という宿命を背負いながらも
懸命に生きている。
そもそも人間とは
不憫としか言いようのない
不確かな存在ではなかったのか。
だからこそなおのこと
人は
同じ悲哀を共有する同胞(きょうだい)として
せめても他者に
とことん寛容でありたいと
願うのである。
今や常態化した
権力者による
「マッチポンプ」式の卑劣な応酬。
だが、これだけは決して忘れてはならない
戦争とは、結局、どんな理由があろうとも
民衆に
民衆同士の殺し合いを強いる
国家権力による
極悪非道の最大の犯罪そのものなのだ。
1.いのち軽視、いのち侮辱の「戦争俗論」の跳梁跋扈を憂える
―卑劣な企み「マッチポンプ」の繰り返し―
憎しみと暴力の坩堝(るつぼ)と化した世界 ―世界の構造的不条理への反旗
今から11年前の2013年1月16日、はるか地の果てアルジェリアのサハラ砂漠の天然ガス施設で突如発生した人質事件は、わずか数日のうちに、先進資本主義大国および現地政府軍の強引な武力制圧によって、凄惨な結末に終わった。
こうした中、同年1月28日、安倍晋三首相(当時)は、衆参両院の本会議で第二次安倍内閣発足後、初めての所信表明演説を行った。
演説の冒頭、アルジェリア人質事件に触れ、「世界の最前線で活躍する、何の罪もない日本人が犠牲となったことは、痛恨の極みだ」と強調。「卑劣なテロ行為は、決して許されるものではなく、断固として非難する」とし、「国際社会と連携し、テロと闘い続ける」と声高に叫び胸を張った。