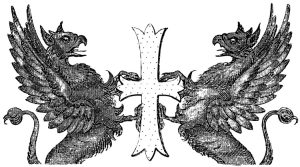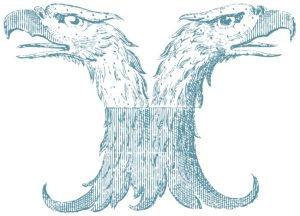連載“高次自然社会への道” 終了にあたって≪5≫
連載“高次自然社会への道” 終了にあたって≪5≫
今や猶予なき喫緊の国民的課題
「菜園家族的平和主義」の構築 ③
―いのちの思想を現実の世界へ―
◆ こちらからダウンロードできます。
連載 “高次自然社会への道” 終了にあたって≪5≫
「菜園家族的平和主義」の構築 ③
(PDF:657KB、A4用紙12枚分)
日米軍事同盟のもと
いつまでもアメリカの権力に追従し
東アジアの民衆に背を向け
この地域世界に
撹乱をもたらしている場合ではないのである。
今こそ
自らの「菜園家族的平和主義」の理念を高く掲げ
この道の選択を
いよいよ決断する時に来ているのではないか。
4 東アジア地域世界に宿命的に集中胚胎するグローバル危機の震源
あまりにも片寄った情報の氾濫の中で考える ―朝鮮半島情勢をめぐって
これまで超大国アメリカをはじめ、日本など先進資本主義諸国は、きまって仲間同士徒党を組み、「テロとの戦い」とか「核不拡散」とかを口実に、特定の国を仮想敵国に仕立て、対立と敵愾心を煽ってきた。
なかんずく極東においては、長きにわたって、米韓合同軍事演習が大々的に展開されてきた。と同時に、アメリカとそれに追従する日本の権力的為政者は、口を揃えて武力威嚇の本音とその本質を眩(くら)ます欺瞞の常套句「抑止力」とか「対話と圧力」などと呪文のように繰り返し、自らは日米軍事同盟のもと、日本国憲法第九条をかなぐり捨て、軍事力を際限なく強化していく。日米合同軍事訓練を強行し、果てには「自衛のため」だと、敵基地先制攻撃をも辞さないと威嚇する。
緊張を高めてきたのは、果たして北朝鮮の側だけなのか。あるいは、中国側だけなのか。
わが国における情報は、あまりにも一方的で、片寄りすぎているのではないか。
軍部主導の大本営発表を鵜呑みに、国民こぞって大戦へとのめり込んでいったかつての記憶が、今鮮やかに甦ってくる。
超大国とその追従者は、「抑止力」とか「対話と圧力」などと言いつつ、自らは国連の舞台で、公然とヒバクシャと世界諸国民の宿願でもある核兵器禁止条約を拒絶し、あくまで核に固執する。そして、日米軍事同盟のもと、巨大な軍事力を背景に相手を威嚇し、圧倒する。さらには、弱小国に対する経済制裁包囲網を強め、孤立化、疲弊化をはかるという。
何と身勝手なことか。
その結末は、民衆に壊滅的犠牲を強いる、勝者も敗者もない一触即発の核戦争なのだ。今や日米軍事同盟は、国民の暮らしと生命を守るどころか、むしろそれを根底から冒涜する、究極の脅威の根源になっていることに気づかなければならない。
今ここで第二次世界大戦後79年間の歴史を紐解くだけでも、ことの本質はすぐに分かるはずだ。
戦後一貫して日米軍事同盟のもと、自らの価値とは異質の分子、異質の体制を敵視し、何かと屁理屈を捏(こ)ねては孤立させ、排除しようと武力を行使し、世界各地で血みどろの戦争を仕掛けてきたのは、果たして誰だったのか。
当事者は、戦後の歴史をあらためて振り返り、謙虚に反省しなければならない時に来ている。相手の立場に立って、相手の存立そのものを認める寛容の精神、つまり体制の違いを超えて平和に共存する精神が、今こそ求められているのである。
朝鮮半島で偶発的にせよ、一旦、戦闘の口火が切られたらどうなるのか。
軍事基地双方入り乱れての、核ミサイル発射の狂気の応酬になる。南・北隔てなく朝鮮半島の全域はおろか、米軍基地と化した沖縄、日本本土の住民は壊滅的な打撃を被ることになる。生き残るのは、太平洋のはるか彼方のアメリカの権力者だけではないか。
圧倒的に強大な軍事力を背景に、「対話と圧力」、「外交」などと欺瞞の手練手管を弄(もてあそ)ぶことが、如何に愚かで恥ずべきことかを、超大国アメリカをはじめ、それに追従する日本の権力的為政者は、しかと知るべきである。
今から6年前の2018年6月12日、懐疑と期待の念をない交ぜながらシンガポールで開催された急ごしらえの米朝首脳初会談に、世界の人々の耳目は釘付けにされた。
一気に融和ムードが醸し出されたのも束の間、翌2019年2月27、28日にベトナムの首都ハノイで行われた第2回米朝首脳会談は、事前の楽観的期待をよそに、交渉は合意に達しないまま、突如、物別れに終わった。
途端に日米両国の強硬派が再び勢いづき、初会談前の状況に戻ったかのように、「国際社会一致して、徹底した経済制裁を」と、いよいよその本性をさらけ出す。威嚇すればするほど、相手はさいごの生き残りをかけて、ますます対抗措置を強化し、身構える。際限のない軍拡競争の悪循環に陥り、双方もろとも破滅の坂道を転がり落ちていく。
こうした中、トランプ米大統領(当時)は、またもやサプライズを演出するかのように、2019年6月30日、突如、韓国と北朝鮮を隔てる軍事境界線上の板門店に現れ、金正恩朝鮮労働党委員長と対面、現職のアメリカ大統領として初めて、北朝鮮側に足を踏み入れた。そして、韓国側の「自由の家」において、第3回米朝首脳会談なるものをそそくさとおこなった。
2020年秋の大統領選への思惑も絡んだ権力者同士の駆け引き(ディール)に、もとより手放しに過度の期待を寄せるべきものではなかったのである。
安倍政権は、一連の北朝鮮情勢の緊迫化をいいことに、これ見よがしに、F35戦闘機や陸上配備型の新たな迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」導入のための巨額の予算を計上してきた。自衛隊と米軍の一体化のもと、軍事力強化をさらに進める際限のない軍拡競争は、もう既にはじまっているのである。
「自衛戦」という美名のもとに、日中戦争、太平洋戦争へと突入していったかつてのあの手法と、本質的にはどこも変わっていないではないか。
「武力による威嚇又は武力の行使」によって、国際紛争を解決するという手段。
人類史上長きにわたって為政者に染みついて離れない、この悪習とも言うべき手段は、今や完全に破綻したのである。朝鮮半島をめぐって取り返しのつかなくなった今日の事態が、そのことを雄弁に物語っている。
戦後一貫して北朝鮮を孤立させ、威嚇し、追い詰め、徹底して「いじめ」続け、ついにはあのような奇妙な専制的軍事国家体制をつくり出してしまったのその大本(おおもと)は、一体誰だったのか。むしろ、その重大な歴史的責任こそ、今、問われるべきである。
核兵器禁止条約発効と世界各国民衆の連帯
北朝鮮をめぐる今日の深刻な事態を解決する唯一残された道は、圧倒的に強大な軍事力を誇るアメリカの首脳が、何よりもまず、1953年以来休戦状態が続く朝鮮戦争を終結させ、相手国北朝鮮が自国の存亡をかけて、かねてより切望している米朝平和条約の締結を即刻、決断することではないのか。
この米朝平和条約締結の実現に向けて、世界の世論を喚起し、国境を越えた民衆の広汎な運動を広げていくことが今、何よりも切実に求められている。
そのためにはどうするのか。
2017年7月7日、ニューヨークの国連本部での条約交渉会議で、国連加盟193ヵ国中3分の2近くに及ぶ122ヵ国の賛成で、核兵器禁止条約 ――核兵器の使用、開発、実験、製造、取得、保有、貯蔵、移転などの禁止に加え、核使用をちらつかせる「脅し」の禁止も盛り込まれた―― が採択された。
署名式典が開かれた同年9月20日のうちに、署名が50ヵ国にものぼった。一方、核保有国とアメリカの核の傘の下にある日本政府は、条約に背を向けた。
こうした中、同年のノーベル平和賞は、この画期的な核兵器禁止条約を実現するために活動してきた国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)に授与されることが決まった。
わが国は唯一の戦争被爆国であると同時に、米朝関係の緊張による核戦争の脅威に晒されており、私たち国民にとって重要な意味を持つ受賞であるにもかかわらず、日本政府は、受賞決定の直後は公式の声明すら出さず、沈黙を守った。
こうした経過は、何を意味しているのであろうか。
それは、諸大国政府に任せておくだけではなかなか解決しない世界共通の重要な課題に対して、市民社会に根付いたNGOが、そして何よりも民衆こそが、国境を越えて連帯し、積極的な役割を果たすことで現実を動かし、実際に未来を変えていくことが可能だということを示しているのである。
そして、2020年10月24日、ついに核兵器禁止条約批准国・地域が、条約の発効に必要な50に達した。これにより、この条約は、いよいよ2021年1月22日に発効することになった。「核なき世界」を求める国際的な声に後押しされ、核兵器を非人道的で違法だとする、初めての国際条約が動き出すことになったのである。
問題なのは、ここに至ってもなお、アメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中国の核保有五大国をはじめとする先進諸国、そして何よりも被爆国日本自身の政府が、核兵器廃絶を願う世界の圧倒的多数の民衆の願いが込められたこの条約に、誠実に向き合おうとしないことである。
このような中で、今日の北朝鮮問題をどう解決していくのか。結局それは、権力者にお任せするのではなく、世界の世論と知恵を結集したこの核兵器禁止条約に沿って、私たち自身が、そして世界各国の人々が、ともに核兵器廃絶に向け、さらに気運を高めていく以外に道はないということなのである。
こうした世界の人々の広汎で力強い世論を背景に、2023年1月時点でなお世界の核兵器全体の9割を占める、圧倒的に莫大な数の核弾頭を保有するアメリカ(5244発)、ロシア(5889発)両国をはじめ、すべての核保有国に核廃絶を迫っていく。
こうした中で同時に、北朝鮮に対しても、核廃絶を強く要求していくのである。
世界の広汎な民衆の運動に支えられ、各国政府にも大きく扉が開かれた、この筋の通った世界規模での核兵器廃絶運動は、世界各地から寄せられる素晴らしい英知を吸収しつつ、やがてきっと、高次のステージへと着実に展開していくであろう。
とりわけ東アジア地域世界に目を向ければ、アメリカとの軍事同盟によって従属を強いられている韓国と日本に共通する、自主独立および社会の変革を求めて止まない民衆の動き。
北朝鮮、中国に深く潜在する民主化への願い。
大国のはざまで、遊牧の大地に根ざす本来の生き方を求めてもがくモンゴルの民衆。
なかんずく、米ソ両大国によって分断を強いられてきた韓国と北朝鮮の民衆にとって、民族の統一は歴史的宿願となっている。
近年、中国において、南宋の芸術に深い影響を受け、20世紀中国水墨画の巨星と言われた傅抱石(ふ ほうせき)の文化・芸術運動の流れを汲み、飽くまでも内面への沈潜を重視する「内斂(ないれん)」の哲学思想が注目されている。
巨大経済圏構想「一帯一路」の根底にある外へ外へと向かう拡張・拡大の思想を克服し、悠久の歴史の中で培われてきた中国民衆の英知が、やがて発揮される時代がやって来るにちがいない。
シリーズ“21世紀の未来社会”(2022年9月~12月、本ホームページに連載)の第十三章で触れたノンフィクション『中国はここにある ―貧しき人々のむれ―』。
中国農村の暗澹たる現実と、未来への民衆のほのかな可能性を描き出した作家 梁鴻(リアン・ホン)の出現は、そのことを予感させるに足る兆候に思えてならない。
中国がこのままであるはずがない。何よりも中国の民衆自身が自覚し、この東アジア地域世界は変わっていくにちがいない。
これら各国各地それぞれに、さまざまな様相を呈しながらも、過去から蓄積されてきた苦難を克服し、東アジア地域世界全域に民衆レベルの真の運動が着実に広がっていくことであろう※ 。
一方、アメリカでは、トランプ前政権のみならず、バイデン現政権下においても、社会の矛盾が噴出している。奴隷解放運動、公民権運動、ベトナム反戦運動の歴史的伝統を脈々と引き継ぎ、社会の不条理に異議申し立てを唱えて止まない賢明なるアメリカ市民と若者たち。このアメリカの民衆の動きは、東アジア地域世界との関連でも格別に注目しなければならない。
朝鮮戦争休戦以来、大国のエゴによって長きにわたって放置されてきた米朝平和条約締結の気運も、紆余曲折や困難があっても、東アジア地域とアメリカ、そして、世界各地における民衆運動の高揚と相互理解の深まりを背景に、次第に高まっていくであろう。
世界の民衆の平和への思いは、やがて北朝鮮の民衆にも届き、不信と恐怖、狂気と傲慢に陥っていく北朝鮮の権力者も、こうした自国民の切なる声と国際環境、なかんずく世界各地の民衆の大きな変化の中で、さすがに国際社会での自己の存立のリスクが、もはや過去のものとなったことに気づき、国民生活と国内経済を圧迫する核兵器の開発・製造・保有が、まったく無意味であることを自ずから悟るにちがいない。
こうした世界の民衆による前向きの明るい動きの兆しを受け、東アジア地域世界(モンゴル、北朝鮮、韓国、中国、ロシア極東、日本)に相互不可侵、内政不干渉、平等互恵の精神が芽生え、非戦・平和と友好の国際環境がゆっくりと醸成されていくであろう。
相互尊重と共生の原則に基づくこの新たな国際環境のもとではじめて、各国民衆の自由な往来、独自の特色ある発展と繁栄、そして真の民衆の交流が約束されるのではないか。
※ シリーズ“21世紀の未来社会(全13章)”の第十三章「夜明けを告げる伝統と革新の『東アジア世界』」https://www.satoken-nomad.com/archives/1993を参照のこと。
権力的為政者同士の「外交」への幻想を捨て、逆流に抗し、民衆自身の主体性の確立を
しかし、現実は厳しい。今日の逆流の由々しき事態を直視することを、つゆほども忘れてはならない。
2017年11月上旬、トランプ米大統領(当時)は就任後初のアジア歴訪で、「我々は世界最高の兵器をつくっている」と自国製武器を売り込み、購入が「アメリカに雇用をもたらす」と公然と言い放った。
安倍首相(当時)も、「日本の防衛力を質的、量的に拡充していかなければならない。アメリカからさらに購入していく」と応じた。安倍首相(当時)はまた、「日米が主導し、北朝鮮に対する圧力を最大限まで高めていくことで完全に一致した」と述べ、米国の軍事行動を含む「全ての選択肢がテーブルの上にあるとのトランプ大統領の立場を一貫して支持している」と表明した。
お互い相手の非を責め、敵愾心を煽り、武力威嚇の応酬を繰り返す愚行からは、何ものも生まれなかったどころか、ますます事態を極度に悪化させ、各国国民に壊滅的犠牲を強いる全面戦争の瀬戸際に追い遣る。
権力支配層による「外交」という名の、実に狡猾な自己本位の損得勘定の醜い取引ゲーム。欲深い権力者たちがどんな言い訳を弄しようとも、彼らは、朝鮮半島におけるこの重大事態を引き起こしてきた歴史の責任から免れることはできない。
「外交」とは所詮、民衆からは隔絶した世界で行われる、「国民」の名を借りた権力者の極めて利己的な利益追求そのものの手段なのである。私たちは、それに惑わされることなく、国境を越えた民衆同士の交流と連帯という草の根の精神を片時も忘れてはならない。
2021年1月20日、トランプ政権からの路線転換を打ち出すジョー・バイデン氏がアメリカ新大統領に就任した。当初、メディアでは楽観的ムードが醸し出されたが、アメリカの社会経済の深刻な構造的矛盾が根っこから解決されない限り、本質的には歴代大統領と同じことの繰り返しになるのは目に見えていた。
就任早々、次々とその本質を露呈。2022年2月、ウクライナ戦争がはじまると、アメリカ国内での反戦運動の高まりを嫌い、直接の米軍派兵は避けつつ、もっぱらウクライナへの武器供与を重ね、戦争の泥沼化の道へと嵌まり込んでいく。
G7首脳とウクライナのゼレンスキー大統領が被爆地広島に集結した、あの悪夢のようなサミットは、2023年5月21日に終わった。
翌5月22日付朝日新聞の報道によれば、核廃絶を望む被爆者からは、岸田文雄首相やG7首脳に対する失望や怒りの声が上がったという。
元広島市長平岡敬さん(95歳)は、憤りを隠せない。「広島に集まるならば、核を全面否定し、平和構築に向けた議論をすべきだった」。
しかし、G7首脳が5月19日に出した「核軍縮・不拡散に関する広島ビジョン」では、ロシア、中国、北朝鮮、イランといった対立する国々の核兵器を非難するばかりで、自らの側については、例の如く核抑止力維持の重要性が強調された。
平岡さんは、「一貫して核と戦争を否定してきた広島が、その舞台として利用された。議長国・日本の岸田首相は罪深い」と指摘する。
さらに、ゼレンスキー氏が招かれ、G7首脳との間で軍事支援の強化が約束されたことについては、「中国とロシアに対して、西側諸国の結束をアピールしたいだけだ。1日も早く停戦と戦後復興について話し合ってほしかった」。こう受け止め、怒りが込み上げてきたという。
被爆者だけでなく、おそらく多くの人々が、このサミットをそう受け止めたのではないか。日本国憲法を尊重し擁護する義務を負う(日本国憲法第九十九条)べきその立場にあるはずの岸田首相は、一体どこの国の首相なのであろうか。
正真正銘の「核なき世界」の実現は、2021年1月22日核兵器禁止条約の発効を機に、私たち主権者民衆自身が、思いを新たに、平和のために自らの社会のあり方そのものを如何に変えていくかという、根源的で包括的な未来志向のたゆまぬ地道な努力をすることができるかどうかにかかっている。
今や欲深い権力者同士の駆け引き、「外交」なるものに、如何なる幻想も抱くことはできない。
結局は、莫大な核を保有する超大国アメリカとロシア、および中国、西欧の核保有諸国における、そして、核を保有していない圧倒的多数の小さな国々における、民衆の社会運動そのものの力量とその高まり如何にかかっている。
迂遠に思われるかもしれないが、とどの詰まり、民衆自身の主体性のまことの確立、これ以外に解決の道はないのである。
戦後79年、もう一度初心にかえり世界の人々に呼びかけよう
私たちは戦後79年を迎える今、もう一度初心にかえり、世界に誇る日本国憲法前文および第九条をそれこそ丹念に、しかも愚直なまでに誠実に読み返そうではないか。そして、その精神を敢然と甦らせるのである。
戦後歴代政権の中でも、こざかしさが際立っていた安倍政権。欺瞞に充ち満ちた「積極的平和主義」なるものを錦の御旗に掲げ、屁理屈を捏ね、国民の目を欺き、それこそ勝手気ままに拡大解釈し、既成事実を積み重ね、憲法の精神を骨抜きにした。
こうした政権を国民不在のまま、身内でたらい回しにして継承した菅義偉政権。
そして、被爆地広島選出と言いながら、見え透いた言い訳を弄して核兵器の廃絶に背を向け、日米軍事同盟のさらなる強化と、NATO(北大西洋条約機構)との連携に奔走する欺瞞の岸田政権。
このような振る舞いほど、国民を愚弄した卑劣で危険きわまりない行為もない。世界に誇る日本国憲法は、決してこうした一握りの権力者によって弄ばれてよいものではない。私たち自身の、そして世界のすべての人々の生きる指針であり、思想そのものなのである。
ウクライナ戦争の渦中にある今こそ、未来を担う小学生の子供たちや若者たちから、高齢者に至るまで、世代を越えてお互いに、日本国憲法前文および第九条を愚直なまでに何度も読み返し、今日の日本と世界の現実から目を反らすことなく、世界の人々とともに戦争と平和の問題を根源的に考え、語り合い、明日への希望へとつなげていくことが切に求められている。
一方に加担して世界の人々を分断するのではなく、今こそ日本国憲法前文および第九条を民衆の名において、北朝鮮や韓国、中国、ロシア、ウクライナ、ヨーロッパ、アメリカの人々をはじめ、世界のすべての人々に向かって正々堂々と再び宣言しよう。そして、それを誠実に自ら身をもって実行する。
その上で、北朝鮮の為政者に対しても、「残虐非道の過激派」と呼ばれている人々に対しても、ロシアとウクライナ、アジア・中東・アフリカ・ラテンアメリカの人々に対しても、そして世界のすべての人々に対しても、民衆の名において誠意を尽くして呼びかけ、とことん話し合おう。これができるのは、日本国憲法を持っている日本の国民をおいてほかにない。
これこそが、今日の世界の人々が心底もとめている、正真正銘の積極的平和主義なのではないか。世界の人々が日本の国民に本当に期待するものは、欺瞞に充ち満ちたアベノミクスとその後継政権の「積極的平和主義」などでは決してない。まさに日本国憲法前文および第九条が高らかに謳ったこの崇高な平和主義であり、それをそれこそ正直に実行することなのである。
覇権主義を排し、日本国憲法の理念に根ざす小国主義の道を
明治維新政治史、日本近代史の研究者である田中彰氏は、小国論の視座から『特命全権大使米欧回覧実記』を検討し、その後に現れた小国主義の代表的な主張、議論を辿りながら日本近代史を描きなおした名著『小国主義 ―日本の近代を読みなおす―』(岩波新書、1999年)の結論部分で、要約以下のように述べている。
明治初年、米欧12か国を回覧した岩倉使節団は、日本近代国家創出のモデルを求め、日本の進むべき道を模索していた。使節団副使だった木戸孝允および大久保利通が没したあとの「明治14年の政変」は、その後の朝鮮問題とからんで日本の岐路となった。かつての特命全権大使だった岩倉具視と副使伊藤博文らによる明治政府がそこで選んだ道は、アジアにおける小国から大国への道だった。
これに対して、中江兆民は「富国強兵」を目指す明治政府の大国への道を痛烈に批判し、小国主義を対置した。当時、自由民権運動の側から出された私擬憲法、なかでも植木枝盛の草案などは、「自由」と「民権」を基調とする内容をもっていた。明治憲法を大国主義の憲法とすれば、植木らの民権派の憲法案は、まさに小国主義の憲法といってよい。
しかし、自由民権運動への徹底した弾圧によって小国主義はおしつぶされ、日清戦争の勝利によって明治天皇制は、その基盤となる思想的・社会的土壌を急速に広げ、確立していった。そして、軽工業から重工業へと、わが国の産業革命は進展していく。それに続く日露戦争は朝鮮を踏みにじり、中国への軍事侵略の足場をつくった。明治国家の大国主義路線は、これらの戦争を通して小国主義をおさえ込んでいく。
小国主義の路線は深く伏流せざるをえなかった。しかし、小国主義の主張は、社会主義思想や内村鑑三らキリスト教者の非戦・平和主義の論調として、時に表層に滲み出た。やがて、大正デモクラシーの潮流の中から顕在化したのが、石橋湛山らの「小日本主義」である。彼は、植民地放棄の論陣を張った。
だが、大正デモクラシーの潮流のなかでの「小日本主義(小国主義)」も、ふたたび大国主義による軍国主義におしのけられ、アジア太平洋戦争によって再度伏流化した。そしてついに、1945年8月15日、日本は敗戦を迎えたのである。
敗戦と占領という外圧を経ることによって、戦前・戦中、苦闘を強いられ続けてきた「未発の可能性」としての小国主義ははじめて陽の目を見たのである。敗戦によるすべての植民地の放棄によって、小国主義が実現し、民権派憲法草案の流れをくんだ憲法研究会草案がマッカーサー草案を介して日本国憲法に流れこむことによって、小国主義はついに現実のものとなったのである。
明治初年さらに明治十年代から、「未発の可能性」としての小国主義は、大国主義と闘い、伏流、台頭、再伏流という長い苦難の水脈を維持しつつ、敗戦・占領という過程で、この小国主義を内包した日本国憲法として結実したのである。
そして、田中氏はこう結んでいる。
21世紀は、「小国主義か大国主義か」ということになろう。小国主義はアンチ大国主義・覇権主義である。それは小国主義としての主張であり、闘いである。小国主義を選択することは、日本国憲法の理念に根ざす小国主義を国民が主体的に闘いとることである。そして、その小国主義を克ちとり続けることこそが、日本近代史の苦闘の歴史の教訓を生かす道である。
それは明治以降、その理念の実現をめざして闘ってきた多くの先人の努力を受けつぐことにほかならない。日清・日露戦争以後、天皇の名においてくり返されてきた戦争に命を奪われた人びと、そして、アジア太平洋戦争にいたる数千万のアジアないし世界の犠牲者に対する、いまを生きる日本人としての責務がそこにはある。
小国主義は、国民の自主・自立のエネルギーの横溢と国家の禁欲を求め、道義と信頼に基づく国際的な連帯と共生を必要とする。そこには大国主義とのたゆまざる闘いがある。
(田中彰『小国主義 ―日本の近代を読みなおす―』岩波新書、1999年)
「押しつけ」憲法論や「国際情勢の変化」を理由に、日本国憲法の小国主義の理念を否定しようとする企みに対する闘いが、今や急を要する事態に直面しているからこそなおのこと、自身も多感な青年期に軍国主義の時代に翻弄され、陸軍士官学校最後の士官候補生として敗戦の日を迎え、戦後、日本近代史の研究に取り組んできた氏のこの論点を大切に心に留めておきたい。
憎しみと暴力の止めどもない連鎖。世界は今や各地に紛争の火種が拡散され、互いに疑心暗鬼に陥り、世界大戦への一触即発の危機にすら晒されている。
末期重症とも言うべき今日の世界のこの恐るべき事態は、拙著『新生「菜園家族」日本 ―東アジア民衆連帯の要(かなめ)―』(本の泉社、2019年)で明らかにしたように、結局、日本近代史、アジア近代史、そして世界史に則して見るならば、大国主義と小国主義の浮き沈みの思想的葛藤の長い歴史の末に、最終的には大国主義が小国主義を押さえ込み、優勢となって浮上してきた結果もたらされたものなのである。
この歴史を直視すれば、米ソ二大陣営の対立による冷戦構造の崩壊後、新たな装いのもと、地球規模で今なお執拗に繰り返されている「新大国主義」とも言うべき多元的覇権抗争が、いかに愚かで虚しいものであるかに気づくはずだ。
そして、21世紀私たちが進むべき道は結局、小国主義を貫く以外にあり得ないことに思い至るであろう。それには何よりもまず、今日の私たち自身の社会経済のあり方そのものを根源的に変えることによってのみはじめて、小国主義日本の21世紀未来の姿を明確に展望することが可能になってくるのではないか。
それは、明治政府による上からの近代化と覇権主義的大国への道に抗して、軍備廃絶と非戦を訴え、農を基盤に自然と共生し、村々の自治を下から確立してゆく、真に民主的な小国日本の可能性を対置した中江兆民、田中正造、内村鑑三ら、近代と格闘した多くの先人たちの思想的苦闘の歴史的水脈を21世紀の今に甦らせ、その具現化の道を探ることでもある。
気候変動とパンデミックの複合危機に晒され、さらにはウクライナ戦争による混迷の中、再び軍事ブロックに依拠した大国主義的抗争が横行する、弱肉強食の凄まじい今日の現代世界にあって、如何にして小国主義を貫き、「小国」を築くことが可能なのか。そして、その「小国」とは、一体どのような理念と原理に基づく社会経済の仕組みであるのか。
その基本を明らかにすることが、「菜園家族」社会構想の究極の目標である。そして、今日のこの時点に立って、“生命系の未来社会論”という新たな視座、新たな論点から、根源的かつ全一体的(ホリスティック)に21世紀未来社会像を描き、その実現への道筋を具体的に提示してきた。
この課題は結局、19世紀以来、人類が連綿として探究し続けてきた、近代資本主義を超克するかつての未来社会論に対しても同時に、21世紀の今日の現実からあらためて再考を迫るものになるであろう。
まさしくそれは、19世紀マルクス未来社会論のアウフヘーベンの課題なのだ。
私たち自身がこの道を誠実に歩むことによって、日本国憲法の前文および「平和主義」、「基本的人権(生存権を含む)の尊重」、「主権在民」の三原則の精神を具現する、新生「菜園家族」日本の創出へと向かうのである。
それはとりもなおさず、「冊封体制」という中国歴代王朝の長きにわたる頑強な伝統的支配権力に色濃く染められ、さらには、近代資本主義の支配・規制という二重の抑圧の下で、苦難の歴史を余儀なくされてきた「東アジア地域世界」※ において、その東端の一角に位置する日本列島に、「労」「農」一体融合の抗市場免疫に優れた「菜園家族」を基調とする、素朴で精神性豊かな自然循環型共生社会(じねん社会としてのFP複合社会)の種子をしっかり着床させ、成長を促し、生命系の未来社会論具現化の道である「菜園家族」社会構想に依拠して、非武装・不戦、非同盟・中立の国土づくりに尽力することを意味するのである。
こうしてはじめて、草の根の民衆による、民衆のための真の東アジア民衆連帯創出のスタートラインに立つことができるのではないか。その意味で、まず私たち自身が自らの国において、この道を追究することの意義は、ひとり日本一国の問題にとどまらず、計り知れなく大きいと言わなければならない。
日米軍事同盟のもと、いつまでもアメリカの権力的支配層に追従し、東アジアの民衆に背を向け、この地域世界に攪乱をもたらしている場合ではないのである。今こそ、自らの「菜園家族的平和主義」のこの道の選択を、いよいよ決断する時に来ているのではないだろうか。
※ 「東アジア地域世界」の前近代から近現代におよぶ歴史構造とその特質については、拙著『新生「菜園家族」日本 ―東アジア民衆連帯の要―』(小貫雅男・伊藤恵子、本の泉社、2019年)の第Ⅰ章・第Ⅱ章・第Ⅷ章に詳述。
◆“高次自然社会への道” 終了にあたって≪5≫の引用・参考文献◆
藤岡惇『グローバリゼーションと戦争 ―宇宙と核の覇権めざすアメリカ』大月書店、2004年
吉川顯麿「“ウクライナ戦争”の1年 ―対ウクライナ軍事支援・武器供与の拡大と戦闘の拡大―」『金沢星稜大学論集』第56巻第2号、金沢星稜大学経済学会、2023年3月
文在寅「平凡さの偉大さ 新たな世界秩序を考えて」ドイツ紙『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』への寄稿(聯合ニュースのWEBサイトに韓国語の原文からの邦訳が掲載)、2019年5月7日
田中彰『小国主義 ―日本の近代を読みなおす―』岩波新書、1999年
日高六郎『戦後思想を考える』岩波新書、1980年
山室信一『憲法9条の思想水脈』朝日新聞出版、2007年
中江兆民 著、桑原武夫・島田虔次 訳・校注『三酔人経綸問答』岩波文庫、1965年
飯田進「戦いは昔のこととさとれ 我人 ―田中正造の平和思想」『法学館憲法研究所報』第10号、HuRP出版、2014年
内村鑑三『後世への最大遺物 デンマルク国の話』岩波文庫、1946年
小貫雅男・伊藤恵子『気候変動とパンデミックの時代 生命系の未来社会論 ―抗市場免疫の「菜園家族」が近代を根底から覆す―』御茶の水書房、2021年
――― ◇ ◇ ―――
★これで一旦、連載“高次自然社会への道”は終了させていただきます。
今、私たちは、大きな転換期に生きています。
主題の核心に切り込んだ、率直なご意見やご感想などをお待ちしています。
協同の力で、新しい時代の局面が開かれていくことを心から願っています。
なお、新しい連載の開始時期・主旨等については、日をあらためてお知らせいたします。
2024年6月14日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/
菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ
https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/