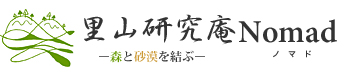
コラム「菜園家族 折々の語らい」(3)
コラム
菜園家族 折々の語らい(3)
21世紀、私たちがめざす未来社会 ―その理念と方法論の革新
―19世紀未来社会論の「否定の否定」の弁証法―(その1)
◆ こちらからダウンロードできます。
コラム「菜園家族 折々の語らい」(3)
(PDF:564KB、A4用紙9枚分)
民衆は黙ってはいられない ―「Kings」のお膝元でも民衆の蜂起が
1990年代初頭、第二次大戦後の世界を規定してきた米ソ二大陣営の対立による冷戦構造が崩壊し、アメリカ単独覇権体制が成立することになる。しかし、それも束の間、アメリカ超大国の相対的衰退傾向の中、その弛緩に乗ずるかのように、旧来の伝統的大国に加え、新興大国が入り乱れる新たな地球規模での多元的覇権争奪の時代がはじまった。
中国は、改革開放の時代を経て、今や日本を追い越し、アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国となった。習近平国家主席が世界に向かって唱える巨大経済圏構想「一帯一路」のもと、経済的・政治的影響力を拡大し、周辺諸国との軋轢を生み出している。中国「社会主義」はすっかり変質したかのようである。
グローバル市場原理のもと、無秩序な自由貿易の拡大とともに、過酷な競争経済が世界を席捲して30年余が経過した今、その歪みが世界各地で噴出している。グローバル多国籍巨大企業や巨大金融資本に莫大な富が集中する一方で、各地の風土に根ざした人々のささやかな暮らしは破壊されていく。
その荒波は、開発途上国のみならず、超大国アメリカをはじめ、先進工業国自身の国内産業、庶民の暮らしをも容赦なく侵蝕した。先進諸国の多くの人々が、従来の延長線上に約束されていたはずの「豊かな暮らし」から滑り落ちていったのである。
その不満と不安から、アメリカ、EU諸国、ロシア、日本をはじめ、世界各地の大衆の間で偏狭な「愛国心」、排他的ナショナリズムが醸成され、これを背景に大衆迎合的な新興政党が台頭し、「強いリーダー」出現の待望と支持が広がりを見せている。「米国第一主義(アメリカ・ファースト)」を掲げるトランプ氏の2017年1月の大統領就任と2024年11月の大統領選での返り咲きは、こうした世界的傾向の結末的象徴であるとも言えよう。
同時に、横暴をきわめる新たな「Kings」トランプ政権の強権的手法と欺瞞、むしろ深まりゆく社会・経済の矛盾に対する抗議も、全米各地で巻き起こっている。奴隷解放運動、公民権運動、ベトナム反戦運動の歴史的伝統を脈々と受け継ぎ、社会の不条理に異議申し立てを唱えてやまないアメリカ民衆の願いが、一時の熱狂から失望に変わることなく、未来を見通し、持続的かつ力強く育っていく道筋と理論の鍛錬が求められている。
ソ連・東欧の「社会主義」体制の崩壊によって、人々は、かつて希望の星と仰いだ人類の理想への道に幻滅し、めざすべき新たな未来への道を見失ったまま、さまよっている。地球規模での混迷と混乱の中、剥(む)き出しの欲望が渦巻き、モラルの崩壊、欺瞞と策略の蔓延、暴力と紛争と戦争の常態化を招き、恐るべき暗黒の世界を現出している。
今、世界の多くの民衆は、自らの生活基盤を根底から切り崩され、先行きの見えない日々に苛立っている。超大国アメリカをはじめ、日本など先進諸国に顕在化している大衆の不満を背景にした排他的志向も、醜い分断と対立も、その真の原因を突きつめていくならば、結局、今日の耐えがたい閉塞感を根源から打開する新たな未来への指針、つまり、従来の19世紀未来社会論に代わる新たな展望と理論の不在に遠因があることに気づくはずだ。
少なくとも、ソ連・東欧の「社会主義」体制の崩壊を機に、その考察・考究は、わが身の問題として、とうになされてしかるべきであったはずである。
こうした状況を生み出してしまった要因は、一体、何だったのか。それは、今日の近代経済学の思潮に不本意ながらもいつの間にか知らず知らずのうちに呑み込まれ、かつまた、19世紀未来社会論の枠組みの残映に囚われ、そこから抜け出すことができないことと決して無関係ではない。
このことをしかと念頭に置き、19世紀未来社会論の可能性と限界を今、あらためて見定めつつ、新たな21世紀未来社会論の探究と構築に着手する時に来ているのではないか。
1.19世紀未来社会論の到達点と限界
近代に先立って現れた民衆の自然権的「共産主義」の先駆的思想
イギリス産業革命が進行し、近代資本主義が形成される中で生まれてきた、ロバート・オウエンなどのいわゆる空想的社会主義といわれる一連の思想や、今日では高校の教科書にも記述されている「社会主義」とか「共産主義」という用語の根底に流れる思想は、はたして近代に限られた近代特有の産物であったのであろうか。決してそうではない。
それは、近代以前の古き時代から人類史の中に脈々として伝えられ、人々の心を動かし、時には民衆による支配層への激しい抵抗や闘いをよびおこし支えてきた、根源的な思潮ともいえる。
それは、私利私欲に走るあさましさ、人間が人間を支配する不公正さ、抑圧される人々の貧困や悲惨さへの憤りに発する思想でもあり、人間の協同と調和と自由に彩られた生活を理想とする人類の根源的な悲願でもあり、したがって、おのずから時代を超えて繰り返し生まれてくる思潮にほかならない。
キリスト教も「貧しきものは幸いなり」とし、私利私欲を堕落とみなし、少なくともその初期には、共有財産による「共産主義」的教団生活を理想としていた。中世においても、キリスト教の教父たちやスコラ哲学の信奉者たちの中には、人類始原の自然状態における人々の自然権は、私有財産による貧富の差別をともなわず、すべてのものの共有にもとづく公正で自由で平等な生活を実現するものであったと考え、この理想的自然状態を、私有財産成立後の人間の腐敗堕落の状態と対比して発想する人たちが、少なからずいた。
こうした思潮の伝統は、中世末期から、農民一揆を支える思想として、現実的な影響力を示していた。神や仏の前に、人間は本来、平等であり、財産や身分による差別は不当であり、来世での救済だけではなく、この世においても公正で共同的な生活を実現する世直しがなされなければならないという思想は、ヨーロッパだけではなく、世界各地の宗教の内にあらわれ、時には激しい農民の一揆や反乱を支えた。
日本でも、15世紀後半から100年にもおよび、近畿・北陸・東海に広がった浄土真宗門徒による一向一揆、さらには、江戸時代を通じて各地に展開した農民一揆などに、こうした思想が色濃く認められる。
江戸中期に『自然真営道』を著した安藤昌益(1703~1762)は、自然の営みと「直耕」の人々の生産活動を基本として、共有、皆労、平等の共同生活を「自然世(じねんのよ)」として実現することを呼びかけている※ 。彼の考えは自然生的ではあるけれども、世界史的にも先駆的で独創的な「共産主義」思想に到達したものであるとして、評価されている。
※ 長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」(2024年9月1日~2025年3月14日 里山研究庵Nomadホームページに連載)のエピローグの2節の項目「自然観と社会観の分離を排し、両者合一の思想を社会変革のすべての基礎におく」を参照のこと。
人類の歴史は民衆の心に根ざす自然権的思潮の終わりのない「否定の否定」の弁証法
近代に先だってあらわれた、これらの先駆的な自然権的「共産主義」思想は、おおくの場合、人類始原の自然状態における、差別や抑圧のない共同的で平等な生活を理想とする見地に立っていた。このような見地から、私有財産とそれをめぐる私利私欲は、身分的な支配隷属関係とともに、人間の腐敗や堕落をもたらすものとして、批判されている。
現存社会の荒廃や抑圧や不公正が、人間の本来あるべき原初の姿と対比して、不自然で歪んだ社会状態であると批判するこの思想は、人間の根源に根ざす普遍的な思想であるだけに、今日までたえず繰り返しあらわれてきたし、これからも繰り返しあらわれてくるにちがいない。そして、その自然権的思潮は、その時代時代の社会と思想の到達水準に照応した新たな内容を盛り込み、新しい形式をととのえて再生されることになる。
太古の人間社会の共有、平等、自由の自然状態を歪めてきたものは、何であり、誰であるのかの疑念が深まれば深まるほど、やがてその考えが科学に転化していくのは、自然の成り行きでもあった。商品経済による有産階層の権利を自然視する啓蒙主義的思想で代替して済まされるものではなかったのである。
むしろ、人間に本来的で根源的な基本的人権とは何か、自然と人間、人間と人間との関係を律すべき根本の原則とはいかなるものなのか、資本主義的商品経済のもとでの人間の疎外や自然の荒廃の原因は何なのか、その究明へとむかっていくのである。
19世紀、マルクスやエンゲルスたちの新たな思想とその理論も、まさしくこうした人類史の基底に脈々として流れる自然権にもとづく民衆の根源的な思想を受け継ぎ、さらに19世紀30年代以降のイギリス資本主義の新たな発展と、それに内在する対立・矛盾とを組み込む形で、必然的にあらわれてきたものであると言わなければならない。
それから200年近くが経った。私たちに今、問われているのは、21世紀の今日の世界とわが国の新たな時代状況の中で、そこに内在する新たな対立と矛盾を組み込みながら、如何にして私たち自身の思想と理論を高次の段階へと発展させていくのかという、人類史を貫く民衆共通の根源的願いに連なる課題そのものなのである。
「否定の否定」の弁証法は、今日のこの時点で途絶えるはずがない。これからも繰り返されていくであろう。その停止は、世界の死を意味するのである。
19世紀に到達したマルクスの未来社会論
マルクス・エンゲルスの最大の功績は、徹底した唯物論哲学を基礎に、人類の始原から近代資本主義に至る人類の全史を見通して総括しうる唯物史観を確立し、これを「導きの糸」として、経済学の研究によって資本主義の内的矛盾とその運動を解明し、資本主義経済学の原理論を確立した点にある。
これにひきかえ、意外に思われるかもしれないが、マルクスやエンゲルスの膨大な著作の中には、未来社会についての具体的で詳細な体系的プランはなく、ごく簡単にしか示されていない。
マルクス以前のロバート・オウエンやサン・シモン、フーリエなどによるユートピア的社会主義が、未来社会の詳細な設計図を描いていたのに比べ、あまりにも叙述が少ないことについては、これまでにもしばしば指摘されてきたところである。
このことは、マルクスやエンゲルスの研究の目的・課題の焦点が、当時の状況においてどこにあったのかということにも、おおいに関連しているように思われる。
それは、マルクスにとっては、ヘーゲルの観念論哲学とその社会観の批判からはじまって、さらに、それに対置する唯物史観を確立し、それを「導きの糸」として経済学の本格的な研究に取り組み、資本主義の運動法則を徹底的に解明することが最大の目的であり、またその時代がマルクスに要請した最大の課題でもあったからである。
それから、もう一つの理由は、今から百数十年前の19世紀の後半には、すでに資本主義は確立していたものの、まだ発展途上にあったということである。マルクス自身の理論からしても、社会革命は資本主義に内在する法則にしたがい、生産力の一定の高まりによって生産関係が変革されること、また変革主体としての労働者階級の質と量の一定の発展水準を待たなければならないこと、こうした諸条件が具体的に把握できていない段階で、未来社会の具体的プランや見取図を詳細に提示すること自体、慎重であるべきだという考えに基づいていたのである。
たしかにマルクス・エンゲルスは、人類史を総括し、資本主義社会の運動法則の解明を通じて、社会主義・共産主義への移行の必然性を明らかにすることによって、資本主義にかわる未来社会への壮大な展望を示すことができたのであるが、未来社会についての具体的で詳細な設計図やプランの提示には、今述べたような理由から極めて慎重であったのは確かである。しかし、未来社会の問題に全く触れていなかったわけではない。
マルクスとエンゲルスの共同執筆による初期の歴史的文書『共産党宣言』(1848年)の中には、資本主義にかわる未来社会についての大まかではあるが比較的まとまった叙述がある。
その中では、まずはじめに、今日までのあらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史であるとおさえた上で、労働者革命の第一歩は、労働者階級を支配階級にまで高めること、民主主義を闘いとることであると述べている。
そして労働者階級は、資本家から次第にいっさいの資本をうばいとり、いっさいの生産用具を、国家すなわち支配階級として組織された労働者階級の手に集中し、生産諸力の量をできるだけ急速に増大させるために、その政治的支配を利用するであろうと述べている。
もちろんこのことは、はじめは所有権と資本主義的生産諸関係への専制的な規制を通じてのみ、おこなわれるものであり、したがって、これらは経済的には不十分で、長もちしえないように見えるが、運動がすすむにつれて自分自身をのりこえて前進し、しかも全生産様式を変革する手段として不可欠であるような諸方策によってのみおこなわれるのである、としている。
これらの方策は当然、国によって色々であろう。しかし、最もすすんだ国々では、次のような諸方策がかなり全般的に適用されるであろうとして、10項目の方策を具体的に挙げている。
その後も、マルクスは断片的ではあるが、未来社会論に触れて自身の見解をさまざまな形で述べているが、資本主義の根本矛盾を「生産手段の社会的規模での共同所有を基礎におく、社会的規模での共同管理・共同運営」によって、すなわち「上からの統治」によって克服し、未来社会を展望するというこの『宣言』の基本線は崩していないと見るべきであろう。
ところで、「上からの統治」の思想は、古代奴隷制にはじまり、中世農奴制、近代資本主義、そして今日においてもそうなのであるが、人類が長きにわたって引き継いできた根強い負の思想的遺産である。
それはもともと支配層に固有の思想でありながら、民衆の心の中にも深く浸透し、その時々の時代相応の内容を組み込む形で強化され、支配、被支配層双方が相俟って、実に執拗に繰り返し再生産されてきたのである。残念ながら一般民衆もいつしかそれに馴らされてしまい、今や当たり前の常識にすらなってしまった。
19世紀の未来社会論、特にマルクス・エンゲルスの初期の著作にあたる『宣言』は、母胎とも言うべき近代からの訣別を意図しながらも、前代からのへその緒を依然として引きずり、なかんずく「上からの統治」の根深い思想を払拭しきれずに、その母斑を色濃く留めていると言わざるを得ない。
近代社会の本質は、資本と賃金労働両者の対立構図にあり、近代を超克するとは、最終的には資本と賃労働の両者を克服し止揚することなのであるが、結局、19世紀の未来社会論においては、前近代からの負の遺産であるこの「上からの統治」の根深い思想を完全に払拭しきれずに、専制的独裁への契機を孕む「生産手段の社会的規模での共同所有を基礎におく、社会的規模での共同管理・共同運営」という道を不覚にも優先・先行させることを許し、まさにそれに依拠した「上からの資本の廃絶」をめざすものになっている。
その結果、もう一方の賃労働それ自体の克服、止揚の問題については、賃金労働者の自己変革による自らの主体性確立のプロセスを遅らせ、あるいは閉ざすこととなり、それがその後の20世紀の現実の社会主義形成期において、民主主義の欠如と専制的独裁体制を生み出す重大な土壌ともなって、やがて体制そのものの崩壊へとつながっていったのである。
今こそ19世紀未来社会論に代わる、私たち自身の草の根の21世紀未来社会論を
19世紀、マルクスやエンゲルスたちにとって、歴史観の探究とその構築(人類史総括としての歴史学研究)は、経済学研究の導きの糸であった。その意味で歴史観の構築と経済学の研究は、紛れもなく車の両輪となっていた。
こうした包括的で全一体的(ホリスティック)な研究の成果から自ずと導き出された19世紀のマルクス未来社会論(生産手段の社会的規模での共同所有に基礎をおく共同管理・共同運営によって、資本主義の根本矛盾を克服し、未来社会を展望する)は、19世紀から20世紀に生きる人々にとって、それがその後どんな結末をもたらしたかは別にしても、時代の行く手を照らし出す光明となって、確かにある時期までは夢と希望と生きる目標を与え、現実世界をも動かす民衆の大きな原動力となっていたことは、間違いのない歴史的事実であろう。
しかし、20世紀末のソ連、東欧、モンゴルをはじめとする社会主義体制の崩壊と、21世紀の今日、現に進行している中国「社会主義」の変質という歴然たる事実によって、そして何よりもマルクス未来社会論が提示されてからおよそ170年という歳月を経た世界と社会の大きな変化によって、資本主義超克としての19世紀未来社会論の理論的限界と欠陥は、一気に露呈することになった。
その根本原因は、先にも述べたように、前近代からの負の遺産とも言うべき「上からの統治」の根深い思想を払拭しきれずに、「生産手段の社会的規模での共同所有を基礎におく、社会的規模での共同管理・共同運営」を優先・先行させるという、19世紀未来社会論の核心そのものに胚胎していたと言えよう。
端的に述べるならば、家族小経営を軽視し、人間のいのちの再生産に最低限度必要不可欠な土地や生産用具、つまり生産手段を人間から切り離したまま、根なし草同然の賃金労働者(近代における高次奴隷身分※ )の大群を一国規模のピラミッドの土台の基底に据えおいた状態で、社会的規模での共同所有を重視するあまり、それを優先・先行させること自体に根源的問題があったと見るべきである。
自立の基盤を失い、自己鍛錬と自己の主体形成の小経営的基盤を失った人間は、個性の多様な発達の条件をも根底から奪われ、長期的に見れば人間の画一化の傾向を辿らざるをえない。こうした社会的土台は、中央集権的専制支配を許す土壌に転化する危険性を当初から孕んでいたことに刮目すべきである。
これまで再三にわたり提起してきた、革新的「地域生態学」に基づく草の根の21世紀“生命系の未来社会論”、その具現化の道である「菜園家族」社会構想を貫く問題意識は、まさにこの点にある。つまり、今ではすっかり常識となった、近代の落とし子とも言うべき根なし草同然の賃金労働者という人間の社会的生存形態そのものの自己変革を、何よりもまず賃金労働者自らが主体的にはじめるよう迫られているのである。
21世紀の今求められているのは、専制的独裁への契機を孕む「生産手段の社会的規模での共同所有を基礎におく、社会的規模での共同管理・共同運営」を性急に導入し、それに依拠して「上からの資本の廃絶」を優先・先行させる道ではなく、あくまでも「労働主体そのものの下からの自己変革」を重視することによって、「資本と賃労働の対立構図」を根源的に止揚し、未来への展望を切り開くことなのである。
すなわちそれは、賃金労働者が生産手段(生きるに必要な最低限度の農地と生産用具と家屋等々)との「再結合」を果たすことによって、根なし草同然の自らの人間の社会的生存形態(賃金労働者)そのものを主体的に自己変革し、近代と前近代の「労」「農」人格一体融合の、抗市場免疫に優れた自律的な新しい人間の社会的生存形態(「菜園家族」)へと止揚すること。これによって、社会の基層に沈滞し、崩壊寸前にある地域コミュニティの再生を現実のものとし、その潜在能力の最大限の発揚を可能にする。
これこそが、民衆自身による近代超克の社会変革にとって、避けてはならない自己の主体形成の過程なのである。
この過程を閉ざしてきた遠因は、19世紀未来社会論の先の核心部分にあると言ってもいい。これは、社会主義的変革に限らず、世界各国、各地域におけるあらゆる時代にも通底する問題でもある。
現に先進資本主義国、なかんずくわが国にも顕著に見られるように、人々の意識もあらゆる政党も、いつしか近代の悪弊とも言うべき欺瞞の「選挙」の罠にはめられ、埋没していく。果てには民衆の精神の真髄すら冒され、「お任せ民主主義」が蔓延し、草の根民主主義の芽をことごとく摘み取られていく。
今日のこの民主主義の衰退と堕落を生み出した遠因も、まさに民衆の主体性を無視したこうした「上からの統治」の根深い思想を、21世紀の今日においても、いまだに払拭できずにいることにあると言ってもいいのではないか。
20世紀も終わり21世紀初頭の今、私たちは、2011年3・11の巨大地震と巨大津波、東京電力福島第一原子力発電所の苛酷事故という未曾有の大災害、2020年新型コロナウイルス・パンデミック、そしてウクライナ戦争、ガザ戦争を境に、社会が大きく転換する時代の奔流のまっただ中に立たされている。
精彩を失ったかつての19世紀未来社会論に代わる、21世紀の私たち自身の新たな草の根の未来社会論を今なお探りあぐね、人々は、不確定な未来と現実の混沌と閉塞状況の中で、明日への希望を失っている。
まさに今日、21世紀全時代を貫き展望するに足る未来像の欠如こそが、東日本大震災の被災地の復興のみならず、このたびの新型コロナウイルス・パンデミック下においても、日本各地の地域再生の混迷と労働運動の沈滞にさらなる拍車をかけ、そこに生きる人々を諦念と絶望の淵に追い遣っている。
この地域の現実と労働の現場に気づかなければならない。私たちは、いつ止むとも知れぬ暴風雨の荒れ狂う大海を羅針盤なしで航海を続け、さ迷っているといってもいい。
手をこまねきそうこうしているうちに、現実は容赦なく進行していく。市場原理至上主義「拡大経済」のもと新自由主義的思潮の奔流に巻き込まれ、生命の源ともいうべき自然は破壊され、人間生活の基盤となる「家族」と「地域」、「労働」の現場はいよいよ土台から揺らぎ、ついには崩壊の危機に晒されていく。
生産力至上主義のもと科学技術と市場原理主義が手を結ぶ時、人間社会は止めどもなく暴走し、結局その行き着く先は人類破滅の恐るべき結末になるのだということを、何よりもフクシマは決してあってはならない自らの惨状をもって、私たちに警告したのではなかったのか。今こそ一刻も早く近代の「成長神話」の呪縛から解き放たれ、やがて来る未来のあるべき姿を確かなものにしなければならない。
かつての19世紀未来社会論の肯定的側面を継承しつつも、その限界と欠陥を根源的に克服し、イギリス産業革命以来の近代を超克する21世紀の未来社会論としても同時に成立し得る、私たち自身の草の根の21世紀社会構想をいよいよ深めていかなければならない時に来ている。
そのためには何よりもまず、今日の日本社会と世界の行き詰まったこのどうしようもない現実そのものに向き合い、その個別具体的現実から着実に帰納を重ねることによって、これまでの思考の枠組み(パラダイム)と方法を根源的に問い直すことから再出発するよう迫られているのである。
※ 前掲長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」のエピローグ「高次自然社会への道」の2節「人類史を貫く『否定の否定』の弁証法」を参照のこと。
◆コラム「菜園家族 折々の語らい」(3)の引用・参考文献◆
金谷治『老子 ―無知無欲のすすめ―』講談社学術文庫、1997年
安藤昌益「稿本 自然真営道」『安藤昌益全集』(第一巻~第七巻)、農山漁村文化協会、1982~1983年
ロバート・オウエン『ラナーク州への報告』未来社、1970年
マルクス、訳・解説 手島正毅『資本主義的生産に先行する諸形態』国民文庫、1970年
マルクス『資本論』(一)~(九)岩波文庫、1970年
ウィリアム・モリス、訳・解説 松村達雄『ユートピアだより』岩波文庫、1968年
A・チャヤーノフ『農民ユートピア国旅行記』晶文社、1984年
カール・ポラニー 著、吉沢英成・野口建彦・長尾史郎・杉村芳美 訳『大転換 ―市場社会の形成と崩壊―』東洋経済新報社、1975年
玉野井芳郎『生命系のエコノミー ―経済学・物理学・哲学への問いかけ―』新評論、1982年
ポール・エキンズ 編著、石見尚ほか 訳『生命系の経済学』御茶の水書房、1987年
ジェイムズ・ロバートソン 著、石見尚・森田邦彦 訳『21世紀の経済システム展望 ―市民所得・地域貨幣・資源・金融システムの総合構想―』日本経済評論社、1999年
藤岡惇「帰りなん、いざ豊饒の大地と海に ―『平和なエコエコノミー』の創造・再論―」『立命館経済学』第65巻 特別号13、立命館大学経済学会、2016年
友寄英隆『「人新世」と唯物史観』本の泉社、2022年
聽濤弘『<論争>地球限界時代とマルクスの「生産力」概念』かもがわ出版、2022年
藤岡惇 書評『人新世の「資本論」』(斎藤幸平 著、集英社新書、2020年)『季刊 経済理論』第59巻第1号、経済理論学会 編集・発行、桜井書店、2022年
――― ◇ ◇ ―――
★このコラム「菜園家族 折々の語らい」は、これからも随時、掲載していく予定です。
読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2025年11月9日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/
