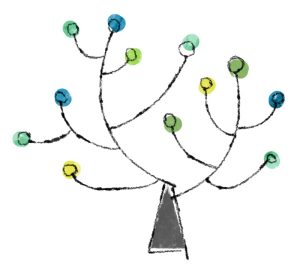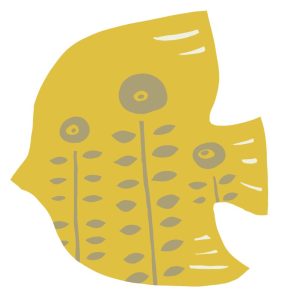連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」の総括にかえて “高次自然社会への道”(その8)
連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」の終了にあたり
≪総括にかえて≫
“高次自然社会への道”(その8)
―自然との再融合、原初的「共感能力」(慈しむ心)再建の可能性―
◆ こちらからダウンロードできます。
連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」の
≪総括にかえて≫ “高次自然社会への道”(その8)
(PDF:690KB、A4用紙19枚分)
8 19世紀未来社会論のアウフヘーベン
―その展開のメカニズムと世界史的意義―
19世紀未来社会論のアウフヘーベン
止揚・熟成・・・そして世界の根源的大転換
「菜園家族」基調のCFP複合社会を経て
自然と人間の再融合
人間復活の高次自然社会へ
世界に誇る日本国憲法具現化の究極の道
1)CFP複合社会から自然循環型共生社会(FP複合社会)を経て高次自然社会へ
CFP複合社会の展開過程とその特質
この世界に、そしてこの宇宙に存在するすべては、絶えず変化の過程にある。それはむしろ、変化、すなわち運動そのものが存在である、と言ってもいいのかもしれない。
21世紀、生命系の未来社会形成の初期段階で、決定的に重要な役割を担う「菜園家族」基調のCFP複合社会も、決してその例外ではない。
ここでは、CFP複合社会の展開過程を、まず、C、F、P3つのセクター間の相互作用に注目しながら見ていきたい。そして、その側面から、人間の労働とは一体何なのかを問いつつ、その未来のあるべき姿についても同時に考えることにする。
まず、資本主義セクターCの内部において、現代賃金労働者(サラリーマン)と生産手段(自足限度の小農地、生産用具、家屋など)との再結合が進み、「菜園家族」への転化が進行していく。
それに伴い、家族小経営(「菜園家族」と「匠商(しょうしょう)家族」)セクターFは、時間の経過とともに発展、増大の一途を辿り、その結果、セクターCにおける純粋な意味での賃金労働者は、当然のことながら、漸次、減少していく。
“高次自然社会への道”(その7)で述べたように、国土に偏在していた巨大企業や官庁などが分割・分散され、全国各地にバランスよく配置されることによって、賃金労働者と農民の人格を二重にもつ「菜園家族」の生成はいっそう進展し、全国の隅々にまで広がっていく。
こうして、自給自足度の高い抗市場免疫の「菜園家族」が国土に隈無く広がることと相俟って、巨大企業の分割配置がさらに促進され、企業の規模適正化が確実に進む。
やがて、適正規模の工業や流通・サービス産業から成る地方の中小都市を中核に、「菜園家族」、「匠商家族」のネットワークが、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)全域に広がりを見せ、美しい田園風景が次第に国土全体を覆っていくことであろう。
その結果、市場競争はおおいに緩和の方向へと向かっていく。こうして資本主義セクターCは、自然循環型共生社会にふさわしい性格に次第に変質する過程を辿らざるを得なくなっていくであろう。
他方、発展途上にある家族小経営セクターFでは、自然と人間との間の直接的な物質代謝過程が回復し、自然循環型共生のおおらかな生活がはじまる。労働に喜びが甦り、人間の自己鍛錬の過程が深まっていく。自然循環型共生の思想とそれにふさわしい倫理に裏打ちされた、新たな人格形成の過程がはじまる。「菜園家族」、「匠商家族」独自のきめ細やかで多様な労働を通じて、人類始原の原初的「共感能力」(慈しむ心)が甦り、人々に和の精神が芽生え、共生の精神によって人々の輪が広がっていく。
原初的「共感能力」(慈しむ心)再建の時代がはじまるのである。
このCFP複合社会形成の過程は、おそらく10年、20年といった短い歳月ではなく、30年、50年、あるいはそれ以上の長い時代を要することになるのかもしれない。
それは今日、人類にとって避けては通れない喫緊の課題となっているエネルギーや資源の浪費抑制や、IPCC特別報告書『1.5℃の地球温暖化』がめざす、2050年までに世界のCO2排出量を実質ゼロにするという国際的な警告目標にも呼応する、重要なプロセスのなくてはならない一翼を担うことになるであろう。
こうした長きにわたる時代の経過の中で、家族小経営セクターFはますます力をつけて発展していく。それにともなって、資本主義セクターC内部の個々の企業や経営体は、次第に自然循環型共生社会にふさわしい内実と規模に変質を遂げながら、漸次、公共的セクターPに転化・移行していく。
やがて、このCFP複合社会展開過程の最終段階では、資本主義セクターCはその存在意義を失い、ついには自然消滅し、家族小経営(「菜園家族」と「匠商家族」)セクターFと公共的セクターPの二大セクターから成る、じねん社会としてのFP複合社会(自然循環型共生社会)が誕生する。この時はじめて、資本主義は超克されるのである。
それでも、この段階に至ってもなお、「菜園家族」を基調とする家族小経営セクターFが、依然としてこの社会の土台に据えられていることに、かわりはないであろう。
このように、CFP複合社会形成の長期にわたる展開過程を経て、最終的に成立したF、Pの二大セクターから成る脱資本主義のFP複合社会は、さらに長期にわたる熟成のプロセスを経て、ついには人間復活の高次自然社会に到達する。そこでは、階級的権力の象徴である国家は次第に消滅へと向かう。この高次自然社会は、はるか遠い未来に到達すべき人類の悲願であり、究極の目標であり、夢でもある。
肉体労働と精神労働の分離を排し、労働を芸術に高める
CFP複合社会の形成からはじまって高次自然社会に到達する、この長いプロセスを貫く特質は、いずれも「菜園家族」がいわば生物個体としての人体における個々の細胞のように、地域社会の最小の基礎単位であり続ける点である。
したがって、「菜園家族」が農地と生産用具を含む生産手段との有機的な結合を維持している限り、この家族の構成員である子供から老人に至る個々人にとっても、自然と人間との間の直接的な物質代謝過程が安定的に確保されることになる。
この過程に投入される労働を通じて、人間は自然を変革すると同時に、何よりも人間自身をも変革する条件とその可能性を絶えず保持し続けるであろう。
このことは、CFP複合社会の形成から高次自然社会に至る全過程を貫く法則である。
したがって、社会の細胞である最小の基礎単位が「菜園家族」である限り、この社会は、人間の発達と人格形成を基軸に据えた、これまでには見られなかった優れた社会システムとしてあり続けることが可能になるのである。
生産手段(「菜園」)が家族小経営の基盤にしっかりと据えられている限り、「菜園」での労働過程の指揮系統は、労働主体である個々の人間の外部にあるのではなく、労働主体である人間と一体のものであり続ける。したがって「菜園家族」は、まさにこの指揮系統を自らのものとして自己の内部に獲得し続けるであろう。
労働過程を指揮する営みを精神労働とし、それに従って神経や筋肉を動かす労働を肉体労働とするならば、もともと精神労働と肉体労働とは、人類史の長きにわたって、一人の人間の中に分かち難く統合されていたものである。
その両者の分離は、労働する人間から生産手段(農地、生産用具、家屋など)を奪った時からはじまるのであるが、この精神労働と肉体労働の両者の分離こそが、労働から創造の喜びを奪い、労働を忌み嫌う傾向を生み出した。
主体性を失い、苦痛のみを強いられるこうした労働とは対照的に、芸術的創作は疲れや時間の経過さえ忘れさせるほど、人間に喜びをもたらすものである。それは、本来の芸術的創作が精神労働と肉体労働の両者の統一されたものであり、まさにそこに創造の喜びの源泉があるからにほかならない。
生命系の未来社会論具現化の道である「菜園家族」社会構想は、資本主義が生み出した、賃金労働者と生産手段(自足限度の小農地、生産用具、家屋など)とのまさにこの分離を「再結合」させることによって、労働過程に指揮する営み、つまり精神労働を取り戻し、肉体労働と精神労働の両者の高次統一を実現し、労働を芸術にまで高めようとするものなのである。
労働が芸術に転化した時はじめて、人間は、創造の喜びを等しく享受することになるであろう。その時、人間は、市場原理至上主義の新自由主義的「拡大経済」のもとで、物欲や金銭欲の充足のみに矮小化された価値観から次第に解き放たれ、多元的な価値に基づく多様で豊かな幸福観を形成し、前時代には見られなかった新たな倫理と思想を育んでいくにちがいない。
CFP複合社会がどんなに高い水準に達し、さらに人類の夢である高次自然社会に到達したとしても、この社会から家族小経営としての「菜園家族」が消えることはないであろう。
「菜園家族」がこの社会の最小の基礎単位であり続けなければならない理由は、まさに人間の労働に人類本来の創造の喜びを取り戻すために不可欠なものであるからであり、しかも、自然との再融合による素朴で精神豊かな世界への回帰を実現し、健全で豊かな人格形成にむけて、人間そのものの変革過程を恒常的かつ永遠に保障するものであるからなのである。
人間の変革過程が静止した時、人間は人間ではなくなるであろう。
2)未来社会を身近に引き寄せる「セクターC、F、P相互の対立と依存の展開過程」
2000年に初めて「菜園家族」社会構想を提起して以来、私たちのもとには、さなざまな意見が寄せられてきた。
その中には、「従来の社会主義理論との違いは何か」、あるいは「資本主義を超克するには、従来の社会主義の道ではだめなのか」といった、これまでの理論的枠組みからすれば当然生ずる自然で率直な疑問も多かった。
これらの疑問に答え、ここであらためて確認しておきたいことは、CFP複合社会の展開過程を通じて、「菜園家族」が週休(2+α)日制のワークシェアリング(但し1≦α≦4)のもとに、自己の週労働日を資本主義セクターCまたは公共的セクターPでの「勤務」と、家族小経営セクターFでの「菜園」とに振り分ける形で、社会的生産を担うということである。
やがて、「菜園家族」を基調とする家族小経営セクターFが隆盛となり、このセクターFが成熟するにつれて、資本主義セクターCは、自己の変革を遂げつつ公共的セクターPに同化・包摂されて、最終的には自然消滅へと向かう。
この時、3つのセクターから成るこのCFP複合社会は、家族小経営セクターFと公共的セクターPの2つのセクターから成る、じねん社会としてのFP複合社会(自然循環型共生社会)へと進化していく。
つまり、家族小経営セクターFの「菜園家族」や「匠商家族」は、CFP複合社会の発展段階において、資本主義セクターCおよび公共的セクターPの社会的生産を担う主体であり、さらに、資本主義セクターCが自然消滅し、より高次のFP複合社会の段階になっても、引き続き自らのFセクターの生産労働の主役であると同時に、公共的セクターPの社会的生産を担う役割を演じ続けることになる。
19世紀未来社会論の主流を継承する考え方、すなわち生産手段の社会的規模での共同所有を基礎に、社会的規模での共同管理・共同運営を優先・先行させる社会実現の道(A型発展の道)では、21世紀の今日に至ってもそうなのであるが、旧社会での変革の主体は賃金労働者であり、新しい社会、すなわち社会主義建設期においても、引き続き賃金労働者がその役割を果たすとされてきた。このことは、今日においても疑問を挟む余地すらなく当然視されている。
これに対して、生命系の未来社会論具現化の道である「菜園家族」社会構想は、その立場をとらない。
新しい社会、すなわち、より高次のFP複合社会に移行するはるか以前の早い時期、つまり、21世紀初頭の今日の段階から、旧社会の生産と生活の担い手である賃金労働者そのものの変革を先行させることを重視する。
つまり、自らの生産の基盤を失った根なし草同然の賃金労働者が、前近代的農民との人格的再融合を果たすことによって、苛酷なグローバル市場に抗する免疫力を備えた「菜園家族」に止揚、転化する。
こうして創出された21世紀の新たな人間の社会的生存形態、すなわち「菜園家族」が社会の基盤にあまねく組み込まれることによってはじめて、近代は、社会の深層から根本的に超克されると見るのである。
近代、すなわち資本主義の軛(くびき)から解き放たれた家族小経営、つまり「菜園家族」や「匠商家族」は、「家族」や「地域」の場により多くの滞留時間を獲得することで、自由闊達で創造性豊かな人間的活動が可能となり、水を得た魚のように息を吹き返す。やがて自己の主体性を回復し、崩壊寸前の窮地に追い込まれた自らの「地域」の再生へと立ち向かっていくであろう。
19世紀以来の従来の未来社会論では、人類理想の未来社会は、遥か遠い彼方の極めて抽象的で漠然とした対象である。
それに対して、21世紀生命系の未来社会論具現化の道である「菜園家族」社会構想では、現実社会(資本主義)とめざすべき未来社会の中間項としてCFP複合社会を措き、「セクターC、F、P相互の対立と依存の展開過程」を具体的に思い描くことによって、未来社会を絶えず私たちの身近な生活の場にまで引き寄せて考えることを可能にしている。
この中間項CFP複合社会の展開過程の中ではじめて、個々人の私的な日常普段の実践がどのような社会的役割を担い、未来社会にどのように具体的に連動していくかが実感的にイメージされるであろう。
したがって、個々人にとっても、自己の日常の実践の意義が絶えず明確に自覚され、本当の意味での自律的で主体的な、しかも持続的な鍛錬が可能になるのである。それは、人々の生きる喜びにつながる、豊かな創意性の源泉でもある。
こうしたことは、もちろん個々人のレベルだけでの問題にとどまらない。農業、非農業を問わず、あらゆる家族小経営をはじめ、多種多様な零細・中小企業やその協同組織体、そして農山漁村・都市部を問わず、さまざまなレベルでの地域協同体としての「なりわいとも」、地方自治体、あるいは労働組合、各種協同組合、その他諸々のNPOなどの非営利団体、さらには営利企業などをも含む、すべての社会的組織や団体にまで押し広げて言えることである。
生命系の未来社会論具現化の道としての「菜園家族」社会構想が、現実と未来社会の中間項としてCFP複合社会を設定したことの意義は、未来社会が遥か遠い非現実的な単なる空想の世界ではなく、まさに現実の個々人の日常普段の生活世界に直結し、そこから直接展開していく実現可能な実践的課題であることを絶えず具体的に実感できる点にある。
21世紀未来社会の構築は、こうした中で促される広範な民衆意識の変革とその分厚い土壌の上にはじめて、民衆主体のより高次の地域政策、さらにはその積み重ねとも言うべき、国レベルでの真に民衆のための長きにわたる政策を通じて、成し遂げられていくものなのである。
3)形骸化した民主主義の現状と「生産手段の再結合」
人類史上、近代に至ってもなお引き継がれてきた、支配層の根強い「上から目線」の民衆統治の思想。それは民衆自身にも、負の遺産として色濃く反映してきた。
前近代のこの負の思想的土壌を払拭しきれないまま、理論化を急いだかつての19世紀未来社会論の根幹を成す、生産手段の共同所有を基礎に、社会的規模での共同管理・共同運営を上から掌握し、それを先行・優先させる社会実現の道(A型発展の道)。
この理論に基づき必然的に社会の上層に組織される「高度な」管理・運営に、常に影のように付き纏う中央集権的専制権力への誘惑。
今日の立場からこれをいかに克服できるかが、21世紀の新たな未来社会論に課せられた大きな宿題なのである。
しかしその克服は、至難の業と言うほかない。
この問題を解決するためにはまず、基本的には「生産手段の共有化」(A型発展の道)に対峙するところの、まさしく「生産手段との再結合」(B型発展の道)、つまり現代賃金労働者(サラリーマン)と生産手段(自足限度の小農地、生産用具、家屋等々)との「再結合」を果たすことによって、21世紀の今日にふさわしい、抗市場免疫の自律的な人間の社会的生存形態(「菜園家族」)を社会の基底に創出し、民衆自身の主体性確立の条件そのものを、本当の意味で自らのものにしていくことである。
まさにこのCFP複合社会の現実的プロセスの展開過程に、専制的権力の跳梁を抑止する、民衆による盤石な本物の民主主義形成の可能性を見出すことができるのではないか。
人類史上長きにわたって、「上から目線」の民衆統治をまともに受け、翻弄されてきた圧倒的多数の民衆が、「選挙」のみに極端に矮小化され、欺瞞に充ち満ちた「お任せ民主主義」の枠組みに閉じ込められ、民衆運動の本来あるべき創造的で豊かな主体性を喪失していく今日の事態を見る時、本物の民主主義の力量を培う、社会の深層からのこうしたプロセスの設定が、如何に大切であるかが分かってくるはずだ。このことを未来社会へのアプローチのあり方の問題として、本気で考えなければならない時に来ている。
近代を超克するまさに最終段階ともいうべき21世紀の今日の段階に至っても、依然として、形骸化した民主主義の現状を憂えるだけで、その主要な原因を、社会上層のあれやこれやの統治システムのあり方のみに矮小化して議論することこそが問題なのではないか。
この専制的権力の跳梁を克服する究極の決め手は、結局、社会の底辺を支える民衆自身が、今日の段階から自らの社会的生存形態を如何にして自ら変革し、自己を、そして自己の主体性を如何にして確立していくかにかかっている。
それは、ほかでもなく「生産手段との再結合」を梃子に、現代賃金労働者(サラリーマン)自らが、如何にして大地に根ざした生活の自律的基盤を獲得していくかなのであろう。民衆の主体性の再構築は、まさにこのことから出発するほかない。
21世紀草の根の生命系の未来社会論としての「菜園家族」社会構想の真髄は、このことに尽きると言ってもいいのではないだろうか。
民衆本来の主体的エネルギーと英知が、まやかしの「選挙」の枠内に閉じ込められ、衰退し疲弊し、国民の意識に「お任せ民主主義」の風潮がますます助長されていく今日の状況の中にあって、このことを特に強調したいのである。
4)より高次のFP複合社会における生産手段の所有形態をめぐって
さて将来、CFP複合社会の資本主義セクターCが自然消滅へと向かい、家族小経営セクターFと公共的セクターPの二大セクターから成る、より高次のFP複合社会(じねん社会としての自然循環型共生社会)に到達した時、社会の基幹かつ主要な生産手段の所有形態と管理運営は、果たしてどのようなものになっているのであろうか。
つまりそれは、公共的セクターPの内実、なかんずく生産手段の所有形態のあり方、すなわち巨大企業の国有化や、地方の各種事業体の公有化の問題、さらには各種協同組合、NPOなど多種多様な非営利団体などをどう評価し、どのように位置づけるかといった問題である。
こうした具体的な内容については、それこそはじめから固定的に予見すべき性格のものではない。CFP複合社会の実に長期にわたる「C、F、P3つのセクター間相互の対立と依存の展開過程」の中で、所有形態をめぐるさまざまな経験や試行錯誤を重ねながら、地域住民の草の根の英知と国民的総意に基づいて、その時どきの社会の発展段階に照応した生産手段の所有形態が、順次編み出されていくものと見るべきであろう。
このような長期にわたるプロセスの矛盾、葛藤と国民的議論の中ではじめて、人間は鍛錬され、民主主義の形骸化は克服され、草の根の民衆による本物の民主主義の可能性は開かれていく。
CFP複合社会というこの長期にわたる苦難のプロセスを避け、上からの急ごしらえの「未来社会」が、たとえ一時的に実現できたとしても、それはいずれ脆くも崩れ去っていく運命にある。
これは、ソ連、東欧、モンゴルをはじめ、その他諸々の「社会主義」の過去の歴史的経験と、現在進行中の中国、ベトナムなどにおける「社会主義」の現実から深く学びとった貴重な教訓でもある。
『新生「菜園家族」日本 ―東アジア民衆連帯の要(かなめ)―』(小貫雅男・伊藤恵子、本の泉社、2019年)では、「東アジア世界」の前近代、および近代以降今日に至る歴史構造の特質と課題を、人知れず権力と闘った、小さな「地域」における草の根の民衆の苦闘の姿から浮き彫りにしてきたのであるが、21世紀の今日、地球規模での多元的覇権争奪がいよいよ熾烈さを増し、東アジア民衆を苦悩と混迷に陥らせている、その根源的で決定的な原因として考えなければならないことは、イデオロギー的評価は別にするとしても、何はともあれ、資本主義の克服をめざしたはずの「社会主義」の変質と崩壊という、打ち消し難い厳然たる事実にあると言わなければならない。
だとすれば、今日のこの東アジア地域世界の抱える困難を思う時、これまで縷々強調してきた中間過程としてのCFP複合社会を抜きにした、まさに資本主義超克の「A型発展の道」の弊害が、如何に甚大であるかが分かってくるはずだ。
マルクスは今から160年前、『経済学批判』(原書1859年、邦訳大月書店、1970年)の序言で、「・・・新しい、さらに高度の生産関係は、その物質的存在条件が古い社会自体の胎内で孵化されおわるまでは、けっして古いものにとって代わることはない。」と述べ、新たな高度の生産関係への移行については、その格別な困難性を指摘し、したがって、極めて慎重であるべきことを示唆している。
もちろんこれは、社会への人間の能動的役割を軽視し、自然史的法則に従いさえすればそれで済むといった、消極的姿勢で言っているわけではない。むしろそれは、後世の人間が、新たな時代状況の中で、その困難を乗り越えるために、如何に新たな未来社会構想を具体的、現実的に編み出していくべきかを、まさに21世紀に生きる今日の私たちに問いかけているものと見るべきではないのか。
19世紀の議論の中で定着していった、資本主義超克の未来社会論としての「A型発展の道」を選択したソ連、東欧、モンゴルなどの「社会主義」体制が、1980年代から90年代初頭にかけて崩壊していった事実は、皮肉にもマルクス自身のこの箴言が的中したとも言えるのではないか。
つまり、「古い社会自体の胎内で」、次代の「物質的存在条件が孵化されおわらない」段階で、「A型発展の道」をめざして強引に政治的権力を奪取し、それを拠り所に、新たな社会の創出の過程で上から一方的に政策を民衆に押しつけ、実行せざるえなかった、ソ連をはじめとする「社会主義」体制が生み出した弊害と、その結末としての自滅を自ら予言した形にもなっているのではないか。
その弊害の中でも、今日私たちが刮目すべき点は、草の根の民衆の主体性が結局、圧殺され、専制的強権体制が肥大化していった事実であろう。それは、先行のこれら「社会主義」諸国に限らず、中国、ベトナムなど現在の「社会主義」諸国、そして、高度に発達した資本主義国が抱え悩んでいる、人類共通の解決しなければならない重い課題でもあるのだ。
私たちは、こうした過去の苦い経験から何を学び、何を教訓とすべきなのか。
それは結局、生産手段の社会的規模での共同所有を基礎に、社会的規模での共同管理・共同運営を優先・先行させる「A型発展の道」に対置して、生産手段を失い、根なし草同然となった近代の落とし子ともいうべき賃金労働者が、生きるに必要な最小限の生産手段を自らのもとに取り戻し、「再結合」を果たすことによって、何よりもまず自己の社会的生存形態の変革を成し遂げ、それを基盤に自らが単なる上辺だけの形式ではなく、まことの主体となって生産と暮らしの場を構築していく「B型発展の道」、すなわち、生命系の未来社会論具現化の道としての「菜園家族」社会構想に行き着くことになるのではないだろうか。
これは、19世紀以来、今日まで主流を成してきた未来社会論に、根本的な転換を迫る問題提起にもなっている。
このことを簡潔に要約するならば、21世紀資本主義の変革において先行すべきは、従来型の「生産手段の社会的共有」ではなく、あくまでも賃金労働者と「生産手段との再結合」が先決であり、そこから民衆自身による、自らの社会の根源的変革のプロセスのすべてがはじまるということなのである。
生命系の未来社会論具現化の道としての「菜園家族」社会構想では、現実の資本主義社会を起点に、めざすべき未来社会に到達するまでのいわば中間項として、CFP複合社会の展開過程を設定している。そして、社会に対する人間の能動的役割を重視し、民衆の豊かな創意の可能性を信頼する立場から、この展開過程をまさに民衆の主体性確立にとって、かけがえのない大切なプロセスとして位置づけているのである。
つまり、民衆が主体となって、日常の身近な生産と暮らしの場に直接参加する、この長期にわたる「C、F、P3つのセクター間相互の対立と依存の展開過程」は、次代の社会基盤となるべき地域協同組織体「なりわいとも」(アソシエーション)の多重・重層的な地域団粒構造を創出し、熟成させていくプロセスにもなっている。
その生き生きとした地域基盤を基礎に、やがて革新的な地方自治体が形成され、各地にその広がりを見せていく。草の根の民衆独自の豊かな政治的力量が次第に涵養されながら、全国規模での国民的ムーブメントの新たな時代を切り開いていくにちがいない。
それは、マルクスが先の箴言の中で、新しい社会への移行には、次代の物質的存在条件が、古い社会自体の胎内で十分に孵化されることの必要性を強調していることとも符合していると言えるのではないか。
民衆の主体性の成長を蔑ろにし、結局、「上からの権力による社会変革」にならざるをえなかった、かつての19世紀未来社会論の限界ないし欠陥を克服し、今こそ21世紀草の根の民衆による、生命系の未来社会論具現化の道としての「菜園家族」社会構想を深化させていかなければならない時に来ている。
克服したい研究姿勢の弱点
これまでの考察から、少なくとも2つの大切なことが明らかになってきた。
1つは、19世紀以来、資本主義超克の道として模索され世界的に展開されてきた、生産手段の社会的規模での共同所有・共同管理を優先・先行させる、従来型の社会主義理論の限界が、20世紀におけるその実践の破綻によって決定的になったにもかかわらず、不思議なことに、今なおその根本原因の省察が不徹底であるということ。
もう1つは、それ故に、19世紀以来の未来社会論に代わる新たな未来社会論、つまり未来への明確な展望を指し示し、同時に現実社会の諸矛盾をも克服していく具体的な道筋を全一体的(ホリスティック)に提起し得る21世紀の未来社会論を、いまだに構築し得ずにいるということである。
戦前においても、そして戦後においてもそうなのであるが、自らの社会が直面する諸矛盾に向き合い、その解決を探る様々な努力が成されてきたものの、広い意味での未来社会論について言うならば、その時々の時代的制約から来るところが実に大きかったとは言え、外国の理論の日本社会への模倣的適用に終始する傾向が強く、自国の現実に即して、より具体的にわが国独自の未来社会論を展開し、練りあげていくという姿勢が、あまりにも欠如していたのではなかったのか。この欠陥を克服できずに、問題を今日まで抱え込んできたと言えよう。
このこととの関連で、とりわけ戦後高度経済成長以降に限って見るならば、絶えず日陰の産業に追い遣られてきた、とりわけ農業・農村の現実に焦点を当て、第二次、第三次産業をも包摂した視座から社会を全一体的(ホリスティック)に捉え、これまで長きにわたって軽視されてきた、社会構造上の基礎的共同体である「家族」にあらためて注目し、地域社会の根源を成す人間一人ひとりの社会的生存形態それ自体の変革を通じて未来社会論を構築しようとする意識が、あまりにも希薄であったことを指摘しなければならない。
その時々の目新しい舶来の理論を追い求め、抽象レベルでの議論にあまりにも終始している昨今の状況にも、このことは如実にあらわれているのではないか。
地球温暖化による気候変動の問題にせよ、新型コロナウイルス後の社会のあり方の問題にせよ、もちろん世界の先進的な知見から学ぶことを否定するものではないが、足もとの「労働」や暮らしの実態、特に農山漁村地域がおかれている現実からかけ離れて、たとえば「ベーシック・インカム」とか、「グリーン・リカバリー」とか、外国直輸入の舶来理論を安易に持ち出し、上滑りの議論を延々と繰り返している。
そうこうしているうちに、現実世界は一向かまわず、むしろ容赦なく取り返しのつかない深刻な事態へと陥っていく。自らの弱さ故の体験からも、自戒の念を込めてそう思うのである。
5)人類史を貫く「否定の否定」の弁証法
自然界の生成・進化を律する「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)を
21世紀未来社会論の基軸にしっかり据える
既に述べたように、週休(2+α)日制のワークシェアリング(但し1≦α≦4)に拠って「菜園家族」を創出し、それを地域社会の基礎単位に位置づけ、社会の土台に組み込むことは、それに伴って、社会全体から見れば、純粋な意味での「賃金労働者」が確実に変質、減少していくことを意味している。
このことはただちに、剰余価値の資本への転化のメカニズムを揺るがし、資本の自己増殖運動を社会のおおもとから抑制し、次第に資本を衰退へと向かわせていくことになる。
これは結果として、「資本の自然遡行的分散過程」を社会の基層から促していくことにもつながるのである。
つまり、地域住民一人ひとりが生きんがために自己の生活防衛として行う、日常普段のこうした「菜園家族」創出の営為は、一見地味で緩慢に見えるが、それは、地域に抗市場免疫の自律的世界を着実に拡充していくプロセスでもあり、ますます強まる資本主義の横暴を社会の基底から抑制し、資本主義そのものをゆっくり時間をかけて確実に衰退へと導き、ついには近代を超克する自然循環型共生社会(じねん社会としてのFP複合社会)への体制転換を促していく大きな原動力になる。
「菜園家族」の創出という、一見些細に見える個々人の身近な生活の場での日常普段の努力の積み重ねそのものが、実は射程の長い世界史的意義をもつ人間的営為であることを、ここであらためて確認しておきたい。
人類が究極において、大自然界の中で生存し続けるためには、人間社会の生成・進化を規定している極めて人為的で反自然的な「指揮・統制・支配」の特殊原理を、自然界の摂理ともいうべき「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)へと、実に長い年月をかけて戻していかなければならない。このことについては既に述べてきた。
本当の意味での持続可能な自然循環型共生社会の実現とは、浮ついた「エコ」風潮に甘んずることなく、まさに人間社会の生成・進化を律する原理レベルにおいて、この壮大な自然界への回帰と止揚(レボリューション)を成し遂げることにほかならない。
大自然界の摂理に背き、人類が自らつくり出した核兵器と原発、つまり核エネルギーの開発と利用という自らの行為によって、無惨にも母なる自然を破壊し、自らのいのちと自らの運命を絶望の淵に追い遣っている今こそ、人間存在を大自然界に包摂する新たな世界認識の枠組みを構築し、その原理と思想を地球環境問題や未来社会構想の根っこにしっかりと据えなければならないのである。
自然界の生成・進化を貫く「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)を人間社会に体現するかのように、人間の社会的生存形態と家族や地域のあり方を根源から変えながら、次代のあるべき姿へと時間をかけてじっくりと熟成させていく。それはまさに、「菜園家族」による“静かなるレボリューション”の長い長い過程なのである。
これまで人類が成し遂げることができなかったこの壮大な課題が、3・11東日本大震災・福島原発苛酷事故、地球温暖化による気候変動、新型コロナウイルス・パンデミック、そしてウクライナ戦争、ガザにおける恐るべきジェノサイドに象徴される世界的複合危機に直面したまさに今、21世紀に生きる私たちに最後の機会として与えられている。
この課題から逃げることなく、真っ正面に据えて取り組む。こうしてはじめて、18世紀イギリス産業革命以来、二百数十年にわたる近代を根底から超克する道は、大きく開かれていくのではないだろうか。
自然への回帰と止揚(レボリューション」)、これこそが民衆の本源的な歴史思想である
新自由主義的市場原理至上主義アメリカ型「拡大経済」を克服し、グローバル市場に対峙する原発のない「抗市場免疫の自律的世界」、つまり「菜園家族」を基調とする、素朴で精神性豊かな自然循環型共生社会(じねん社会としてのFP複合社会)を創出する主体は、紛れもなく「菜園家族」自身である。
その意味で、「生命の思想」、そして「自然(じねん)の思想」に裏打ちされた、社会の深層からのこの“静かなるレボリューション”による21世紀の社会変革の道は、“菜園家族レボリューション”とでも言うべきものなのかもしれない。
“菜園家族レボリューション”
これを文字どおりに解釈すれば、「菜園家族」が主体となる革命ということである。
しかし、“レボリューション”には、大自然界と人間界を貫く、もっと深遠な哲理が秘められているように思えてならない。
それはもともと旋回であり、回転であるが、天体の公転でもあり、季節の循環でもある。そして何よりも、原初への回帰を想起させるに足る壮大な動きが感じとれる。
イエス・キリストにせよ、ブッダにせよ、わが国近世の稀有なる思想家安藤昌益にせよ、19世紀のマルクスにせよ、インドの偉大なる思想家ガンジーにせよ、あるいはルネサンスやフランス革命にしても、レボリューションの名に値するものは、現状の否定による、原初への回帰の情熱によって突き動かされたものである。
現状の否定による、より高次の段階への回帰と止揚(レボリューション)。それはまさに、事物の発展の根源的哲理とも言うべき「否定の否定」の弁証法なのである。
21世紀の今、気候変動、新型コロナウイルス・パンデミック、ウクライナ戦争、ガザにおけるジェノサイドとも言うべき凄惨な虐殺という複合危機の中で、再び世界の人々を襲っている未曾有の経済格差と社会的分断。
今日の混迷の中から、私たちが、そして世界が探しもとめているものは、エコロジーの深い思想に根ざした、ほんものの自然循環型共生社会への確かな糸口である。
その意味でも、21世紀生命系の未来社会論具現化の道とも言うべき「菜園家族」社会構想は、「辺境」からのささやかな試みではあっても、その夢は大きいと言わなければならない。
現代工業社会の廃墟の中から、それ自身の否定によって、田園の牧歌的情景への回帰と人間復活の夢を、この“菜園家族レボリューション”のことばに託したいと思う。
人は明日があるから、今日を生きるのである。
21世紀、失望と混迷の中から、人々は、人類始原の自由と平等と友愛のおおらかな自然状態を夢見て、素朴で精神性豊かな自然(じねん)世界への壮大な回帰と止揚(レボリューション)、原初的「共感能力」(慈しむ心)の再建、人間復活の高次自然社会への道を歩みはじめるにちがいない。
自然観と社会観の分離を排し、両者合一の思想を社会変革のすべての基礎におく
わが国の先駆的思想家であり、『自然真営道』の著者として世に知られる安藤昌益(1703~1762)は、江戸幕藩体制のただ中に、出羽国の大館盆地南部に位置する二井田村(現秋田県大館市)に生まれた。
昌益の用いる「自然」の一語には、宇宙の全存在の「自(ひと)り然(す)る」、すなわち自律的自己運動性と、作為の加わらぬ天然性と、権力の加わらぬ無階級性、男女平等性が含意されている。
人類の太古には、全員が耕し、平等に暮らした共同社会があったと想定する。そこでは、生態系は自然のままに循環し、人は労働することで自然の治癒力が十分にはたらき、みな無病息災であった。そこにはゆったりとした豊かさがあり、すべては自然のままに上下、貴賤、貧富の差別のない万人直耕の無階級社会であったとして、これを「自然世(じねんのよ)」と名付けた。
こうして、自己充足的な集落や村など、小単位の自治的農民共同体の社会が、もっとも自然なものとされた。自然観と社会観を分離する考え方を排し、人類始原の自然状態の存在を直感し、確信し、それを自己の理論的全体系の基礎に据えたのである。
昌益のまさにこの「自然世」こそ、「菜園家族」を基調とする自然循環型共生社会の原形を成すものではないのか。
マルクスの『資本論』(初版発行1867年)に先行すること100年、今からおよそ260年も前に、わが国の風土の中から、世界史的にも稀な独自の思想が生み出されたことに驚かされるとともに、同じこの山河に生きるひとりの人間であることをひそかに誇らしく思う。
この思想的伝統を、21世紀混迷のこの時代にあってどう受け継ぎ、未来へと創造的に展開できるのか。生命系の未来社会論具現化の道としてのこのささやかな「菜園家族」社会構想が、そのことを探る出発になればと願う。
めざすべき永遠の彼方の「高次自然社会の内実」と、そこへ至る長い実践のプロセス、つまり「静かなるレボリューション」のいわば「静」と「動」のこの両者が、相互に作用をおよぼし合いながら、絶えず共進化を遂げていく。
まさにこの理念と現実との対立・矛盾の葛藤を通して、さらなる高次の段階へと展開する終わりのない自律的自己運動の総体を、ここでは今日一般に用いられている自然(ネイチャー)と区別して、昌益に学び、敢えて「自然(じねん)」と呼ぶことにしよう。この「自然(じねん)」こそが本構想の真髄でもあるのだ。
悠久の時空のなか
人は大地に生まれ
育ち
大地に還ってゆく
6)混迷の時代だからこそ見失ってはならない未来社会への展望
―避けては通れない近代桎梏からの解放
人間社会のあるべき姿を、宇宙、すなわち大自然界における物質世界と生命世界の生成・進化のあらゆる現象を貫く、自然の摂理とも言うべき「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)に照らして考える。つまり、自然観と社会観の分離を排し、両者合一の思想を社会変革のすべての基礎に置く。
このことが、21世紀生命系の未来社会論具現化の道としての「菜園家族」社会構想の大前提であるとともに、この「構想」を首尾一貫して貫く哲理とも言うべきものであることを、ここであらためて確認しておきたい。
微に入り細をうがつ目から一旦離れ、人類史を長いスパンで大きく捉えるならば、この「菜園家族」社会構想の根底に流れる人類の未来を見据えた歴史観、およびその展開のメカニズムの論理と意義は、以下のようになるであろう。
<自然への回帰と止揚(レボリューション)の歴史過程>
原始自然社会 → 古代奴隷社会 → 中世封建社会 → 近代資本主義社会 →「菜園家族」基調のCFP複合社会 → じねん社会としての脱資本主義FP複合社会(自然循環型共生社会)→ 高次自然社会(国家権力の自然消滅、人間の全面的開花)
以上の人類史の全過程を、人間の社会的生存形態に着目して捉えるならば;
原始自由身分 → 古代奴隷身分(低次奴隷身分)→ 中世農奴身分 → 根なし草同然の近代賃金労働者(高次奴隷身分)→ CFP複合社会における抗市場免疫の「菜園家族」的身分 → じねん社会としての脱資本主義FP複合社会(自然循環型共生社会)における「菜園家族」的自律身分 → 高次自然社会における高次自由身分
となる。
同じく、人類史の全過程を、直接生産者としての「人間」と「生産手段」両者の関係に着目し、それを重視して捉えるならば;
原始自然社会における両者融合の状態 → 古代奴隷制における両者の完全分離の状態(低次奴隷状態)→ 中世封建制下での両者再結合への途上での未成熟の状態 → 近代資本主義における両者の大がかりで徹底した完全分離の特殊状態(高次奴隷状態)→「菜園家族」基調のCFP複合社会下での両者再結合への途上での未成熟の状態 → じねん社会としての脱資本主義FP複合社会(自然循環型共生社会)下での両者再結合の成熟期の状態 → 高次自然社会における両者の最終的かつ完全なる再融合の状態
となる。
つまり、直接生産者である人間から生産手段が完全に分離した、かつての古代奴隷制時代の奴隷状態が、近代資本主義に至り、高次奴隷状態となって、再び亡霊の如く執拗に現れてくることに刮目したい。
このように、「人間」と「生産手段」両者の完全分離状態が、近代に至って執拗に再現したのはなぜか。
その理由は、ここまでに考察してきたように、人類がその始原の段階から大自然界の中にありながら、他の哺乳動物には見られないほど特異で異常なまでに頭脳の発達を遂げ、その結果、道具の飛躍的な発達を促し、剰余価値を生み出すことが可能になったこと。
それを契機に、人間社会の生成・進化を律する原理が、大自然界の生成・進化を貫く「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)から、極めて人為的で反自然的な「指揮・統制・支配」の特殊原理に転換し、その異質な原理によって、執拗なまでに徹底して大がかりに人間社会が組織・編成されてきたことにある。
それはあたかも、人体の局所に発症した悪性の癌細胞が、人体の一部でありながら、その発達が人体の他の細胞とは異質の原理に拠るが故に、異常増殖を引き起こし、転移を繰り返しながら、ついには人体そのものを蚕食するまでに至るメカニズムと驚くほど酷似している。
近代に至って、かつての古代奴隷制時代の奴隷状態に回帰したこと、すなわち「人間」と「生産手段」両者の完全分離状態が、近代において高次奴隷状態として再現した理由をこのように捉えるならば、資本主義を超克するという難題に直面している私たちは、まず人間社会の生成・進化のこの原理レベルにおける歴史的特殊性を認識し、自覚することが如何に大切であるかが、自ずと分かってくるはずである。
そして、そこから自ずから導き出されてくる私たちの今日の課題は、「生産手段と直接生産者との再結合」を基礎に構想される、まさに21世紀生命系の未来社会論具現化の道としての「菜園家族」社会構想であることが、論理的にも、現実社会の実態からも頷けるのではないだろうか。
さて、以上述べてきた人類史の全過程を、人間の社会的生存形態に着目し、かつ経済的搾取・被搾取による経済的格差を梃子に形成される、人間の人間による支配・被支配の社会的階級関係に視点を据えて要約すれば、それは大きく次の3つの時代に区分される;
原始自然社会(無階級)→ 階級社会 → 高次自然社会(無階級)
(1) (2) (3)
つまり、無階級社会の原始自然社会から、さまざまな階梯の階級社会を経て、それ自身を止揚して、高次自然社会としての無階級社会に再び回帰していくことが分かる。ここにも、歴史における「否定の否定」の哲理としての弁証法が貫かれている。
上記(1)、(2)、(3)の各ステージにおける、人間社会の生成・進化を律する基本原理は;
(1)のステージにおいては、自然界を貫く「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)
(2)のステージにおいては、極めて人為的で反自然的な「指揮・統制・支配」の特殊原理
(3)のステージにおいては、自然界と人間社会を貫く「適応・調整」の普遍的原理(=「自己組織化」)
となり、人間社会は生成・進化の原理レベルにおいても、人類始原における自然界の生成・進化を貫く「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)から、極めて人為的で反自然的な「指揮・統制・支配」の特殊原理を経て、やがてはるか未来において、再び自然界の生成・進化を貫く「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)に回帰していくことが分かる。
つまり人類史は、人間社会の生成・進化の原理レベルにおいても、「自然への回帰と止揚(レボリューション)の歴史過程」として捉えることができよう。
21世紀未来社会論の核心 ―自然との再融合、原初的「共感能力」(慈しむ心)の再建
これからの21世紀未来社会論は、人類史の基底に脈々として受け継がれてきた、この「自然への回帰と止揚(レボリューション)」という歴史思想、つまり、いつの時代にも人々の心の中に脈々と息づいてきた「自然との再融合」、そして何よりも「原初的『共感能力』(慈しむ心)の再建」を願う民衆の切なる歴史思想に、しっかり裏打ちされたものでなければならない。
そして大切なことは、はるか彼方のあるべき理想の未来社会と現実とのあいだに、抗市場免疫の「菜園家族」を基調とするCFP複合社会という中間過程を設定することによってはじめて、長期にわたる創造性豊かなこの複合社会の生成・展開の全過程を通じて、人々が自らの日常普段の生産と暮らしの身近な場において自己を鍛錬し、自らの社会と世界の道理を深く究め、優れた英知を獲得し、やがて民衆自らが、自己を歴史の真の変革主体に変えていくことが可能になるという点にある。
こうしてこそ、近代以降、長きにわたって欺瞞の「選挙」のみに矮小化され、形骸化した上っ面だけの「民主主義」に甘んじる現状を排し、為政者に決して騙され、翻弄されることのない主体的力量の涵養と、真の草の根民主主義思想の熟成は可能になるのである。
しかも、この中間プロセスCFP複合社会は、「家族」と「地域」と「労働」という身近な場から、自らの手で、次代の生産と暮らしの礎を一つひとつ時間をかけて丹念に積み上げていく、実に根気のいる長期にわたる過程でもある。
それは同時に、“高次自然社会への道”(その7)で詳述したように、「菜園家族」の台頭による資本の自然遡行的分散過程であり、これまでとは全く異次元の、身の丈に合った「潤いのある小さな科学技術」の新たな体系が生成・構築され、自然循環型共生社会にふさわしい生産と暮らしのあり方が形成されていく重要なプロセスにもなっているのである。
こうした実に長期にわたる抗市場免疫の「菜園家族」を基調とするCFP複合社会という中間項としてのプロセス、つまり、「地域」や「労働」の現場に深く根を張った粘り強い民衆運動を抜きにしたどんな「革命」も、たとえそれがおざなりの「選挙」による「議会」を通じて一時期政権を掌握できたとしても、結局は、民衆の精神的・物質的力量の脆弱さ故に綻(ほころ)びを見せはじめ、新たな専制的権力の跳梁を許し、ついには挫折せざるを得ない。
この重い歴史的教訓の核心こそが、「菜園家族」による“静かなるレボリューション”に込められた変革の根源的な思想なのである。
日本列島を縦断する脊梁山脈を分水嶺に、太平洋と日本海へと水を分け迸(ほとばし)る数々の山中の渓流は、やがて大きな流れとなって平野部をよぎり、ゆったりと大海に注いてゆく。
川上の渓流に寄り添い息づく奥山の集落。そして、中・下流域の各地に形成される大小さまざまな都市の住民たち。
山頂から開ける広大無窮の裾野に芽吹く、これら実に個性豊かな民衆主体のエネルギーの自覚的結集こそが、高次自然社会(自然世 じねんのよ)への道を切り拓いていく。
そこには想像を絶する苦悶や困難が横たわっているが、それに勝る壮大な世界史的意義をきっと見出していくことであろう。そこにこそ、生きる喜びがある。
そこにこそ、希望の明日がある。
人は
明日があるから
今日を
生きるのです。
夜明けの歌
生あらばいつの日か
長い長い夜であった
星の見にくい夜ばかりであった、と
言い交わしうる日もあろうか・・・
1945年1月29日、友への手紙にこう綴ったわだつみの若き学徒松原成信(近江八幡市出身)は、
一縷の望みを胸に灯しつつ、同年8月1日北京にて人知れず戦病死した。享年23歳。
あまりにも短い生涯であった。※
戦後さまざまな苦難の曲折を経ながらも
それでもなお国民が追求してやまなかったもの
それは、戦争の惨禍から学び獲得した
「平和主義」、「基本的人権(生存権を含む)の尊重」、「主権在民」の
三原則に貫かれた
世界に誇る
日本国憲法の理念を遵守する精神ではなかったのか。
戦後78年を経た今日においても
なおもこの遵守の精神が
たとえ僅かであっても
人々の心のどこかに生き続けている限り
それは、あたかも自然界の
天空と大地をめぐる水の循環の如く
その一滴一滴が地層深く浸透し、地下水脈となり
いつしか地表に湧水となってあらわれ
大地を潤していく。
燦々と降り注ぐ
太陽の光をいっぱいに浴び
豊かな土と水に
ゆっくりと育まれた植物は
やがて実を結び
生きとし生けるもの
すべての喜びを祝福する
大きなエネルギーに転換される。
私たちも同じであろう。
先を焦らず
ゆっくり、しかも時間をかけて
地力を養い蓄積された
いのちのエネルギーは
醜い欺瞞と反動の闇夜を引き裂き
根源から時代を問い直す
新生「菜園家族」日本の幕開けを告げる黎明となる。
この夢は、せめて人々の心の中に
いつまでも生き続けてほしい。
いや、それどころではない。
この夢こそが
この国の
そして東アジアと
世界のすべての人々に
勇気と希望を
生きる喜びを
いつまでも与え続けていくであろう。
この小さな
幸せ祈る
私たちの心を
きっと
おぼえておいておくれ
地平を開く
夜明けの歌よ。
※ 日本戦没学生記念会 編『新版 きけ わだつみのこえ ―日本戦没学生の手記』(岩波文庫、1995年)より。
◆“高次自然社会への道”(その8)の引用・参考文献◆
マルクス、訳・解説 手島正毅『資本主義的生産に先行する諸形態』国民文庫、1970年
マルクス『経済学批判』大月書店、1970年
スチュアート・カウフマン 著、米沢登美子 監訳『自己組織化と進化の論理 ―宇宙を貫く複雑系の法則―』日本経済新聞社、1999年
メラニー・ミッチェル 著、高橋洋 訳『ガイドツアー 複雑系の世界 ―サンタフェ研究所講義ノートから』紀伊國屋書店、2011年
安藤昌益「稿本 自然真営道」『安藤昌益全集』(第一巻~第七巻)、農山漁村文化協会、1982~1983年
寺尾五郎「総合解説 ―安藤昌益の存在と思想、および現代とのかかわり」『安藤昌益全集』(第一巻)農山漁村文化協会、1982年
若尾政希『安藤昌益からみえる日本近世』東京大学出版会、2004年
川村晃生「安藤昌益の夢 ―三つのユートピア―」『ユートピアの文学世界』慶應義塾大学出版会、2008年
藤岡惇 書評『人新世の「資本論」』(斎藤幸平 著、集英社新書、2020年)『季刊 経済理論』第59巻第1号、経済理論学会 編集・発行、桜井書店、2022年
日本戦没学生記念会 編『新版 きけ わだつみのこえ ―日本戦没学生の手記』岩波文庫、1995年
同会 編『新版 第二集 きけ わだつみのこえ ―日本戦没学生の手記』岩波文庫、2003年
童話屋編集部 編『復刊 あたらしい憲法のはなし』童話屋、2001年(1947年に文部省が発行した中学校1年生用の社会科の教科書を復刻したもの)
――― ◇ ◇ ―――
★読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2024年5月3日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
◆ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」(2023年11月~2024年3月)の≪目次一覧≫は、下記リンクのページをご覧ください。
https://www.satoken-nomad.com/archives/2726
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/
菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ
https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/