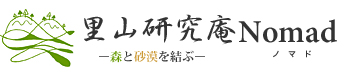
コラム「菜園家族 折々の語らい」(1)
コラム
菜園家族 折々の語らい(1)
高市自民党と日本維新の会の欺瞞の連立政権 発足に思う
―農業・農村問題の根っこから私たちの未来を考え直す―
◆ こちらからダウンロードできます。
コラム「菜園家族 折々の語らい」(1)
(PDF:433KB、A4用紙6枚分)
9月の初め、かつての滋賀県立大学時代のゼミの女子学生の父親で、湖南地域の農村で、50年以上にわたり米作りを続けてこられた篤農家のIさんから、異常とも言える猛暑の中、丹精込めて育て、収穫された新米が届いた。
添えられていた「心のふるさと 自然と農」と題する手書きのお便りには、次のような言葉が綴られていた。
「天地異変。全国各地で起こった集中豪雨や水不足による農作物への影響は大。
これまで無かった国民の米への関心。日本の主食でありながら、ここまでの話題になったことは過去にはない。飽食の時代で満足し、今日まで来たツケが廻ってきた感じ。
我が集落では、農地が70ヘクタールあり、米作りをやっている農業者は法人1ヵ所と担い手農家2戸と零細農家6戸(60アール弱の私も該当)で、残りの9割の農家が「地主農家」となっているのが現状で、今後の農地維持が大きな課題となっています。」
農業・農村問題は、「社会」の致命的なアキレス腱
どんな時代であろうとも、どんなに高度に発達した資本主義社会であっても、農業・農村問題は、「社会」の致命的なアキレス腱になる。そのことは、昨年以来の「令和のコメ騒動」によって、誰もが痛切に実感させられたところである。
本来農業は“森”と“水”と“野”を結ぶリンケージの循環の中で成立している。大小さまざまな水路の確保・維持や、農道や畦(あぜ)の草刈り、里山の保全など細やかな作業は、小規模農家や集落の“協同”の労働によって伝統的に支えられてきた。
さらに、子育て・介護など生活上の助け合いや、地域に根ざした文化も、多世代が共生する家族たちや集落によって担い育まれ、人間の潤いある暮らしを成り立たせてきた。火事、洪水、雪かき・雪おろし、地震など自然災害への対策や相互救援の活動もまた、家族間の協力や集落の協同の力なくしては考えられない。
今ここであらためて農村集落の実態を見るならば、冒頭のIさんも憂うように、農業経営の8割近くを兼業農家が占めるに至り、高齢化がすすみ、農業労働に従事することが困難になっている。農業機械がますます大型化・精密化し、高価になっている今、兼業のサラリーマンとしての給与所得を得ているうちは何とか維持できても、退職後はそれも不可能になる。そして、後継者もないまま、多くの農村で耕作放棄地が増大するとともに、農村地域コミュニティは衰退の一途を辿っている。
農水省は、その解決策として、こうした高齢化した兼業農家を集めて、「集落営農」の組織化をすすめてきたが、高齢化した個々の農家は、後継者が得られなければ遠からず自然消滅し、やがて企業の大規模農業法人に吸収されていく運命にある。
農水省がすすめてきたこのような形の「集落営農」は、先の見えない緊急避難的な対処にすぎない。いずれ遠からず、“集落”営農としての性格は完全に失われ、ついには、農業法人企業による農地の本格的な集約化と大規模化の波に呑み込まれていく。
しかも、現在、「集落営農」組織を中心的に担っている者自身が、すでに60~70歳代である。彼らは、農作業のみならず、その段取りや農家間の調整、経理などの取りまとめを一手に引き受けなければならない。その上、兼業農家であるがゆえに日々の会社勤めも重なり、過重な負担に苦しんでいるケースが多く見られる。それでは創造的で積極的なたのしい農業の再生は、望むべくもない。
そして、いくら規模拡大したところで、日本とは比較にならないほどはるかに大規模な農業を営む、米国をはじめ外国からの輸入農産物との競争に晒されたままでは、価格面からだけでも太刀打ちできないのは目に見えている。
親の苦労を見ているこうした兼業農家の若い息子や娘は、このような将来のない「農業」なら後を継ぎたいとは思わない。親も先祖伝来の田畑を自分の代で手放しては申し訳ないと、何とか維持してはいるものの、息子や娘には同じ苦労をさせたくないので、無理をしてまで継がなくてもよいとさえ思っているのが実情である。
農業を継がないこうした若者の就職先の確保は、都市部における経済成長頼みとならざるをえない。しかし、かつてのような右肩上がりの高度経済成長は望むべくもない今、親の世代にはどうにかありつけた近隣都市部での勤め口の確保も、これからの若者世代にはますます困難になるにちがいない。
これが今日の日本の農山村に共通して見られる、偽らざる実態ではないだろうか。
時どきの政権交代によって農政が若干手直しされたとしても、本質的問題は何ら解決されるものではない。工業製品の輸出拡大を狙う外需依存の「成長戦略」から脱却しない限り、貿易自由化の枠組みの中で、これまで以上に農産物の大量輸入を許し、「国際競争に生き残る農業」の名のもとに、結局は外部資本や大企業の参入をも許す、農業の規模拡大化の道を踏襲せざるをえなくなるであろう。
仮に大規模経営体(大規模専業農家、あるいは企業参入による大規模農業経営体)が競争に「生き残った」としても、農家の大多数を占める小規模農家が衰退すれば、農村コミュニティは破壊され、“森”と“水”と“野”のリンケージも維持困難に陥ることは、容易に予測されるところである。
2013年2月28日、安倍首相(当時)は施政方針演説の中で、「・・・『攻めの農業政策』が必要です。日本は瑞穂(みずほ)の国です。息をのむほど美しい棚田の風景、伝統ある文化。若者たちが、こうした美しい故郷(ふるさと)を守り、未来に『希望』を持てる『強い農業』を創ってまいります。」と心にもない空言を弄していたが、言っていることと実際にやっていることはまったく逆なのである。
「聖域なき関税撤廃」を原則としたTPPに象徴される「自由貿易」の推進や、「国際競争力」の強化によって、日本の農業・農村はいよいよ最後のとどめを刺され、地域社会は土台から崩れ、再起不能の壊滅的事態に陥ることは分かっていたはずだ。美辞麗句を並べ立てれば、農民をはじめ国民を騙すことができるとでも思っているのであろうか。
2025年の今年、「令和のコメ騒動」の渦中に起用された小泉進次郎農水大臣(当時)。就任早々の5月末、「古古古米」(2021年産米)を含む過去4年分の備蓄米の試食会でおにぎりを口にし、「率直にどれを食べてもおいしい」などと、深刻な事態のまっただ中にあって、いかにも軽い口調で感想を述べた。
戦後自民党が続けてきた農業・農村政策を反省することなく、ひたすら流通の問題に矮小化する。農業も農村の実態も知るはずのない生粋の都会人、市場原理至上主義者が、国民のいのちを支える土台とも言うべき農業・農村をどこへ導くというのか。
資本主義の胎内に胚胎する「菜園家族」型ワークシェアリングの可能性を開く
―“菜園家族群落”による日本型農業の再生
日本はもともと中山間地帯が国土の大きな割合を占め、急峻な斜面の耕地が多い土地柄である。こうした日本特有の国土や自然の条件を考えても、大規模経営体はそぐわず、日本の条件に適った中規模専業農家を育成すべきである。
そして、週休(2+α)日制のワークシェアリング(但し1≦α≦4)によって新しく立ちあらわれてくる、「労」「農」人格一体融合の抗市場免疫に優れた「菜園家族」が、こうした中規模専業農家の間をうずめていくことになるであろう。
「菜園家族」社会構想は、革新的「地域生態学」の理念と方法※1 に基づき、日本の農業・農村のあり方を長期的展望に立って見据え、兼業農家や新規就農者を週休(2+α)日制のワークシェアリングによる「菜園家族」に積極的に改造・育成していく。
そして中規模専業農家を核に、その周囲を10家族前後の「菜園家族」が囲む、いわば植物生態学で言うところの“群落”の形成を促していく。こうして形成される十数戸の家族から成る農と暮らしの村落協同体を、ここでは“菜園家族群落”と呼ぶことにしよう。
この“菜園家族群落”は、多重・重層的な地域団粒構造全体の中では、三次元の団粒「村なりわいとも」(集落レベル)の主要な構成要素に当たるものである※2 。
“菜園家族群落”の核となる中規模専業農家は、特に失業や不安定労働に悩み、農ある暮らしを求めて都会からやって来る新規就農者や、かつてふるさとの親元を離れ都会に出た帰農希望者や、兼業農家の後継者でありながら農業を知らない若い息子・娘に対して、農業技術を伝授・指導したり、堆肥をまとめて生産したりして、「菜園家族」を育成・支援する中核的な役割を果たす。
一方、新生「菜園家族」は、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)のもとに自家の「菜園」を営むほかに、集落共有の水利や農道の草刈りなど農業生産基盤の整備に参加したり、子育てや介護や除雪など暮らしの上でお互いに協力したりする。
このようにして、中規模専業農家と「菜園家族」との間に、深い相互理解と信頼に基づくきめ細やかな協力関係が、時間をかけて熟成されていく。
週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)では、例えばα=3として、週休5日制であれば、週2日の“従来型”のお勤めで安定的に得られる現金収入によって家計が補完されるので、残りの5日は、安心して「菜園」で自給のための多品目少量生産に勤しみ、大人も子どもも家族総出の創造的活動をたのしみ、自己実現をはかることになる。
若干の余剰生産物は、近所にお裾分けするか、近傍の市街地の青空市場に出品して、地域や街の人々との交流をこれまたたのしむのである。
中規模専業農家は、新鮮な地場の農産物や加工品を流域地域圏(エリア)の中核地方都市に供給し、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)の地産地消を支える。こうしてはじめて、流域地域圏(エリア)の中核地方都市も、農山漁村部とのヒトとモノと情報の密な交流によって活性化し、再生のきっかけをつかんでいく。
もちろん中規模専業農家が規模と技能を生かして、米や麦や生鮮野菜など特定の品目を量産して、近傍の中小都市、あるいは遠隔の大都市にも供給するという社会的役割は、当面は必要であろう。この社会的役割を考慮して、農産物の価格保障と所得補償は、もっぱらこの中規模専業農家に集中的になされることになる。
一方、家族小経営である週休(2+α)日制の「菜園家族」に対しては、国や地方の自治体は、あるべき未来社会の新しい芽をいかに育成するかという視点から、その創出と育成のための制度的保障や「菜園家族インフラ」の整備・拡充などの形で、CSSK方式による財政的・経済的支援を積極的におこなう必要がある※3 。
将来の農村や山村や漁村における地域編成はどうあるべきかを考える時、政府の農業への財政支援は、はっきりした長期的ビジョンもないまま、闇雲なばらまきであったり、めまぐるしく変わる「猫の目農政」であってはならない。これでは、日本の農業・農村はますます衰退していくばかりである。
新自由主義的市場原理至上主義「拡大経済」は、今や行き着くところまで行き着いた。その結果、経済や社会、教育や文化などあらゆる分野で問題が噴出している。こうした時だからこそ、農業・農村問題への施策は、20年、30年、50年先を見据えて、遠大な長期展望のもとに目標を定め、何に、何を、どのような手立てで支援していくのかを明確にした上で、財政構造そのものを根本から変革して、限られた財源を有効に活用し、メリハリをつけたものでなければならない。
農業・農村のあり方をめぐる議論は、経済効率とか、自由貿易とか、国際競争での勝ち負けといった目先の利益や都合に矮小化するものであってはならない。
しかもこのことは、「農業従事者」だけの問題にとどまるものではない。むしろこれは、戦後高度経済成長の過程で大地から引き離され、根なし草同然となって浮遊し、都市部へと流れていった圧倒的多数の現代賃金労働者(サラリーマン)の生活そのものを今後どのようにしていくのかという問題であり、都市住民のライフスタイルは今後どのようにあるべきなのかというきわめて重い、根源的な問題なのである。
つまり、今日の都市部での深刻な労働力過剰を吸収できる、基本的でしかも広大な潜在的可能性をもっているのは、長きにわたって見過ごされてきた国土面積の圧倒的部分を占める農山漁村であり、こうした可能性を生かすことによって、農山漁村自身も再生へのきっかけをつかむ。
このように、農業・農村問題は、わが国社会全体のあり方そのものの質を根底から決定づける、すべての国民共通の大テーマなのである。
熾烈なグローバル市場競争のもとでは、科学・技術の発達による生産性の向上は、人間労働の軽減とゆとりある生活につながるどころか、社会はむしろ全般的労働力過剰に陥り、失業や、派遣・期間工・パートなど不安定労働をこれから先もますます増大させていく。
“菜園家族群落”による日本型農業の再生は、こうした二律背反とも言うべきこの社会の矛盾を、次第に解消へと向かわせていくにちがいない。それを可能にする肝心要(かなめ)の梃子は、紛れもなく都市と農村の垣根を取り払い成立する、賃金労働者と農民の深い相互理解と信頼に基づく、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングなのである。
「土・日農業」という後ろ向きで、きわめて消極的な農業を長い間強いられてきた、農家の圧倒的多数を占める兼業農家をはじめ、失業と不安定労働に悩み苦しむ都市からの新規就農希望家族も、この週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングによってはじめて、時間的にも余裕のある、創造的で豊かな多品目少量生産の、人間味あふれる楽しい農業に勤しむことが可能になるであろう。
これは、戦後70年間にわたって低迷を続けてきた日本農業の大転換であり、都市住民の働き方、生き方をも根底から変え、今日の社会の混迷と閉塞状況を打ち破る決定的な鍵となる。
根なし草同然の現代賃金労働者(サラリーマン)と「菜園」という生産手段とのこの歴史的とも言うべき「再結合」を果たすことによって、市場原理の作用を抑制し、それに対抗しうる免疫を家族と地域社会の内部につくりあげ、秩序ある理性的な調整貿易のもとに、わが国の自然や国土にふさわしい、「菜園家族」型内需主導の日本独自の農ある暮らしの道(B型発展の道)※4 を追求するのか。
それとも、ただ消費のために必死に働かされる、内面生活の伴わない、浅薄でうわべだけの「経済成長」を金科玉条の如くいまだに追い求め、大地に生きる精神性豊かな未来への可能性を閉ざしてしまうのか。その選択が今問われている。
新型コロナウイルス・パンデミックと気候危機、そしてウクライナ戦争、ガザにおけるジェノサイドという凄惨な事態、世界大戦への暗雲立ちこめるこの時代、今こそ決断の時ではないのか。残された時間はそれほどない。
それにしても、旧態依然たる高市早苗自民党と、まやかしの「身を切る改革」を突如、前面に押し出し、「政治とカネ」というそもそもの問題から巧みに目を反らす日本維新の会 ―「国家観を共に」し、軍拡強硬路線で一致する両者の連立政権成立に至る、あの延々と繰り広げられた、マスメディア大合唱のもとでの長期にわたるだまし合いの騒動劇は、一体、何だったのか。
おそらくその真相と本質は、遅かれ早かれ白昼、国民の面前で明らかにされるであろう。
※1 長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」(2024年9月1日~2025年3月14日 里山研究庵Nomadホームページに連載)の第5章2節「21世紀の未来社会論、そのパラダイムと方法論の革新」を参照のこと。
※2 同上第6章6節「草の根民主主義熟成の土壌、地域協同組織体『なりわいとも』の形成過程」を参照のこと。
※3 同上第10章「気候変動とパンデミックの時代を生きる ―避けては通れない社会システムの根源的大転換―」を参照のこと。
※4 同上第6章1節「21世紀の「菜園家族」社会構想 ―「地域生態学」的理念とその方法を基軸に―」を参照のこと。
★このコラム「菜園家族 折々の語らい」は、これからも随時、掲載していく予定です。
読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2025年10月22日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/

